
新幹線と並行在来線の取扱はJRの旅客営業規則をめぐるFAQの一分野である。 JRの旅客営業規則第16条の2は、新幹線と在来線は同一路線として取り扱うと定めているが、さまざまな制度上の矛盾が指摘されている。 その問題点を紹介し、これを解消するための旅規の改定案を考えてみたい。目次
旅客営業規則の条項 新幹線経由の表示 新在別線区間に係わる乗車券 発着駅の例 接続駅の例 選択乗車による重複乗車 新在別線通過型 新幹線独立駅発着型 新在接続(通過・発着)型 図1 新在別線通過型選択乗車による復乗のタイプ
表1 新在別線通過型選択乗車による復乗
図2 新幹線独立駅発着型選択乗車による復乗のタイプ
表2 新幹線独立駅発着型選択乗車による復乗大都市近郊区間の取扱 表3 大都市近郊区間の取扱 新下関・博多間の特例 図3 最長片道切符の九州ルート 新在別線の原則に
原則:東海道、山陽、東北(東京・盛岡間)、上越、九州(博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間)、西九州(諫早・長崎間)の各新幹線とこれに並行する在来線は、山陽新幹線の新下関・博多間を除き、同一の線路として取り扱う(規則第16条の2)
| (1) | 東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間 | 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間 |
| (2) | 東北本線 | 東北本線(新幹線) |
| (3) | 高崎線、上越線及び信越本線 | 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線) |
| (4) | 鹿児島本線中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間 | 鹿児島本線(新幹線)中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間 |
| (5) | 長崎本線中諫早・長崎間 | 長崎本線(新幹線) |
新幹線と並行在来線は、同一の線路として取り扱うという原則を定めたものである。従来は全区間同一線路扱いだったものが、1996年1月の三島会社の運賃体系変更にともない新下関・博多間が第1号から外れた。
例外:新幹線の駅が並行在来線上にない場合、この駅を中間に挟む区間内の駅を発着駅または接続駅とする場合は、別線として取り扱う(規則第16条の2第2項)
新下関・博多間の特例:新下関・博多間は別線だが、乗車券の発行要件等においては、同一の線路として取り扱う(規則第16条の3)
| 山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間 | 山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間 |
この条項は、乗車券の発売要件や運賃計算においては、新在を同一路線として取り扱うことを定めたものである。この条項により、東京都区内−福岡市内の往路在来線、復路新幹線の往復割引乗車券が発売される。
整備新幹線:並行在来線がJRから分離された区間については、新幹線は単一の路線として扱う(規則第16条の4)
1997年開業の北陸(長野)新幹線以降の整備新幹線(九州新幹線博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間並びに西九州新幹線諫早・長崎間を除く)は、並行在来線が経営分離され、第三セクターに移管された。なお、2022年開業の西九州新幹線の並行在来線江北(肥前山口から改称)・諫早間は上下分離し、JR九州が第2種事業者として運行を継続する。施設を保有する第3種事業者は、佐賀・長崎両県が設立した一般社団法人佐賀・長崎鉄道管理センター。
これらの条文から、JR各社において新幹線が在来線の新線増線として扱われていることがわかる。規則における新幹線の線名は、国鉄時代の線路名称を引継いだJR各社の線路名称に従っており、整備新幹線の並行在来線が存在しない区間のみが○○新幹線の通称を使用している。一方国土交通省監修の「鉄道要覧」は、全ての路線について通称を用いている[1]。
JR発足時の1987年4月1日施行の規則第263条の2には、新幹線と在来線の事業者が異なる区間で、在来線経由の乗車券を所持する旅客が新幹線に乗車する場合は、改札口で新幹線振替票を公布し、下車駅の改札口で回収する旨の規定があった。
その詳細は、旅客営業取扱基準規程(以下「基準規程」)第297条の2に次のとおり規定されていた。
この制度は国鉄分割民営化から1年経過した1988年4月1日に廃止されたが、実際には交付洩れ・回収洩れが多発し、旅規改定を待たずして取扱をやめたようだ。
これにかわってマルス券では、券面に経由を表示するとともに、[□]と[■]でそれぞれ在来線/新幹線乗車区間を示すようになった。[□]と[■]は、[・]を含めて、次のように12個または9個表示されている。
1987年の分割民営化により、東京・熱海間、米原・新大阪間、新下関・博多間で並行する路線の事業者が異なることになった。このため本来同一線扱いであるにもかかわらず、旅客会社間の運賃配分の必要から、券面の経由欄に「新幹線」等新在の別を表示することになった。
新幹線経由の表示
新幹線停車駅の改札の箇所(駅内に改札の箇所が設置されている駅については、当該箇所。以下この条において「改札口」という。)において、所定の新幹線特急券を所持していることを確認のうえ、当該旅客に交付するものとする。この場合、入鋏及び発行日付は省略するものとする。
改札口において新幹線の特別急行列車から下車した当該旅客から当該振替証を新幹線特急券等とともに回収する。回収した振替証は、回収日ごとにとりまとめ別に定めるところにより、審査課長に提出するものとする。
新幹線振替証の様式は、次のとおりとする。(様式省略)都区内−京都市内(経由・新幹線、特急券一体型):■■■■■■・・・
最初の4個(または3個)は、東京・熱海間、次が米原・新大阪間、最後が新下関・博多間を示している。
この3個または4個は、一体として新在の別を表示しているのであって、それぞれが各駅間を示しているわけではない。山手線内−静岡を、小田原まで在来線、小田原から新幹線経由で発券してくれと頼んでも、
三島−中野(経由・新幹線):■■■■・・・・・・・・
都区内−福岡市内(経由・在来線):□□□□□□□□□□□□□□□■・・・・・・・・
のようにはならない。また、新幹線乗車が考えられない次のような乗車券にも[□]が表示されている。
有楽町−成田空港:□□□□・・・・・・・・
この[□]表示は、在来線経由の乗車券で新幹線に乗車したとき、車内改札で該当区間の[□]を塗りつぶし、回収した乗車券を光学式読取装置にかけ、旅客会社間の運賃精算に使用する構想があったから、と聞いたことがある。 しかし、車掌が車内改札で[□]を塗りつぶしているのを見たことがない。まして新幹線経由の乗車券で在来線に変更するときは、[■]を[□]に戻せない。これも「新幹線振替票」と同様、構想倒れに終わってしまったらしい。
規則第16条の2第2項は、この区間を通過するときは、規則第16条の2第1項に基づき同一の線路として扱うが、この区間内の駅(両端駅を除く)が発着駅または接続駅となるときは別線として扱うという規定である。この規定により、次の乗車券は、片道乗車券として発売される。
新在別線区間に係わる乗車券
新幹線から在来線に乗り継いで発駅方向に折り返す乗車は一般的に行われているだろう。 上記の例は、静岡駅で乗り継ぎ草薙に折り返すものだが、着駅である草薙が第16条の2第2項の三島・静岡間の駅であるので、片道乗車券として発券できる。しかし、都区内(新幹線)浜松(在来線)天竜川という同様の乗車は、掛川・浜松間が第16条の2第2項に含まれず、同一線扱いのため、浜松で打ち切られ、連続乗車券となる。三島・静岡間が第16条の2第2項の区間に含まれたのは、1998年3月、同区間内に新幹線新富士駅が開業したときからである。同時に、静岡・浜松間にも、新幹線掛川駅が開業した。このとき、新富士駅が在来線から独立して設置され、掛川駅が在来線に併設されたためこのような差異が生じることとなった。
この乗車券は、三島・静岡間内の在来線駅である富士と沼津を接続駅とし、その後三島・静岡間を新幹線で通過するものであるから、片道乗車券として発券可能である。
この乗車券は、三島・静岡間内の新幹線駅である新富士を発駅とし、在来線の富士と沼津を接続駅とするものであるから、片道乗車券として発券可能である。これらの規則第16条の2第2項の区間を接続駅とする乗車券を使用して、在来線を重複して乗車すること(以下「復乗」)が可能となる。規則第157条の選択乗車区間に新幹線と並行在来線相互間の選択乗車が含まれているが、復乗を禁止する明文規定がないためである。

選択対象の()が2個あって、選択乗車区間内に2組の選択肢が示されている。すなわち、三島・静岡間を次の4通りの乗車ができることを示している。
・三島−富士−静岡先にあげた甲府−浜松(身延・東海・御殿場・小田原・新幹線経由)の片道乗車券で、この選択乗車によって、三島・静岡間を在来線に乗車することが認められる。すると、富士・沼津間の在来線が復乗となる。
・三島−新富士−静岡
・三島−富士/新富士−静岡
・三島−新富士/富士−静岡
三島・静岡間を通過するときは、もともと新在同一路線であり、富士と新富士を乗り継ぐ後者の2ケースにしか、選択乗車を定める意味がない。あえて新在別線通過型の選択乗車区間を設定し、前二者の通過型選択乗車を認めていることから、復乗を禁止する明文規定がないだけでなく、むしろ積極的にこれを認めているとも解釈しうるのである。
このような新在別線通過型の新幹線経由の乗車券で、在来線に選択乗車することによる復乗は、選択乗車区間内の在来線に分岐駅が存在する区間に生じる。ただし分岐する路線が盲腸線だけの分岐駅及び分岐駅間同士を直接結ぶルートしかない分岐駅を除く。図1でこれを模式的に示す(赤線:発券ルート、青線:実乗ルート)。
タイプA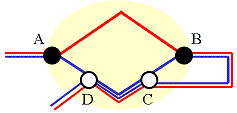 |
タイプB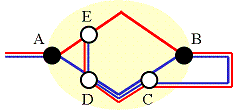 |
タイプC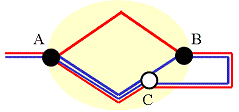 |
タイプD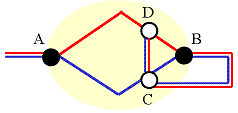 |
図1のタイプAは、A駅・B駅間の選択乗車区間の在来線にC、Dの二つの分岐駅があり、その分岐駅の一つ以上がA、Bの以遠駅と直接接続しているケースである。A・B間を新幹線経由で発券し、在来線に乗車すると、C・D間が復乗となる。タイプBは、在来線に二つの分岐駅(C、D)が存在するが、そのうちの一つが選択乗車区間内の新幹線駅(E)にしか接続していないケースである。例えば、(12)長岡以遠(宮内方面)=新潟以遠(白山・東新潟方面)は、在来線に新津(C)と東三条(D)の二つの分岐駅が存在し、そのうち新津は新潟の以遠駅と接続している。しかし、他の分岐駅である東三条から分岐する路線は選択乗車区間内の新幹線駅燕三条(E)に接続しているため、タイプAのように、選択乗車区間を通過する乗車券は発売されない。しかし、この場合でも、中間の新幹線駅(E)または両端駅(A、B)着駅とする6の字型乗車券が発売され、選択乗車によりC・D間またはC・A/B間が復乗となる。タイプCは、在来線の分岐駅が1駅のケースだが、この場合も両端駅(A、B)までの6の字型乗車券が発売され、C・A/B間が復乗となる。なお、タイプDは、タイプCのC駅から新幹線駅Dに直接接続している場合で、A・B間を新幹線経由で発券し、在来線に乗車すると、C駅で環状線一周となる9の字ルートとなる。これらの新在別線通過型選択乗車区間を表1に示す。
| 選択乗車区間 | 接続駅 | 乗車券の例 | 復乗区間 |
| (3)あおば通・仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面) (9)あおば通・仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面) |
小牛田 | (タイプC)福島−仙台/一ノ関(新幹線・一ノ関・大船渡線・気仙沼線・石巻線・東北線経由) | 仙台・小牛田間/小牛田・一ノ関間 |
| (タイプC)福島−古川(新幹線・一ノ関・大船渡線・気仙沼線・石巻線・陸羽東線経由) | 小牛田(環状線一周) | ||
| (9)福島以遠(南福島・笹木野方面)=あおば通・仙台以遠(東照宮・東仙台・榴ケ岡方面) | 岩沼 | (タイプC)南福島−仙台/福島(福島・新幹線・仙台・仙山線・奥羽線・米坂線・羽越線・磐越西線・磐越東線・常磐線・東北線経由) | 岩沼・仙台間/福島・岩沼間 |
| (12)長岡以遠(宮内方面)=新潟以遠(白山・東新潟方面) | (東三条)、新津 | (タイプB)浦佐−燕三条(新幹線・新潟・白新線・羽越線・信越線・弥彦線経由) | 新津・東三条間 |
| (タイプC)浦佐−新潟/長岡(新幹線・新潟・白新線・羽越線・信越線経由) | 新津・新潟間/長岡・新津間 | ||
| (13)高崎以遠(倉賀野・北高崎方面)=越後湯沢以遠(石打・ガーラ湯沢方面) | 新前橋 | (タイプC)本庄早稲田−高崎/越後湯沢(新幹線・越後湯沢・上越線・只見線・磐越西線・東北線・両毛線・上越線経由) | 高崎・新前橋間/新前橋・越後湯沢間 |
| (16)熊谷以遠(行田方面)=高崎以遠(高崎問屋町・北高崎・安中榛名方面) | 倉賀野 | (タイプC)行田−高崎/熊谷(熊谷・新幹線・長野・篠ノ井線・中央線・八高線・高崎線経由) | 倉賀野・高崎間/熊谷・倉賀野間 |
| (20)品川以遠(田町・大崎・西大井方面)=小田原以遠(早川方面) | 川崎、武蔵小杉、(東神奈川)、茅ヶ崎 | (タイプA)三島−八王子(新幹線・品川・山手線・中央線・南武線・東海道線・相模線経由) | 川崎・茅ヶ崎間 |
| (タイプB)舞浜−新横浜(京葉線・新幹線・小田原・東海道線・御殿場線・東海道線・横浜線経由) | 東神奈川・国府津間 | ||
| (タイプC)熱海−小田原/品川(新幹線・品川・山手線・中央線・横浜線・東海道線経由) | 小田原・東神奈川間/東神奈川・品川間 | ||
| (25)三島以遠(函南方面)=静岡以遠(安倍川方面) | 沼津、富士 | (タイプA)甲府−浜松(身延線・東海道線・御殿場線・東海道線・小田原・新幹線経由) | 富士・沼津間 |
| (タイプC)浜松−静岡/三島(新幹線・小田原・東海道線・御殿場線・東海道線経由) | 静岡・沼津間 | ||
| (28)名古屋以遠(尾頭橋・八田方面)=米原以遠(彦根・坂田方面) | 岐阜 | (タイプC)豊橋−米原/名古屋(新幹線・米原・北陸線・高山線・東海道線経由) | 岐阜・米原間/名古屋・岐阜間 |
| (30)新大阪以遠(東淀川方面)=西明石以遠(大久保方面) | 大阪、尼崎 | (タイプA)姫路−和歌山(新幹線・京都・山陰線・福知山線・東海道線・阪和線経由) | 尼崎・大阪間 |
| (タイプC)姫路−西明石/新大阪(新幹線・京都・山陰線・福知山線・東海道線経由) | 西明石・尼崎間/尼崎・新大阪間 | ||
| (48)博多南・博多以遠(吉塚・小倉方面)=久留米以遠(荒木・久留米高校前方面) | 原田、(鳥栖) | (タイプB)筑後船小屋−新鳥栖(新幹線・博多・鹿児島線・篠栗線・筑豊線・鹿児島線・長崎線経由) | 鳥栖・原田間 |
| (タイプC)筑後船小屋−博多/久留米(新幹線・博多・鹿児島線・篠栗線・筑豊線・鹿児島線経由) | 原田・博多間/久留米・原田間 |

ここでも、選択乗車による復乗が可能となる。新富士−御殿場(新幹線・小田原・東海・相模・中央東・身延・東海・御殿場経由)の片道乗車券で、選択乗車により、新富士・三島間を富士駅から在来線に乗車(富士・三島間)することが可能であり、富士・沼津間が復乗となる。
新幹線独立駅発着型選択乗車による復乗は、選択乗車区間内の在来線に分岐駅が存在する区間だけでなく、すべての選択乗車区間に生じる。一方の以遠駅を越えて他方の以遠駅に連絡する他のルートが存在するためである。これを図2の模式図に示す。
タイプA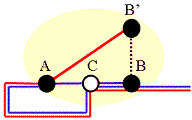 |
タイプB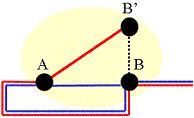 |
タイプC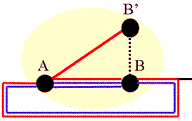 |
| 選択乗車区間 | 接続駅 | 乗車券の例 | 復乗区間 |
| (3)一ノ関以遠(有壁・真滝方面)=水沢江刺・水沢以遠(金ヶ崎方面) | − | (タイプC)水沢江刺−一ノ関(新幹線・古川・陸羽東線・奥羽線・北上線・東北線経由) | 水沢・一ノ関間 |
| (4)北上以遠(村崎野・柳原方面)=水沢江刺・水沢以遠(陸中折居方面) | − | (タイプC)水沢江刺−北上(新幹線・北上・北上線・奥羽線・陸羽東線・東北線経由) | 水沢・北上間 |
| (6)あおば通・仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=くりこま高原・新田以遠(石越方面) | 小牛田 | (タイプA)くりこま高原−一ノ関(新幹線・仙台・仙石線・石巻線・東北線経由) | 新田・小牛田間 |
| − | (タイプC)くりこま高原−仙台(新幹線・仙台・仙山線・奥羽線・北上線・東北線経由) | 新田・仙台間 | |
| (7)一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)=くりこま高原・新田以遠(石越方面) | − | (タイプC)くりこま高原−一ノ関(新幹線・一ノ関・大船渡線・気仙沼線・石巻線・東北線経由) | 新田・一ノ関間 |
| (8)小牛田以遠(松山町・上涌谷方面)=くりこま高原・新田以遠(石越方面) | − | (タイプC)くりこま高原−小牛田(新幹線・小牛田・石巻線・気仙沼線・大船渡線・東北線経由) | 新田・小牛田間 |
| (10)福島以遠(南福島・笹木野方面)=白石蔵王・白石以遠(越河方面) | − | (タイプC)白石蔵王−福島(新幹線・福島・奥羽線・仙山線・東北線経由) | 白石・福島間 |
| (11)あおば通・仙台以遠(東照宮・東仙台・榴ケ岡方面)=白石蔵王・白石以遠(東白石方面) | 岩沼 | (タイプA)白石蔵王−福島(新幹線・仙台・仙山線・奥羽線・東北線・磐越東線・常磐線・東北線経由) | 白石・岩沼間 |
| − | (タイプC)白石蔵王−仙台(新幹線・仙台・仙山線・奥羽線・東北線経由) | 白石・仙台間 | |
| (14)越後湯沢以遠(石打・ガーラ湯沢方面)=上毛高原・後閑以遠(沼田方面) | − | (タイプC)上毛高原−越後湯沢(新幹線・越後湯沢・上越線・只見線・磐越西線・東北線・両毛線・上越線) | 後閑・越後湯沢間 |
| (15)高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=上毛高原・後閑以遠(上牧方面) | 新前橋 | (タイプA)上毛高原−越後湯沢(新幹線・大宮・東北線・両毛線・上越線経由) | 後閑・新前橋間 |
| − | (タイプC)上毛高原−高崎(新幹線・長野・飯山線・上越線経由) | 後閑・高崎間 | |
| (17)熊谷以遠(行田方面)=本庄早稲田・本庄以遠(神保原方面) | − | (タイプC)本庄早稲田−熊谷(新幹線・大宮・東北線・両毛線・上越線・高崎線経由) | 本庄・熊谷間 |
| (18)高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=本庄早稲田・本庄以遠(岡部方面) | 倉賀野 | (タイプA)本庄早稲田−大宮(新幹線・長野・篠ノ井線・中央線・八高線・高崎線経由) | 本庄・倉賀野間 |
| − | (タイプC)本庄早稲田−高崎(新幹線・高崎・上越線・両毛線・東北線・高崎線経由) | 本庄・高崎間 | |
| (23)三島以遠(函南方面)=新富士・富士以遠(富士川・柚木方面) | 沼津 | (タイプA)新富士−御殿場(新幹線・小田原・東海道線・相模線・横浜線・中央線・身延線・東海道線・御殿場線経由) | 富士・沼津間 |
| − | (タイプC)新富士−三島(新幹線・小田原・東海道線・相模線・横浜線・中央線・身延線・東海道線経由) | 富士・三島間 | |
| (24)静岡以遠(安部川方面)=新富士・富士以遠(吉原方面) | − | (タイプC)新富士−静岡(新幹線・豊橋・飯田線・中央線・身延線・東海道線経由) | 富士・静岡間 |
| (26)名古屋以遠(尾頭橋・八田方面)=岐阜羽島・岐阜以遠(木曽川・長森方面) | − | (タイプC)岐阜羽島−名古屋(新幹線・名古屋・中央線・太多線・高山線・東海道線経由) | 岐阜・名古屋間 |
| (27)米原以遠(彦根・坂田方面)=岐阜羽島・岐阜以遠(木曽川・長森方面) | 岐阜 | (タイプB)岐阜羽島−名古屋(新幹線・米原・北陸線・高山線・東海道線経由) | 岐阜(環状線一周) |
| − | (タイプC)岐阜羽島−米原(新幹線・米原・東海道線・草津線・関西線経由) | 岐阜・米原間 | |
| (31)新大阪以遠(東淀川方面)=新神戸・神戸以遠(兵庫方面) | 大阪、尼崎 | (タイプA)新神戸−和歌山(新幹線・京都・山陰線・福知山線・東海道線・阪和線経由) | 尼崎・大阪間 |
| − | (タイプC)新神戸−新大阪(新幹線・京都・山陰線・福知山線・東海道線経由) | 神戸・新大阪間 | |
| (32)西明石以遠(大久保方面)=新神戸・神戸以遠(元町方面) | − | (タイプC)新神戸−西明石(新幹線・西明石・山陽線・加古川線・福知山線・山陰線・東海道線経由) | 神戸・西明石間 |
| (35)福山以遠(東福山・備後本庄方面)=新尾道・尾道以遠(糸崎方面) | − | (タイプC)新尾道−福山(新幹線・福山・福塩線・芸備線・山陽線経由) | 尾道・福山間 |
| (36)三原以遠(本郷・須波方面)=新尾道・尾道以遠(松永方面) | − | (タイプC)新尾道−三原(新幹線・広島・芸備線・福塩線・山陽線経由) | 尾道・三原間 |
| (38)三原以遠(糸崎・須波方面)=東広島・西条以遠(八本松方面) | − | (タイプC)東広島−三原(新幹線・三原・呉線・山陽線経由) | 西条・三原間 |
| (39)広島以遠(横川・矢賀方面)=東広島・西条以遠(西高屋方面) | − | (タイプC)東広島−広島(新幹線・広島・芸備線・福塩線・山陽線経由) | 西条・広島間 |
| (41)広島以遠(天神川・矢賀方面)=新岩国・岩国以遠(南岩国・西岩国方面) | − | (タイプC)新岩国−広島(新幹線・広島・芸備線・三江線・山陰線・山口線・山陽線経由) | 岩国・広島間 |
| (42)徳山以遠(新南陽方面)=新岩国・岩国以遠(和木方面) | − | (タイプC)新岩国−徳山(新幹線・新山口・山口線・山陰線・三江線・芸備線・山陽線経由) | 岩国・徳山間 |
| (46)博多南・博多以遠(吉塚・小倉方面)=新鳥栖・鳥栖以遠(肥前旭方面) | 原田、(鳥栖) | (タイプA)新鳥栖−新鳥栖(新幹線・博多・鹿児島線・篠栗線・筑豊線・鹿児島線・長崎線経由) | 鳥栖・原田間 |
| − | (タイプC)新鳥栖−博多(新幹線・博多・鹿児島線・篠栗線・筑豊線・後藤寺線・日田彦山線・久大線・鹿児島線経由) | 鳥栖・博多間 | |
| (47)久留米以遠(荒木・久留米高校前方面)=新鳥栖・鳥栖以遠(田代方面) | − | (タイプC)新鳥栖−久留米(新幹線・久留米・久大線・日田彦山線・後藤寺線・筑豊線・鹿児島線経由) | 鳥栖・原田間 |
| (50)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=新大牟田・大牟田以遠(荒尾方面) | − | (タイプC)新大牟田−筑後船小屋(新幹線・久留米・久大線・豊肥線・鹿児島線経由) | 大牟田・筑後船小屋間 |
| (51)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=新玉名・玉名以遠(肥後伊倉方面) | − | (タイプC)新玉名−筑後船小屋(新幹線・久留米・久大線・豊肥線・鹿児島線経由) | 玉名・筑後船小屋間 |
| (53)熊本以遠(川尻・平成方面)=新大牟田・大牟田以遠(銀水方面) | − | (タイプC)新大牟田−熊本(新幹線・熊本・豊肥線・久大線・鹿児島線経由) | 大牟田・熊本間 |
| (54)熊本以遠(川尻・平成方面)=新玉名・玉名以遠(大野下方面) | − | (タイプC)新玉名−熊本(新幹線・久留米・久大線・豊肥線・鹿児島線経由) | 玉名・熊本間 |
規則第16条の2第2項の新在別線区間のうち、新幹線の中間駅が並行在来線と接続する別の路線に設置されている区間の一部に設定されており、通過型と発着型の2タイプがある。ここでは、仙台・小牛田間と小牛田・一ノ関間の二つの新在接続(通過)型選択乗車区間を紹介する。


二つの新在接続(通過)型選択乗車区間を併用すれば、仙台−一ノ関の乗車券(新在の経由を問わず)で、仙台−古川−小牛田、小牛田−古川−一ノ関と乗り継ぐことが可能であり、小牛田・古川間が復乗となる。二つの新在接続(通過)型選択乗車区間が連続しているケースは、この区間だけである。
| 新幹線経由 | 在来線経由 | |
| 有効期間 | 2日 | 1日 |
| 途中下車 | 可 | 不可 |
| 券面経路以外の選択乗車 | 不可 | 可 |
| 乗り越し(山手線内通過の乗り越し) | 打ち切り計算(出口駅からの運賃収受) | 発駅からの差額計算 |
しかし、新在同一扱いの原則および新在別線扱い区間の選択乗車の規則が存在するから、次のように、新幹線経由の乗車券を購入し在来線に乗車して途中下車するなど、目的にあわせて最適の発券方法をとることが可能である。
例えば松戸・熱海間の新幹線経由の乗車券で、在来線に乗車し、在来線の駅(例えば大船、真鶴)で途中下車ができるか。新幹線経由の乗車券では、品川や小田原のような新在同一駅では可能であろうが、それ以外の駅ではどうだろう。しかし、大船で途中下車するときは、小田原まで在来線経由、小田原から熱海までを新幹線経由で発券すれば、大都市近郊区間相互発着にはならず途中下車可である。 真鶴の場合は、その逆に小田原まで新幹線、小田原から熱海を在来線経由とすればよい。もちろん、券面上新幹線経由の区間も在来線に乗車可能であり、全区間在来線を利用して途中下車ができることになる(こんな面倒をかけずとも、同じ運賃区分の函南まで購入すれば、在来線駅での途中下車が可能ではあるが)。
一方、在来線経由の乗車券で新幹線に乗車した後、在来線の駅で途中下車することも可能である。山手線内−熱海(在来線経由)の乗車券で東京・小田原間を新幹線に乗車したのち、真鶴で途中下車できるか。実乗車経路どおりの乗車券ならば途中下車可能となるため、東京・小田原間について東海道経由から新幹線経由への区間変更(経路の変更)の取扱いをして、真鶴での途中下車を認めているようだ。
普通乗車券の発売要件に関して、新下関・小倉・博多間を従来どおり新在同一扱いとするためには、第68条4項は上述した1号及び2号の規定で十分であった。しかし、第68条第4項第3号として、「新下関又は小倉、小倉又は博多で新幹線・在来線を相互に直接乗り継ぐ場合」の規定が新設されたことにより、新在をまたがった経路でこの区間を乗車するときに片道乗車券が発券できるという解釈が生じることとなった。まずは、条文を紹介する。
この「新下関、小倉または博多で新幹線と並行在来線を相互に直接乗り継ぐときは乗継駅で営業キロ又は運賃計算キロを打ちきる」という規定が「直接乗り継がないときは、(第68条第4項第1号または第2号の規定にかかわらず)乗継駅で営業キロ又は運賃計算キロを打ちきらずに、片道乗車券として発券できる」という解釈の余地を生み出したのである。
ここで、直接乗り継ぐの解釈には、基準規程第43条の2、第116条及び第151条の3が関連している。これらの条項は、1996年1月の旅規改訂以前に存在していた西小倉・小倉間及び吉塚・博多間の分岐駅に係わる区間外乗車の規定の趣旨を引き継いだものである。煩雑になるが、基準規程は、JR各社のウェブに掲載されていないので、ここに引用する。
最長片道切符の経路に関連して、この条項は注目を浴びることになった。 すなわち、規則第68条第4項第3号を「直接乗り継がないときは、新在は別線扱いとなり片道乗車券として発券できる」と解釈すれば、「小倉(新幹線)博多(鹿児島線)吉塚(篠栗線・香椎線)香椎(鹿児島線)西小倉(日豊線)」という、従来の同一路線扱いでは認められていなかった小倉・博多間で新幹線と在来線の双方を経由する経路が選択でき、最長片道切符のルートを延長できるのである。
最長片道切符のルートを数学的に厳密な方法で求め、これを実践した葛西隆也氏のケースでは、上記の経路を含む片道乗車券が発売された。 基準規程第43条の2、第116条及び第151条の3の特例によって博多で「直接乗り継いでいない」ので、博多駅で打ち切らずに「新在別線」として扱われたようである。しかし、この区間を葛西氏に伴走した人は、博多駅ではなく、規則第68条4項1号にしたがって環状線一周となる鹿児島本線の香椎駅でキロを打ち切った連続乗車券が発券されたという。その乗車経路が葛西氏の最長片道切符の経路内であったであるにもかかわらず、片道乗車券にはならなかった。このように、第68条第4項第3号の解釈はJR各社間で統一されていない。
また、葛西氏以前に最長片道切符旅行を行った脇坂健氏の場合は、葛西氏の経路よりも短い「小倉(新幹線)博多(鹿児島線)原田(筑豊線)桂川(篠栗線)吉塚(鹿児島線)折尾(筑豊線)新飯塚」というルートを選択した。脇坂氏も片道乗車券で、新幹線(小倉・博多間)と在来線(吉塚・折尾間)の双方に乗車できたことになる。脇坂氏は、葛西氏のルートを採用しなかった理由を「(片道切符として)発券できるとはいうものの、これでは、一部区間(博多・吉塚間)を復乗しなければ乗れない「片道切符」になってしまうから」と書いている。
第68条第4項第3号は盲腸のような条項ではあるが、乗り継ぎ駅で新幹線から在来線に直接乗り継ぐ(=引き返す)場合について規定しているだけで、第68条第4項第1、2号の原則を否定しているわけではない。したがって、上記二氏のルートは、博多駅で直接乗り継いでいないのでそこで打ち切る必要はないが、第16条の3にしたがって新在を同一視した場合環状線一周となる香椎駅または吉塚駅で打ち切るという解釈が妥当と思う。
NHKは、2004年5月6日からBSで、「列島縦断鉄道12000キロの旅〜最長片道切符でゆく42日〜」を生中継で放映した。NHKの最長片道ルートの選定には葛西氏が協力しているが、新幹線と在来線を同一線として扱う解釈をとり、小倉−博多間で新幹線を使用していない。
葛西氏ルート(2000年)

|
脇坂氏ルート(1999-2000年)
 |
NHKルート(2004年)
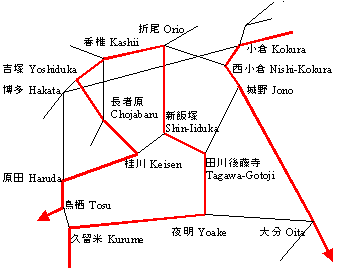 |
もともと、1964年の東海道新幹線開業時に、新幹線と在来線を同一路線と扱うことにしたのは、新幹線の運賃を在来線の営業キロで計算するための苦肉の策だった。この虚構がほころび始めたのは、1987年の国鉄分割民営化により並行する路線の事業者が異なった区間が生じてからである。1996年の三島会社の運賃制度改訂により新下関・博多間の新在の運賃が異なることとなったため、別線とせざるを得なくなった。なお、1997年の北陸(長野)新幹線開業以降は、並行在来線は第三セクターに移管され、新幹線の営業キロは実キロが適用されるようになった。
会社ごとに別路線というのが、旅客会社が期待する方向であろう。 周遊きっぷの往復券では、東海道新幹線利用の割引率が異なり、東海道在来線経由の乗車券では新幹線に乗車できないように改正された。周遊区間の細分化も旅客会社間の取り分を明確にしようと言う動きからである。しかしJR発足時の公約(分割しても全国ネットワークは維持、運賃も通算)から、完全分離というわけにもいかず、現在はこの混沌とした状態が続いている。
公約を維持しながら、新在別線の原則に営業規則を改正し、これらの矛盾は解消できるのではないかと考える。改正案の骨子は、次のとおりである。
1. 新幹線と並行在来線はすべての並行区間において別線として扱う。
規則第16条の2及び第16条の4を削除し、全ての区間で新幹線と並行在来線を別線とすることにより、東京−静岡−草薙のような片道乗車券による新幹線から在来線を乗り継いで発駅方向への折返しを、東京−浜松−天竜川など、全区間に適用することができる。
なお、JR九州の下関・博多間の賃率を本州会社と同一に戻し、新在の運賃格差を解消することにより、第16条の3も削除する。「JRの運賃計算ルールは複雑すぎる」に書いたように、この区間はJR九州が企画乗車券で割引運賃を設定しているドル箱路線であり、本州三社に比べて割高な賃率を適用する必要はない。新幹線と並行在来線を別線扱いにしても、2、3項で述べるように第69条に準じた特定区間とし、選択乗車を認めるから、往復割引乗車券で異経路を乗車できる。
なお、すべて新在別線となるから、第68条第4項3号も廃止する。最長片道切符は、葛西氏の九州内経路が取れ、現在同一路線扱いとなっている区間が別線となるので更に長くなる可能性がある。
2. 新幹線と並行在来線により環状線が形成される区間は、規則第69条に準じた特定区間とする。
規則第69条の2として、次の条項を新設する。
*は現在の第16条の2第2項による別線扱い区間で、一ノ関・北上間を除き、新在別線通過型選択乗車区間となっている。第69条の特定区間は経路を指定しないが、新幹線と並行在来線については、運賃配分のため、会社が異なる区間に限って経路を指定することにした。
なお、新幹線の営業キロを並行在来線に一致させる方針を貫く限り、「○印の経路(在来線)の営業キロによつて計算する」とする意味はない。しかし第69条特定区間の東京・蘇我間が京葉線経由でも同じ営業キロなのに、総武本線・外房線経由の営業キロで計算するとされていることから、これにあわせた。 また、上記第2号の品川・小田原間、第21号の三原・広島間、第22号の広島・徳山間及び第29号の上野・大宮間は、それぞれの区間内に、69条の特定区間である品川・鶴見間(西大井経由、○大井町経由)、三原・海田市間(呉線経由、○山陽本線経由)、岩国・櫛ヶ浜間(山陽本線経由、○岩徳線経由)、赤羽・大宮間(戸田公園・与野本町経由、○川口・浦和経由)を含む。したがって、広島・徳山間は、岩徳線の運賃計算キロで計算した山陽本線経由のキロによって、運賃・料金が計算される。
3. 第69条の2の特定区間については、大都市近郊区間相互発着の乗車券を除き、新幹線と在来線の選択乗車を認める。
第158条の2を以下のとおり新設して、第69条の2の特定区間についても、第69条の特定区間と同様、運賃計算経路以外の他経路の乗車(新幹線→在来線)を認める。ただし、新幹線はすべて大都市市近郊区間から除き、大都市市近郊区間内相互発着の乗車券については新在の選択乗車を認めない。
大都市近郊区間では選択乗車を認めないことにより、発売した乗車券を基準にして、有効日数、途中下車・う回乗車の可否、乗り越し時の精算方法を適用する。
第158条の2を新設し、第157条の選択乗車区間から、新在別線通過型選択乗車区間を削除する。これによって、新幹線と並行在来線の双方にまたがる乗車券で、新幹線と在来線の選択乗車により在来線を復乗することが排除できる。先にあげた甲府−浜松(身延・東海・御殿場・小田原・新幹線経由)の片道乗車券は、三島・静岡間で在来線と新幹線にまたがっているので、第69条の2の規定により発売した普通乗車券とはならず、富士・沼津間の在来線が復乗となる選択乗車は認められない。
4. 幹独立駅発着型選択乗車区間は、第157条の選択乗車区間として存続するが、復乗を排除する規定を付け加える。
この際、新幹線独立駅での発着に限定せず、通過型選択乗車区間の中間の新在対応駅で、新幹線・在来線の相互乗り継ぎを認めるように改定する。その結果、第157条の新在別線関連の選択乗車区間は、以下のとおりとなる(赤字は現行条文の変更部分。取消し線は2014年4月1日廃止の選択乗車区間)。
現行の選択乗車区間の第2号は、「北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)」であるが、これを第69条の2の特定区間に移管するにあたり、中間の新在対応駅である花巻・新花巻で新幹線・在来線の相互乗り継ぎを認めるために(*)を加える。また、第35号と第36号は、現行の第38号「新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)」の規定を反映して修正した。
復乗排除の規定は、第157条第1項本文に次の赤字部分を追加することにする。
新富士−御殿場(新幹線・小田原・東海・相模・中央東・身延・東海経由)の片道乗車券で、選択乗車により新富士・三島間のかわりに富士駅から在来線に乗車(富士・三島間)することは、身延線で富士に戻った時点で環状線一周となるため認められない。いかがだろうか。
| [1] | JRの路線名は、各社が定めて公告した「線路名称」と鉄道事業法に基づき国土交通省が「許可」(JR発足当時は「免許」)した路線名の2種類がある。前者は、鉄道院時代の1909年10月12日に制定された部線体系の「国有鉄道線路名称」に由来し、以後国鉄、JRに継承されてきた。後者は、1981年3月11日公布・施行の「日本国有鉄道経営再建特別措置法施行令」の別表1(将来JR各社が国鉄から承継する線名・区間)が起源であり、JR発足時にこれを「事業基本計画」として運輸大臣に提出することにより、鉄道事業法に基づく免許を受けたものとみなされた。両者の線名・区間は、新幹線名の表記のほか、次の点が異なっている。「鉄道要覧」に記載されている線名は後者のものであるが、掲載の順序は線路名称順である。
|
||||||||||||
| [2] | 2011年3月12日の九州新幹線博多・新八代間開業によって、最長片道切符の九州北部ルートが変更になった。最長片道切符ルートの変遷2011年3月12日の項参照 |
| 2004/03/15: | 2004/03/13の九州新幹線及び上越新幹線本庄早稲田駅の開業に伴う旅規改訂を反映(赤字で注記) |
| 2004/04/19: | 「新下関・博多間の特例」を加筆 |
| 2004/05/22: | 2004/03/13の旅規改訂を本文中に反映し、「大都市近郊区間の取扱」を改訂。 「新下関・博多間の特例」に「NHK列島縦断鉄道12000キロの旅」のルートを加筆。 |
| 2004/11/29: | 引用と表のスタイル変更 |
| 2004/12/28: | 「新下関・博多間の特例」を加筆 |
| 2006/07/13: | 他のページの表現に合わせて、「幹在」を「新在」に変更。「新下関・博多間の特例」の脇坂氏の項を改訂、リンクを更新。「新在別線の原則に」に旅規の改訂案(69条の2)を掲載し、大幅に加筆 |
| 2006/10/21: | 目次の設置 |
| 2009/01/31: | 読者の指摘を受け誤記等を訂正 |
| 2012/03/14: | 東北新幹線新青森延伸開業(2010/12/04)、九州新幹線全通開業(2011/03/12)に伴う旅規改定を反映。新在別線の選択乗車により復乗(または環状線一周)となる例をパターン化し、その全区間を掲載。全体的に加筆し、脚注を挿入。条文引用のスタイルを変更 |
| 2015/03/19: | 2015/03/14の旅規改定の条文変更を反映。2014/04/01の旅規改定で第157条第1、2号が削除されたのに伴い「選択乗車による復乗」の「新在接続(通過・発着)型」に注記。またこれに伴い、表1、表2及び「新在別線の原則に」の「4.幹独立駅発着型選択乗車区間は、第157条の選択乗車区間として存続するが、復乗を排除する規定を付け加える。 」の号番号を訂正 |
| 2022/05/01: | 「旅客営業規則の条項」の整備新幹線の条文第16条の4を訂正(2016/03/26改定で北海道新幹線が追加されたが反映していなかった) |
| 2022/09/22: | 9月23日の西九州新幹線開業に伴う旅規改定を「旅客営業規則の条項」に反映。新在別線に基づく旅規の改定案(第69条の2)に第51号(諫早・長崎間)を追加 |
| 2022/12/10: | 3月16日の北陸新幹線敦賀延伸開業に伴う旅規改定を「旅客営業規則の条項」に反映(16条の4の「高崎・金沢間」を「高崎・敦賀間」に変更) |