| タイプA | タイプB | タイプC |
| A以遠(a方面)の各駅とB以遠(b方面)の各駅との相互間(x経由、y経由) | A以遠(a方面)の各駅とB1・B2間の各駅との相互間(x経由、y経由) | A以遠(a方面)の各駅とB'又はB以遠(b方面)の各駅との相互間(A・B間、A・B'間) |
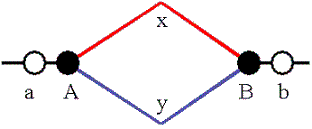 |
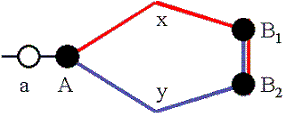 |
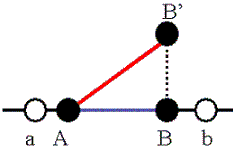 |
JRの旅客営業規則は、実際に乗車する経路による旅客運賃・料金の計算、乗車券類の券面表示事項にしたがった乗車、という原則を定めている。 ところが、さまざまな理由でこの原則に対する例外規定が存在する。 この点に着目して、JRの旅客制度の変遷をたどってみたい。目次
JR旅客制度の原則と例外 表1 運賃・料金計算及び乗車券類の効力の特例
表2 特例の4タイプ経路間ルート選択型 69条経路特定区間 157条選択乗車区間 列車特定区間 その他の他経路乗車 表3 経路特定区間の変遷
図1 選択乗車区間のタイプ
表4 選択乗車区間の変遷
表5 列車特定区間の変遷
表6 特定列車による短絡乗車制度の変遷エリア内ルート選択型 70条特定区間 大都市近郊区間 図2 70条特定区間の変遷
図3 大都市近郊区間の変遷エリア内中心駅運賃計算型 特定都区市内・山手線内発着 新大阪駅・大阪駅発着制度など 区間外乗車型 特定分岐区間 分岐駅通過列車 折返し列車 その他の区間外・折返し乗車制度 表7 特定分岐区間の変遷
表8 分岐駅通過列車の変遷
表9 折返し列車の変遷特例の改訂履歴 表10 特例の改訂履歴 参考文献 注 改訂履歴
JRの約款である「旅客営業規則」(以下、規則)は、運賃・料金の計算方法及び乗車券類の効力に関して、次のとおり原則を定めている。
すなわち、旅客運賃・料金は実際に乗車する経路の営業キロ(または擬制キロ)によって計算し、乗車券類はその券面に記載された経路及び区間について有効であるというのが、JRの旅客営業規則の大原則である。 この原則に対し、規則及びJRの内部規定である「旅客営業取扱基準規程」(以下、規程)には、表1のような例外規定(特例)が定められている。なお、2021年5月27日の旅規改定で、列車特定区間が規程110条から規則70条の2に移行し、2024年4月1日の改定で区間外乗車関連の規定が規則に移行した(下表で新旧条文を対比)。
| 項目 | 運賃・料金計算 | 乗車券類の効力 |
| 経路特定区間 | 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。(規則69条) | 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。(規則158条) |
| 大環状線 | 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。(規則70条) | 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。(規則159条)
第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。(規則160条) |
| 列車特定区間 | 次の各号に掲げる場合で、当該各号の末尾のかつこ内の上段の区間を乗車するときは、その区間内において途中下車しない限り、規則第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによつて旅客運賃、急行料金及び特別車両料金を計算する |
「規程第110条」の規定により発売した乗車券を所持する旅客に対しては、同条各号に掲げる急行列車に乗車する場合に限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該列車によるう回乗車の取扱いをすることができる。ただし、う回乗車区間内における途中下車の取扱いはしない。(規程154条?) |
| 特定都区市内・東京山手線内 | 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。(規則86条)
東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。 ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。(規則87条) |
特定都区市内 規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間(注:塚本−尼崎−加島間)の全部又は一部について、別に運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。 ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで太線区間の全部を乗車する場合に限る。(規程150条2項) 第86条の規定により発売した特定都区市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間のうち左方の駅以外の駅において 途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。 (1) 第86条第2号の規定により発売した横浜市内発又は着の普通乗車券 鶴見・武蔵小杉間 (2) 同条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券 塚本・尼崎間及び尼崎・加島間間 (3) 同条同号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券 加美・久宝寺間及び久宝寺・新加美間(規則160条の3、2項) |
| 新大阪駅・大阪駅発着 | 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。(規則88条) | |
| 北新地駅発着 | 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によって計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。(規則89条) | |
| 選択乗車区間 | 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。(規則157条) | |
| 大都市近郊区間 | 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。(規則157条2項) | |
| 特定分岐区間 | 次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。) の乗車券を所持する旅客 |
|
| 分岐駅通過列車 | 次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車 |
|
| 折返し列車 | 次に掲げる区間を折り返して直通運転する |
これらの特例は、表2の四つのタイプに分類できる。
| タイプ | 特例 | 該当条項 |
| 経路間ルート選択型 | 発着地点間の複数のルートのうち短いルートで運賃・料金を計算するか、短いルートを選択乗車できる(特定列車に限って認める場合もある) | 規則69条、157条1項、158条。規程110条、154条 |
| エリア内ルート選択型 | エリア内の複数のルートのうち短いルートで運賃・料金を計算するか、短いルートを選択乗車できる | 規則70条、157条2項、159条、160条 |
| エリア内中心駅運賃計算型 | エリア内の中心駅からのキロ程で運賃を計算する | 規則86条、87条、88条、89条。(規程150条) |
| 区間外乗車型 | 乗車券面に記載された以外の区間を乗車できる | 規程149条、150条、151条、152条 |
これらの特例は、国鉄・JRの発券事務の合理化と旅客の便宜をはかるという目的から制定されている。国鉄・JRの約款及び内部規定において、それがどのように変化してきたか、変遷をたどる。この間、約款の名称は、「旅客及び荷物運送規則(旅客編)」、「旅客及び荷物営業規則(旅客編)」、「旅客営業規則」と変化し、内規は、「旅客及び荷物運送取扱細則」、「旅客及び荷物営業細則」が「旅客営業取扱基準規程」と変わった[1]。なお、参考にした「旅客営業規則」等は、参考文献に記した。
経路特定制度は、1920(大正9)年、奥羽本線経由、常磐線経由でも東北本線経由で運賃を計算する制度の制定によりはじまったというのが定説になっている[2]。「日本国有鉄道百年史」(第8巻)によれば、1920(大正9)年10月それまでの単行規程を整理統合し制定され、1921(大正10)年1月11日施行された「国有鉄道旅客及び荷物運送規則」26条において、奥羽本線経由、常磐線経由の場合でも東北本線経由の営業マイルの旅客運賃で乗車券を発売し、旅客は任意の経路を乗車できることとした。
その後、1932年8月の改訂で次のとおり適用区間を拡大した。
その後の十数回の改訂を経て現在に至るが、1947年以降の経路特定区間の変遷を表3に示す。なお、現行の規則におけるフォーマットは「A以遠の各駅(a1又はa2方面)とB以遠の各駅(b方面)との相互間(x線、○y線)」であるが、これを表3では「A以遠(a1・a2方面)=B以遠(b方面)(x線、○y線)」と簡略している。
| 19/11改 | 04/03改 | 01/12改 | 94/03改 | 87/03改 | 83/07改 | 75/03改 | 73/09改 | 72/09改 | 66/03改 | 62/04改 | 58/10 現 |
57/01 現 |
53/03 現 |
50/05 現 |
47/08 現 |
|
| 長万部以遠(中ノ沢方面)=岩見沢以遠(峰延・萱野方面)(函館本線、○室蘭本線) | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ||||||||||||
| 長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂以遠(白石方面)(○函館本線、室蘭本線・千歳線) | ○1 | ○1 | ||||||||||||||
| 長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂、白石以遠(厚別方面)(○函館本線、室蘭本線・千歳線) | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ||||||||||||
| 福島以遠(金谷川方面)=青森・津軽線・北海道内 (奥羽本線、○東北本線) | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ||||||||||||
| 大沼以遠( |
○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○2 | ○2 | ○2 | ○7 | ○6 | ○6 | ○5 | ○5 | ○7 | ○7 | ○9 | ○* |
| 岩切以遠(東仙台方面)=品井沼以遠(鹿島台方面)(陸前山王駅経由東北本線、○利府駅経由東北本線) | ○6 | ○6 | ○8 | ○10 | ○* | |||||||||||
| 日暮里以遠(鶯谷・西日暮里・尾久方面)=岩沼以遠(亘理方面)(○東北本線、常磐線) | ○2 | ○3 | ○3 | ○3 | ○2 | ○2 | ○2 | ○1 | ○1 | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | |||
| 赤羽以遠(川口方面)=日暮里以遠(上野・北千住方面) (尾久経由東北本線、○王子経由東北本線) | ○7 | ○6 | ○7 | ○9 | ○9 | ○11 | ○* | |||||||||
| 日暮里以遠(鶯谷・三河島方面)=赤羽以遠(川口・北赤羽・十条方面)(尾久経由東北本線、○王子経由東北本線) | ○2 | ○2 | ||||||||||||||
| 赤羽以遠(尾久・東十条・十条方面)=大宮以遠(土呂・宮原・日進方面)(戸田公園・与野本町経由東北本線、○川口・浦和経由東北本線) | ○3 | ○3 | ||||||||||||||
| 品川以遠(田町・大崎方面)=鶴見以遠(新子安・国道方面)(西大井経由東海道本線、○大井町経由東海道本線) | ○4 | ○2 | ||||||||||||||
| 品川以遠( |
○4 | |||||||||||||||
| 東京以遠(有楽町・神田方面)=蘇我以遠(鎌取・浜野方面)(京葉線、○総武本線・外房線) | ○5 | ○5 | ||||||||||||||
| 岡谷以遠(下諏訪方面)=塩尻以遠(洗馬・広丘方面)(辰野経由、○みどり湖経由) | ○3 | ○4 | ○4 | |||||||||||||
| 河原田以遠(南四日市方面)=津以遠(阿漕以遠)(○伊勢線経由、関西本線・紀勢本線経由) | ○5 | ○4 | ○3 | |||||||||||||
| 山科以遠(京都方面)=近江塩津以遠(新疋田方面)(東海道本線・北陸本線、○湖西線) | ○6 | ○6 | ○2 | ○4 | ○5 | ○6 | ○5 | |||||||||
| 大阪以遠(塚本・新大阪方面)=天王寺以遠(東部市場前・美章園方面)(福島経由大阪環状線、○天満経由大阪環状線) | ○7 | ○7 | ||||||||||||||
| 三原以遠(糸崎方面)=海田市以遠(向洋方面)(呉線、○山陽本線) | ○8 | ○8 | ○3 | ○5 | ○6 | ○7 | ○6 | ○4 | ○3 | ○3 | ○2 | ○2 | ○4 | ○4 | ○4 | ○4 |
| 岩国以遠( |
○9 | ○9 | ○4 | ○6 | ○7 | ○8 | ○7 | ○5 | ○4 | ○4 | ○3 | ○3 | ○5 | ○5 | ○5 | ○5 |
| 肥前山口以遠(牛津方面)=諫早以遠(西諫早方面)(○長崎本線経由、佐世保線・大村線経由) | ○8 | ○9 | ○8 | ○6 | ○5 | ○5 | ○4 | ○4 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ||||
| 谷山以遠(五位野方面)=八代以遠(千丁方面)(鹿児島本線経由、○肥薩線・日豊本線・鹿児島本線経由) | ○7 | ○7 | ○7 | |||||||||||||
| 鹿児島、鹿児島古江間航路経由古江以遠(荒平方面)=八代以遠(千丁方面)(鹿児島本線経由、○肥薩線・日豊本線経由) | ○8 | ○8 |
経路特定区間の端緒になった、奥羽本線と東北本線は1958年に、常磐線と東北本線は2001年の改訂時に廃止された。2001年12月の改訂では特定区間は過去最低の4区間まで減少した。 2004年3月の改訂で、70条の特定区間の縮小・廃止に伴い、69条の経路特定区間に日暮里・赤羽間が復活、赤羽・大宮間、品川・鶴見間、東京・蘇我間、大阪・天王寺間が新たに指定され、9区間に拡大した。
この制度はあまり知られていない。 同条の第2項で同じ選択乗車として扱われている大都市近郊区間に比べて影が薄い。時刻表のピンクのページに記載されていないからだろう。 後述する列車特定制度や区間外乗車制度は、営業規則の本文ではなく、JRの内規である基準規程に規定されているだけなのに、ピンクのページに記載されているのとくらべて、不当に扱われている。したがってこの変遷を知るためには、古い営業規則にあたらねばならない。
選択乗車区間は、図1に示す三つのタイプに分類できる。
| タイプA | タイプB | タイプC |
| A以遠(a方面)の各駅とB以遠(b方面)の各駅との相互間(x経由、y経由) | A以遠(a方面)の各駅とB1・B2間の各駅との相互間(x経由、y経由) | A以遠(a方面)の各駅とB'又はB以遠(b方面)の各駅との相互間(A・B間、A・B'間) |
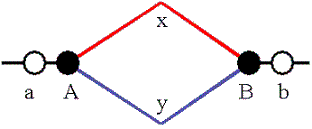 |
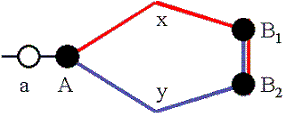 |
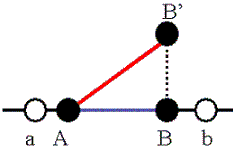 |
選択乗車区間のフォーマットは、まず[・・駅と・・駅相互間]と適用区間を示し、かっこ内に選択経路を示す。タイプAは、適用区間がA駅以遠とB駅以遠の相互間、選択経路がx、yのいずれかとなる。派生形として、選択経路を区間分割して、(x1、y1)(x2、y2)とするタイプがある。タイプBは、適用区間が、A駅以遠とB1・B2駅間との相互間、選択経路はx、yのいずれか。なお、適用区間にB1、B2の以遠駅を含む派生形もある。 タイプCは、適用区間がA以遠とB以遠又はB'の相互間、選択経路がA・B駅間またはA・B'間となる。B以遠駅に乗り継ぐためのB'・B間の移動は、旅客が何らかの手段で行うことになる。かつては、適用区間にBの以遠駅を含まないタイプや、逆にB'の以遠駅を含むタイプもあった。一般に、適用区間は選択経路に外接しているが、適用区間が選択経路から離れているタイプもあった。
1947年以降の選択乗車区間の変遷は表4の通りである。 なお、各タイプに付したNは新幹線絡みの選択乗車区間であることを示す。
| 区間(現行または最終) | 14/04現 | 11/03現 | 06/01現 | 02/12現 | 97/06現 | 89/10現 | 87/04現 | 82/05現 | 74/10現 | 67/04現 | 62/10現 | 58/10現 | 57/01現 | 53/03現 | 50/05現 | 47/08現 | |
| B | 新旭川以遠(旭川方面)=紋別・渚滑間(名寄経由、遠軽経由) | ○1 | ○1 4a | ○1 4a | ○1 4a | ||||||||||||
| C | 小樽築港以遠(朝里方面)=小樽以遠(塩谷方面)、手宮=(南小樽・小樽間、南小樽・手宮間) | ○1 | |||||||||||||||
| C | 下北以遠(赤川方面)=大湊・田名部(下北・大湊間、下北・田名部間) | ○2 | ○2 | ○2 | |||||||||||||
| AN | あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田以遠(田尻・上涌谷方面)(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由) | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○2 | ○2-2 | |||||||||
| AN | 小牛田以遠(松山町・上涌谷方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由) | ○2 | ○2 | ○2 | ○1-2 | ○1-2 | ○2-2 | ○2-3 | |||||||||
| AN | あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間) | ○1 | ○3 | ○3 | ○3 | ○1-3 | ○1-3 | ○2-3 | ○2-4 | ||||||||
| BN | あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田・古川間(東北本線経由、新幹線経由) | ○4 4b | ○4 4b | ○4 4b | ○1-4 4b | ○1-4 4b | ○2-4 4b | ○2-5 4b | |||||||||
| AN | 新花巻以遠(小山田方面)=盛岡以遠(厨川・大釜・上盛岡方面)(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由) | ○1-5 | ○1-5 | ○2-5 | |||||||||||||
| AN | 北上以遠(六原・柳原方面)=新花巻以遠(小山田方面)(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由) | ○1-6 | ○1-6 | ○2-6 | |||||||||||||
| AN | 北上以遠(六原・柳原方面)=花巻以遠(花巻空港方面)(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由) | ○1-7 | ○1-7 | ○2-7 | |||||||||||||
| AN | 花巻以遠(村崎野方面)=盛岡以遠(厨川・大釜・上盛岡方面)(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由) | ○1-8 | ○1-8 | ○2-8 | |||||||||||||
| AN | 北上以遠(六原・柳原方面)=盛岡以遠(いわて沼宮内・ |
○2 | ○5 | ○5 | ○5 | ||||||||||||
| CN | 一ノ関以遠(有壁・真滝方面)=水沢江刺、水沢以遠(金ケ崎方面)(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間) | ○3 | ○6 | ○6 | ○6 | ○1-9 | ○1-9 | ○2-9 | |||||||||
| CN | 北上以遠(村崎野・柳原方面)=水沢江刺、水沢以遠(陸中折居方面)(北上・水沢間、北上・水沢江刺間) | ○4 | ○7 | ○7 | ○7 | ○1-10 | ○1-10 | ○2-10 | |||||||||
| BN | 一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)=小牛田・古川間(東北本線経由、新幹線経由) | ○8 4b | ○8 4b | ○8 4b | ○1-11 4b | ○1-11 4b | |||||||||||
| AN | あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間) | ○5 | ○9 | ○9 | ○9 | ○1-12 | ○1-12 | ||||||||||
| 14/04 | 11/03 | 06/01 | 02/12 | 97/06 | 89/10 | 87/04 | 82/05 | 74/10 | 67/04 | 62/10 | 58/10 | 57/01 | 53/03 | 50/05 | 47/08 | ||
| CN | あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=くりこま高原、新田以遠(石越方面)(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間) | ○6 | ○10 | ○10 | ○10 | ○1-13 | ○1-13 | ||||||||||
| CN | 一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)=くりこま高原、新田以遠(梅ケ沢方面)(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間) | ○7 | ○11 | ○11 | ○11 | ○1-14 | ○1-14 | ||||||||||
| CN | 小牛田以遠(松山町・上涌谷方面)=くりこま高原、新田以遠(石越方面)(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間) | ○8 | ○12 | ○12 | ○12 | ○1-15 | ○1-15 | ||||||||||
| C | 仙台以遠(北仙台・長町方面)=西塩釜・本塩釜・東塩釜・塩釜駅との相互間(岩切経由、仙石線経由) | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ||||||||||||
| C | 岩沼以遠(槻木・亘理方面)・羽前千歳以遠(北山形・南出羽方面)=塩釜・本塩釜(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間) | ○2 | ○2 | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | ○1 | ○2 | ||||||||
| C | 仙台以遠(北仙台・長町方面)=松島・新松島・松島海岸(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間) | ○3 4c | |||||||||||||||
| C | 仙台以遠(東照宮・長町方面)=松島・松島海岸(仙台・松島間、仙台・松島海岸間) | ○3 | ○3 | ○4 | ○4 | ○4 | ○4 | ○2 | |||||||||
| C2 | 仙台以遠(長町・北仙台方面)=品井沼以遠(鹿島台方面)(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)(松島・品井沼間、新松島・品井沼間) | ○4 4c | |||||||||||||||
| C2 | 仙台以遠(東照宮・長町方面)=品井沼以遠(鹿島台方面)・高城町以遠(手樽方面)(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間) | ○4 | ○4 | ○5 | ○5 | ○5 | ○5 | ○3 | |||||||||
| C | 品井沼以遠(鹿島台方面)=松島・新松島(品井沼・松島間、品井沼・新松島間) | ○5 | |||||||||||||||
| AN | 福島以遠(南福島・笹木野方面)=あおば通、仙台以遠(東照宮・東仙台・榴ケ岡方面)(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間) | ○9 | ○13 | ○13 | ○13 | ○4-2 | ○4-2 | ○5-2 | ○5-2 | ||||||||
| CN | 福島以遠(南福島・笹木野方面)=白石蔵王、白石以遠(東白石方面)(福島・白石間、福島・白石蔵王間) | ○10 | ○14 | ○14 | ○14 | ○4-3 | ○4-3 | ○5-3 | ○5-3 | ||||||||
| CN | あおば通、仙台以遠(東照宮、東仙台・榴ケ岡方面)=白石蔵王、白石以遠(越河方面)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間) | ○11 | ○15 | ○15 | ○15 | ○4-4 | ○4-4 | ○5-4 | ○5-4 | ||||||||
| C | 亀田以遠(萩川方面)=新潟・新潟港(垂足新潟間、垂足新潟港間) | ○2 | |||||||||||||||
| A | 柏崎以遠(鯨波方面)=新発田以遠(加治・五十公野方面)(信越本線・羽越本線経由、越後線・白新線経由) | ○6 | ○4 | ○6 | ○2 | ||||||||||||
| A | 新津以遠(古津・東新津方面)=新発田以遠(加治方面)(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由) | ○16 | ○5 | ○5 | ○6 | ○6 | ○6 | ||||||||||
| 14/04 | 11/03 | 06/01 | 02/12 | 97/06 | 89/10 | 87/04 | 82/05 | 74/10 | 67/04 | 62/10 | 58/10 | 57/01 | 53/03 | 50/05 | 47/08 | ||
| AN | 長岡以遠(宮内方面)=新発田以遠(加治方面)(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由) | ○17 | ○5-2 | ○5-2 | ○6-2 | ||||||||||||
| AN | 長岡以遠(宮内方面)=東三条以遠(保内方面)(信越本線経由、新幹線経由) | ○5-3 | ○5-3 | ○6-3 | |||||||||||||
| AN | 長岡以遠(宮内方面)=新潟以遠( |
○12 | ○16 | ○16 | ○18 | ○5-4 | ○5-4 | ○6-4 | |||||||||
| BN | 長岡以遠(宮内方面)=東三条・燕三条間(信越本線経由、新幹線経由) | ○19 4b | ○5-5 4b | ○5-5 4b | ○6-5 4b | ||||||||||||
| AN | 高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=越後湯沢以遠(石打・ガーラ湯沢方面)(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間) | ○13 | ○17 | ○17 | ○20 | ○5-6 | ○5-6 | ○6-6 | |||||||||
| CN | 越後湯沢以遠(石打・ガーラ湯沢方面)=上毛高原、後閑以遠(沼田方面)(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間) | ○14 | ○18 | ○18 | ○21 | ○5-7 | ○5-7 | ○6-7 | |||||||||
| CN | 高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=上毛高原、後閑以遠(上牧方面)(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間) | ○15 | ○19 | ○19 | ○22 | ○5-8 | ○5-8 | ○6-8 | |||||||||
| AN | 熊谷以遠(行田方面)=高崎以遠(高崎問屋町・北高崎・安中榛名方面)(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間) | ○16 | ○20 | ○20 | |||||||||||||
| CN | 熊谷以遠(行田方面)=本庄早稲田、本庄以遠(神保原方面)(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間) | ○17 | ○21 | ○21 | |||||||||||||
| CN | 高崎以遠(高崎問屋町・北高崎・安中榛名方面)=本庄早稲田、本庄以遠(岡部方面)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間) | ○18 | ○22 | ○22 | |||||||||||||
| A | 大宮以遠(日進・北与野・与野方面)=桐生(井野及び前橋経由、小山経由) | ○6 | ○6 | ○7 | ○7 4d | ○7 4d | ○7 4d 4e | ○5 4d 4e | ○7 4d 4e | ||||||||
| B | 日暮里以遠(鶯谷・西日暮里・尾久方面)・両国以遠(浅草橋方面)=成田以遠(久住・空港第2ビル方面)(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由) | ○23 | ○23 | ○7 | ○7 | ○8 | ○8 | ○8 | ○8 | ○6 | ○8 | ○3 4f | ○2 | ○2 | ○* | ||
| A | 佐倉以遠(物井方面)=松岸・銚子(総武本線経由、成田線経由) | ○24 | ○24 | ○8 | ○8 | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 4e | ○7 4e | ○9 4e | ||||||
| A | 千葉以遠(西千葉方面)=成東以遠(松尾方面)(四街道経由、誉田経由) | ○8 | ○10 | ○4 | ○3 | ○3 | ○3 | ||||||||||
| B | 蘇我以遠(本千葉方面・千葉みなと方面)=館山・安房鴨川間(外房線経由、内房線経由) | ○25 4b | ○25 4b | ○8-2 4b | ○8-2 4b | ○9-2 4b | ○9-2 4b | ○9-2 4b | |||||||||
| A | 西船橋以遠(下総中山方面・船橋法典方面)=蘇我以遠(鎌取方面・浜野方面)(総武本線・外房線経由、京葉線経由) | ○8-3 | |||||||||||||||
| 14/04 | 11/03 | 06/01 | 02/12 | 97/06 | 89/10 | 87/04 | 82/05 | 74/10 | 67/04 | 62/10 | 58/10 | 57/01 | 53/03 | 50/05 | 47/08 | ||
| B | 西船橋以遠(下総中山方面・船橋法典方面)=二俣新町(市川塩浜経由、南船橋経由) | ○8-4 | |||||||||||||||
| CN | 小田原以遠(早川方面)=横浜・新横浜(小田原・横浜間、小田原・新横浜間) | ○10 | |||||||||||||||
| BN | 小田原以遠(早川方面)=横浜・新横浜間(東海道本線経由、新幹線経由) | ○19 | ○23 4b | ○26 4b | ○26 4b | ○9 4b | ○9 4b | ○10 4b | ○10 4b | ○10 4b | |||||||
| AN | 東京以遠(神田・新日本橋・八丁堀方面)=小田原以遠(早川方面)(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間) | ○27 | ○10 | ○10 | ○11 | ○11 | ○11 | ○11 | |||||||||
| AN | 品川以遠( |
○20 | ○24 | ○27 | |||||||||||||
| AN | 小田原以遠(早川方面)=東神奈川以遠(新子安方面)(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由) | ○21 | ○25 | ○28 | ○28 | ○11 | ○11 | ○12 | ○12 | ○12 | |||||||
| C | 戸塚以遠(保土ヶ谷方面)=藤沢以遠(辻堂方面)・鎌倉以遠(逗子方面)(大船・藤沢間、大船・鎌倉間) | ○12 | ○9 | ○11 | |||||||||||||
| B | 大船以遠(藤沢・北鎌倉方面)=桜木町・磯子間 (戸塚経由、本郷台経由) | ○12 4e | ○12 4e | ○13 4e | ○13 4e | ○13 4e | |||||||||||
| B | 横浜以遠(東神奈川方面)=磯子・本郷台間 (桜木町経由、戸塚経由) | ○12-2 4e | ○12-2 4e | ○13-2 4e | ○13-2 4e | ○13-2 4e | |||||||||||
| A | 小野、辰野以遠(宮木方面)=岡谷以遠(下諏訪方面)(川岸経由、塩尻経由) | ○29 4e | ○13 4e | ○13 4e | ○14 4e | ||||||||||||
| A | 辰野以遠(宮木方面)=塩尻以遠(洗馬・広丘方面)(小野経由、岡谷経由) | ○22 | ○26 4e | ○30 4e | ○30 4e | ○13-2 4e | ○13-2 4e | ○14-2 4e | |||||||||
| CN | 三島以遠(函南方面)=新富士、富士以遠(富士川・柚木方面)(三島・富士間、三島・新富士間) | ○23 | ○27 | ○31 | ○31 | ○13-3 | ○13-3 | ||||||||||
| CN | 静岡以遠(安倍川方面)=新富士、富士以遠(吉原・柚木方面)(静岡・富士間、静岡・新富士間) | ○24 | ○28 | ○32 | ○32 | ○13-4 | ○13-4 | ||||||||||
| AN | 三島以遠(函南方面)=静岡以遠(安倍川方面)(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間) | ○25 | ○29 | ○33 | ○33 | ○13-5 | ○13-5 | ||||||||||
| C | 大府以遠(共和方面)=刈谷・緒川 (大府・刈谷間、大府・緒川間) | ○15 | ○14 | ○14 | ○13 | ○10 | ○12 | ||||||||||
| CN | 名古屋以遠(尾頭橋・八田方面)=岐阜羽島、岐阜以遠(西岐阜・長森方面)(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。 | ○26 | ○30 | ○34 | ○34 | ○14 | ○14 | ○16 4g | ○15 4g | ○15 4h | ○14 4h | ||||||
| 14/04 | 11/03 | 06/01 | 02/12 | 97/06 | 89/10 | 87/04 | 82/05 | 74/10 | 67/04 | 62/10 | 58/10 | 57/01 | 53/03 | 50/05 | 47/08 | ||
| CN | 米原以遠(彦根・坂田方面)=岐阜羽島、岐阜以遠(木曽川・長森方面)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間) | ○27 | ○31 | ○35 | ○35 | ○15 | ○15 | ○17 | ○16 | ○16 | ○15 | ||||||
| AN | 名古屋以遠(尾頭橋・八田方面)=米原以遠(彦根・坂田方面)(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間) | ○28 | ○32 | ○36 | ○36 | ○16 | ○16 | ○18 | ○17 | ○17 | ○16 | ||||||
| C | 越中中川以遠(高岡方面)=伏木・新湊(能町伏木間、能町新湊間) | ○4 | ○4 | ||||||||||||||
| A | 木ノ本以遠(高月方面)=敦賀以遠(南今庄・西敦賀方面)(北陸本線経由、柳ヶ瀬線経由) | ○11 | ○13 | ||||||||||||||
| B | 亀山以遠(関方面)=鈴鹿・東一新田間 (河原田経由、津経由) | ○17-2 | ○17-2 | ||||||||||||||
| A | 柘植以遠(加太方面)=大阪以遠(塚本方面)、安治川口・桜島間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由) | ○17 | ○17 | ○19 | ○18 | ○18 | ○17 | ○12 | ○14 4i | ○5 4i | ○4 4i | ○5 4i | ○5 4i | ||||
| A | 奈良以遠(木津方面)=高田以遠(大和新庄方面)(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由) | ○6 | ○5 | ○6 | ○6 | ||||||||||||
| A | 奈良以遠(木津方面)=大和新庄以遠(御所方面)(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由) | ○18 | ○18 | ○20 | ○19 | ○19 | ○18 | ○13 | ○15 | ||||||||
| C | 平野以遠(加美方面)=大阪以遠(塚本・新大阪方面)(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間) | ○20 | ○21 | ○20 | ○20 | ○19 | ○14 | ○16 | ○7 | ○6 | ○7 | ○7 | |||||
| C | 東部市場以遠(平野方面)=大阪以遠(塚本・新大阪方面)(天王寺・大阪間、天王寺・JR難波間) | ○19 | |||||||||||||||
| A | 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)=和歌山市、和歌山、東和歌山以遠(紀三井寺方面)(紀伊中ノ島・和歌山市間、紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、紀伊中ノ島・東和歌山間) | ○8 | ○7 | ○8 | ○8 | ||||||||||||
| A | 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)=和歌山以遠(紀三井寺方面)(紀伊中ノ島・紀和・和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・和歌山間) | ○20 | ○15 | ○17 | |||||||||||||
| AN | 大阪以遠(天満・福島方面)=西明石以遠(大久保方面)(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由) | ○29 | ○33 4e | ○37 4e | ○37 4e | ○20 4e | ○21 4e | ○22 4e | ○21 4e | ○21 4e | |||||||
| AN | 新大阪以遠(東淀川・南吹田方面)=西明石以遠(大久保方面)(新大阪・三ノ宮・神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸・三ノ宮間、西明石・新神戸間) | ○30 | ○34 | ○38 | ○38 | ○21 | ○22 | ○23 | ○22 | ○21-2 | |||||||
| 14/04 | 11/03 | 06/01 | 02/12 | 97/06 | 89/10 | 87/04 | 82/05 | 74/10 | 67/04 | 62/10 | 58/10 | 57/01 | 53/03 | 50/05 | 47/08 | ||
| CN | 新大阪以遠(東淀川・南吹田方面)=新神戸・神戸以遠(兵庫方面)(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間) | ○31 | ○35 | ○39 | ○39 | ○22 | ○23 | ○24 | ○23 | ||||||||
| CN | 西明石以遠(大久保方面)=新神戸・神戸以遠(元町方面)(西明石・神戸間、西明石・新神戸間) | ○32 | ○36 | ○40 | ○40 | ○23 | ○24 | ○25 | ○24 | ||||||||
| A | 相生以遠(竜野方面)=東岡山以遠(高島方面)(山陽本線経由、赤穂線経由) | ○33 | ○37 | ○41 | ○41 | ○23-2 | ○24-2 | ○25-2 | |||||||||
| A | 向井原以遠(伊予市方面)=伊予大洲以遠(西大洲方面)(伊予長浜経由、内子経由) | ○34 | ○38 | ○42 | ○42 | ○23-3 | ○24-3 | ○25-3 | |||||||||
| CN | 福山以遠(東福山・備後本庄方面)=新尾道、尾道以遠(糸崎方面)(福山・尾道間、福山・新尾道間) | ○35 | ○39 | ○43 | ○43 | ○23-4 | ○24-4 | ||||||||||
| CN | 三原以遠(本郷・須波方面)=新尾道、尾道以遠(松永方面)(三原・尾道間、三原・新尾道間) | ○36 | ○40 | ○44 | ○44 | ○23-5 | ○24-5 | ||||||||||
| AN | 福山以遠(東福山・備後本庄方面)=三原以遠(本郷・須波方面)(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間) | ○37 | ○41 | ○45 | ○45 | ○23-6 | ○24-6 | ||||||||||
| CN | 三原以遠(糸崎・須波方面)=東広島、西条以遠(寺家方面)(三原・西条間、三原・東広島間) | ○38 | ○42 | ○46 | ○46 | ○23-7 | ○24-7 | ||||||||||
| CN | 広島以遠(新白島・矢賀方面)=東広島、西条以遠(西高屋方面)(広島・西条間、広島・東広島間) | ○39 | ○43 | ○47 | ○47 | ○23-8 | ○24-8 | ||||||||||
| AN | 三原以遠(糸崎・須波方面)=広島以遠(新白島・矢賀方面)(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間) | ○40 | ○44 | ○48 | ○48 | ○23-9 | ○24-9 | ||||||||||
| CN | 広島以遠(天神川・矢賀方面)=新岩国、岩国以遠(南岩国・西岩国方面)(広島・岩国間、広島・新岩国間) | ○41 | ○45 | ○49 | ○49 | ○24 | ○25 | ○26 | ○25 | ||||||||
| CN | 徳山以遠(新南陽方面)=新岩国、岩国以遠( |
○42 | ○46 | ○50 | ○50 | ○25 | ○26 | ○27 | ○26 | ||||||||
| AN | 広島以遠(天神川・矢賀方面)=徳山以遠(新南陽方面)(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間) | ○43 | ○47 | ○51 | ○51 | ○26 | ○27 | ○28 | ○27 | ||||||||
| A | 大阪以遠(天満・福島方面)・尼崎以遠(立花方面)=綾部以遠(梅迫方面)(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由) | ○27 | ○28 | ○29 | ○28 | ○22 | ○21 | ○16 | ○18 | ○9 4f | ○8 4f | ○9 4f | |||||
| A | 居能以遠(宇部新川方面)=小野田以遠(厚狭方面)(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由) | ○44 | ○48 | ○52 | ○52 | ○28 | ○29 | ○30 | ○29 | ○23 | ○22 | ○17 | ○19 | ○10 | ○9 | ||
| A | 新山口以遠(四辻・周防下郷方面)=宇部以遠(小野田方面)(山陽本線経由、宇部線経由) | ○45 | ○49 | ○53 | ○53 | ○29 | ○30 | ○31 | ○30 | ○24 | ○23 | ||||||
| 14/04 | 11/03 | 06/01 | 02/12 | 97/06 | 89/10 | 87/04 | 82/05 | 74/10 | 67/04 | 62/10 | 58/10 | 57/01 | 53/03 | 50/05 | 47/08 | ||
| A | 益田以遠(石見津田方面)=厚狭以遠(埴生方面)(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由) | ○30 | ○31 | ○32 | ○31 | ○25 | ○24 | ○11 | ○10 | ○10 | ○9 | ||||||
| A | 益田以遠(石見津田方面)=幡生以遠(下関方面)(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由) | ○31 | ○32 | ○33 | ○32 | ○26 | ○25 | ○18 | ○12 | ○11 | ○11 | ○10 | |||||
| A | 仙崎、長門市以遠(長門三隅方面)=幡生以遠(下関方面)(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由) | ○32 | ○33 | ○34 | ○33 | ○27 | ○26 | ○19 | ○13 | ○12 | ○12 | ○11 | |||||
| C | 中田以遠(地蔵橋方面)=小松島・南小松島 (中田・小松島間、中田・南小松島間) | ○34 | ○28 | ○27 | ○20 | ○20 | ○14 | ○13 | ○13 | ○12 | |||||||
| A | 下関以遠(幡生方面)=門司以遠(小倉方面)(ずい道線経由、下関・門司港間航路及び鹿児島本線経由)。ただし、下関・門司港間相互発着となるものを除く。 | ○15 | ○14 | ○14 | ○13 4j | ||||||||||||
| A | 下関以遠(幡生方面)=門司港(下関・門司港間航路、下関・門司間ずい道線及び門司・門司港間) | ○16 | ○15 | ○15 | ○14 4j | ||||||||||||
| A | 下関以遠(幡生方面)=門司以遠(小倉方面)(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間) | ○21 | ○21 | ||||||||||||||
| C | 門司以遠(小倉方面)=下関・門司港 (門司・下関間、門司・門司港間) | ○35 | ○35 | ||||||||||||||
| A | 小倉以遠(門司方面)=伊田以遠(後藤寺方面)(日豊本線及び田川線経由、鹿児島本線、筑豊本線及び伊田線経由) | ○17 | ○16 | ○16 | ○16 | ||||||||||||
| A | 香春以遠(採銅所方面)=添田以遠(豊前桝田方面)(日田彦山線経由、添田線経由) | ○36 | ○29 | ○28 | ○22 | ○22 | |||||||||||
| C | 遠賀川以遠(海老津・古月方面)・中間以遠(筑前垣生・新手方面)=若松・戸畑以遠(小倉方面)(折尾・若松間、折尾・戸畑間) | ○30 | ○29 | ○23 | ○23 | ○18 | ○17 | ○17 | ○17 | ||||||||
| C | 水巻以遠(遠賀川方面)・中間以遠(筑前垣生方面)=若松・戸畑以遠(小倉方面)(折尾・若松間、折尾・戸畑間) | ○35 | ○36 | ○37 | |||||||||||||
| A | 博多以遠(越前簑島方面)・吉塚以遠(原町・御手洗方面)=直方以遠(中泉方面)(折尾経由筑豊本線、原田経由筑豊本線) | ○38 | ○31 | ○30 | ○24 | ○24 | ○19 | ○18 | ○18 | ○18 | |||||||
| A | 金田以遠(赤池方面)=田川後藤寺以遠(池尻・船尾方面)(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由) | ○36 | ○37 | ○39 | ○32 | ○31 | ○25 | ○25 | |||||||||
| C | 山本以遠(相知・肥前久保・牟田部方面)=唐津、西唐津、東唐津以遠(虹ノ松原方面)(山本・唐津・西唐津間、山本・東唐津間) | ○40 | ○33 | ○32 | ○26 | ○26 | ○20 | ○19 | ○19 | ○19 | |||||||
| 14/04 | 11/03 | 06/01 | 02/12 | 97/06 | 89/10 | 87/04 | 82/05 | 74/10 | 67/04 | 62/10 | 58/10 | 57/01 | 53/03 | 50/05 | 47/08 | ||
| BN | 博多南・博多以遠(吉塚・小倉方面)=新鳥栖・鳥栖以遠(肥前旭方面)(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間) | ○46 | ○50 | ||||||||||||||
| BN | 久留米以遠(荒木・久留米高校前方面)=新鳥栖・鳥栖以遠(田代方面)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間) | ○47 | ○51 | ||||||||||||||
| AN | 博多南・博多以遠(吉塚・小倉方面)=久留米以遠(荒木・久留米高校前方面)(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間) | ○48 | ○52 | ||||||||||||||
| AN | 筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=熊本以遠( |
○49 | ○53 | ||||||||||||||
| BN | 筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=新大牟田・大牟田以遠(荒尾方面)(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間) | ○50 | ○54 | ||||||||||||||
| BN | 筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=新玉名・玉名以遠(肥後伊倉方面)(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間) | ○51 | ○55 | ||||||||||||||
| BN | 大牟田以遠(銀水方面)・新大牟田=玉名以遠(肥後伊倉方面)・新玉名(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間) | ○52 | ○56 | ||||||||||||||
| BN | 熊本以遠( |
○53 | ○57 | ||||||||||||||
| BN | 熊本以遠(熊本以遠( |
○54 | ○58 | ||||||||||||||
| A | 肥前山口以遠(牛津方面)=岩松・竹松間 (早岐経由、諫早経由) | ○33 | ○37 | ○38 | ○41 | ○34 | ○33 | ○27 | ○27 | ○21 | ○20 | ○20 | ○20 | ||||
| A | 喜々津以遠(西諫早方面)=浦上・長崎 (現川経由、本川内経由) | ○55 | ○59 | ○54 | ○54 | ○34 | ○38 | ○39 | ○42 | ○35 | |||||||
| B | 喜々津以遠(西諫早方面)=長与・西浦上間(現川経由、本川内経由) | ○56 | ○60 4b | ○55 4b | ○55 4b | ||||||||||||
| B | 東園・本川内間=浦上・長崎(長与経由、現川経由) | ○57 | ○61 | ○56 | ○56 | ||||||||||||
| C | 加治木以遠(帖佐方面)=霧島神宮以遠(北永野田方面)・霧島西口以遠(大隈横川方面)(隼人・霧島神宮間、隼人・霧島西口間) | ○39 | ○40 | ○43 | ○36 | ○34 | ○28 | ○28 | ○22 | ○21 | ○21 | ||||||
| A | 南宮崎以遠(宮崎方面)=志布志以遠(菱田方面)(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由) | ○44 | ○37 | ○35 | |||||||||||||
選択乗車制度の起源は「日本国有鉄道百年史」にも記載されておらず、定かでない。しかし、1919(大正8)年2月25日付の「中外商業新報」の記事「東京大阪市内経由旅客の取扱方改正」[3]によると、当時から選択乗車のルーツと思われる制度が存在していたことがわかる。双方向の選択乗車ではなく、経路が連続するA・B間の乗車券を所持する旅客がA・B間に代えてA・B'間またはA'・B間を選択できるという他経路乗車の規定である。1921(大正10)年1月11日施行の「国有鉄道旅客及荷物運送取扱細則」(大正11年3月21日改訂再販)の第49条から第57条及び第59条は他経路乗車の規定であり、1919年の区間が引き継がれている。当時の他経路乗車区間を表4のフォーマットで示すと次のとおり(カッコ内の○を付した左側の経路の乗車券で右側の経路の乗車が可)[4]。
上記の区間は、すべてタイプCである。このうち、岩切−松島・塩竃間や大船−藤沢・鎌倉間は、観光旅行客の便宜を図り、鉄道利用を促進しようとしたものである[5]。
選択乗車区間は、路線の新設・廃止や旅客の移動需要の変化によって、刻々変化してきた。東北新幹線八戸延伸時の2002年12月1日改定で在来線の選択乗車区間の多くが廃止され、タイプCは新幹線絡みのものしか残っていない。近年新設されたのは、ほとんどが新幹線の別線扱い区間にかかわるものである。新幹線の選択乗車区間の問題については、「新幹線と在来線−同一線扱いの虚構と矛盾」で考察した。
JR東日本は、IC乗車券Suicaの取扱範囲の拡大に伴い、大都市近郊区間を拡大し、関連する選択乗車区間を廃止している。2004年11月の新潟地区へのSuica導入時に新潟近郊区間が設定され、「新津以遠(古津・東新津方面)=新発田以遠(加治方面)(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)」など3区間が廃止された。また千葉県全体が東京近郊区間に指定された2009年3月14日改訂で、1949年の公社としての日本国有鉄道設立以前から継続して選択乗車区間に指定されていた「日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)」が廃止された。さらに、2014年4月、仙台近郊区間を設定、4選択乗車区間を廃止した。
列車特定制度が正式に「旅客運送取扱細則」に規定された1958年以降の変遷を表5に示す。現行の規則におけるフォーマットは「A以遠の各駅(a又1はa2方面)とB以遠の各駅(b方面)との相互間を、x線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき(x線、○y線)」であるが、これを表5では、「A以遠(a1・a2方面)=B以遠(b方面)(x線、○y線)」と表示する。なお、58年11月現行の細則第81条では、対象列車列車を明記していた。
| 区間 | 06/01現 | 02/04現 | 99/02現 | 97/06現 | 96/04現 | 93/02現 | 91/02現 | 87/04現 | 82/05現 | 74/10現 | 67/04現 | 62/10現 | 58/11 現 |
| 音威子府以遠(咲来方面)=南稚内・稚内(天北線、○宗谷本線) | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ||||||||
| 白石以遠(苗穂方面)=新得以遠(十勝清水方面) (函館本線及び根室本線、○千歳線及び石勝線) | ○2 | ○2 | |||||||||||
| 長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂以遠(白石方面)(室蘭本線静狩・沼ノ端間及び千歳線、○函館本線) | ○2 | ○2 | ○1:107/108 | ||||||||||
| 福島以遠(南福島方面)=青森以遠(油川・函館方面)(奥羽本線、○東北本線) | ○1 | ○3 | ○3 | ○2 | ○3 | ○3 | ○2:401/402 | ||||||
| 新津以遠(東新津・古津方面)=新発田以遠(加治方面) (白新線及び信越本線新潟・新津間、○羽越本線) | ○1 5a | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○2 | ○4 | ○4 | ○3 | ○4 | ○4 | ||
| 高崎以遠(倉賀野方面)・新前橋以遠(前橋方面)・井野駅=直江津以遠(谷浜方面)(上越線群馬総社・宮内間及び信越本線長岡・黒井間、○信越本線) | ○2 | ○2 | ○2 | ○3 | ○5 | ○5 | ○4 | ○5 | ○5 | ○3:601/602 | |||
| 大宮以遠(与野、与野本町・日進方面)=秋田以遠(土崎方面)(高崎線、上越線、信越本線(白新線を含む)及び羽越本線、○東北本線及び奥羽本線) | ○3 | ○3 | ○4 | ○6 | ○6 | ○5 | ○6 | ○6 | ○4:801/802 | ||||
| 大宮以遠(与野・与野本町・日進方面)=青森以遠(油川方面)(高崎線、上越線、信越本線(白新線を含む)、羽越本線及び奥羽本線、○東北本線) | ○2 | ○2 | ○3 | ○4 | ○4 | ||||||||
| 福島以遠(南福島方面)=山形・北山形以遠(東金井方面)・羽前千歳以遠(南出羽方面)(東北本線、仙山線及び奥羽本線、○奥羽本線) | ○5 | ○5 | |||||||||||
| 福島以遠(南福島方面)=新庄以遠(泉田方面) (東北本線、陸羽東線及び奥羽本線、○奥羽本線) | ○6 | ○6 | |||||||||||
| 福島以遠(南福島方面)=横手以遠(後三年方面) (東北本線、北上線及び奥羽本線、○奥羽本線) | ○7 | ○7 | |||||||||||
| 福島以遠(南福島方面)=青森以遠(油川方面) (東北本線、仙山線及び奥羽本線、○東北本線) | ○8 | ○8 | |||||||||||
| 福島以遠(南福島方面)=青森以遠(油川方面) (東北本線、陸羽東線及び奥羽本線、○東北本線) | ○9 | ○9 | |||||||||||
| 福島以遠(南福島方面)=横手以遠(後三年方面) (東北本線、北上線及び奥羽本線、○奥羽本線) | ○10 | ○10 | |||||||||||
| 赤羽以遠(川口方面)=池袋以遠(目白方面)(東北本線及び山手線、○赤羽線) | ○1 5b | ○3 | ○3 | ○4 | ○11 | ○11 | |||||||
| 代々木以遠(新宿方面)=錦糸町以遠(亀戸方面)(山手線、東海道本線品川・東京間及び総武本線東京・錦糸町間、○中央本線及び総武本線御茶ノ水・錦糸町間) | ○2 | ○4 | ○4 | ○5 | ○12 | ○12 | ○5 | ||||||
| 品川以遠(田町・大崎方面)=鶴見以遠(新子安方面)(東海道本線(新川崎経由)、○東海道本線(川崎経由)) | ○5 | ○5 | ○6 | ○13 | |||||||||
| 岡谷以遠(下諏訪方面)=塩尻(洗馬・広丘方面)(辰野経由、○みどり湖経由) | ○3 5c | ○6 | |||||||||||
| 尼崎以遠(塚本方面)=和田山以遠(養父方面)(山陽本線、播但線及び山陰本線)、○東海道本線、福知山線及び山陰本線) | ○4 | ○7 | ○6 | ○7 | ○14 | ○13 | ○6 | ○7 | ○7 | ○6 | ○7 | ||
| 多度津以遠(海岸寺方面)=佐古以遠(徳島方面)(予讃本線、土讃本線及び徳島本線、○予讃本線、及び高徳本線) | ○8 | ||||||||||||
| 小倉以遠(門司方面)=鹿児島・西鹿児島以遠(南鹿児島方面)(日豊本線、○鹿児島本線) | ○ 5d | ○ 5d | ○ 5d | ○ 5d | ○ 5d | ○9 5e |
一方、長い経路の乗車券で、短絡経路を運転する列車の乗車を認める、規程155条(67年以前は細則122条)も国鉄時代に存在した。
該当区間及び列車は表6のとおりである。 なお、58年11月現行の細則では、列車名を明記していた。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:数字は、規程155条(細則122条)の「号」を示す。 |
2009年4月1日現行の規程第155条に、06年1月版になかった併用乗車券による他経路乗車の規定を発見した。2011年現行版には2010年3月の東海道本線(品鶴線)武蔵小杉駅開業にともなう追加区間が記載されている。またデスクトップ鉄の雑記帳の記事のコメントで、仙石東北ライン開業時に第1号と第2号が追加されたことが判明した。
| (1) | 仙台市内着の乗車券 | 中野栄発で高城町以遠(手樽方面)の各駅着の乗車券 | |
| 岩切・高城町間 | |||
| (2) | 仙台市内発の乗車券 | 高城町以遠(手樽方面)の各駅発で中野栄駅着の乗車券 | |
| 高城町・岩切間 | |||
| (3) | 東京都区内着の乗車券 | 小岩駅発で南船橋以遠(新習志野方面)の各駅又は西船橋以遠(船橋法典方面)の各駅着の乗車券 | |
| 葛西臨海公園・南船橋間又は葛西臨海公園・西船橋間 | |||
| (4) | 南船橋以遠(新習志野方面)の各駅又は西船橋以遠(船橋法典方面)の各駅発で小岩駅着の乗車券 | 東京都区内発の乗車券 | |
| 南船橋・葛西臨海公園間又は西船橋・葛西臨海公園間 | |||
| (5) | 東京都区内着の乗車券 | 西大井駅発で武蔵小杉以遠(武蔵中原方面)の各駅着の乗車券 | |
| 蒲田・武蔵小杉間 | |||
| (6) | 武蔵小杉以遠(武蔵中原方面)の各駅発で西大井駅着の乗車券 | 東京都区内発の乗車券 | |
| 武蔵小杉・蒲田間 | |||
| (7) | 横浜市内着の乗車券 | 本郷台駅発で大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅着の乗車券 | |
| 戸塚・大船間 | |||
| (8) | 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅発で本郷台駅着の乗車券 | 横浜市内発の乗車券 | |
| 大船・戸塚間 | |||
| (9) | 横浜市内着の乗車券 | 矢向駅発で武蔵小杉以遠(武蔵中原方面)の各駅着の乗車券 | |
| 鶴見・武蔵小杉間 | |||
| (10) | 武蔵小杉以遠(武蔵中原方面)の各駅発で矢向駅着の乗車券 | 横浜市内発の乗車券 | |
| 武蔵小杉・鶴見間 | |||
| (11) | 大阪市内着の乗車券 | 加島駅発で尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅着の乗車券 | |
| 塚本・尼崎間 | |||
| (12) | 尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅発で加島駅着の乗車券 | 大阪市内発の乗車券 | |
| 尼崎・塚本間 |
特定都区市内発着の乗車券は、都区市内の境界駅から(まで)乗車可能なので、これと境界駅まで(から)の乗車券とを併用して(着の場合は区間変更によることも可)運賃を節約することが広く行われている。新設された条項は、実際の乗車経路の運賃よりも安い乗車券を併用して他経路の乗車を認めるもので、JRとしてはきわめて寛容な取扱いである(例えば、小岩・市川大野間13.7キロ220円の併用乗車券で東京駅から京葉線経由で西船橋で乗り換えずに乗車できる。この条項がなければ、葛西臨海公園・市川大野間19.4キロ310円の乗車券が必要)。しかし、内部規定でウェブや時刻表のピンクのページに掲載されておらず、どこまで周知されているか疑問である。
なお、10号、11号は、後述する規程155条2項の区間外乗車区間にあわせて設定されている。2019年3月16日のおおさか東線の開業に伴い新加美・久宝寺・加美間の区間外乗車が設定されたので、次の他経路乗車が13号、14号として追加された可能性がある。
| (13) | 大阪市内着の乗車券 | 新加美駅発で久宝寺以遠(八尾方面)の各駅着の乗車券 |
| 加美・久宝寺間 | ||
| (14) | 久宝寺以遠(八尾方面)の各駅発で加島駅着の乗車券 | 大阪市内発の乗車券 |
| 久宝寺・加美間 | ||
規則70条には標題がない。その対象範囲は、一般には、「70条太線区間」や「大環状線」と呼ばれている。1958年10月の規則改正で、東京大環状線区間が制定された。それ以前の営業規則にも「図の太線区間」は規定されていたが、最短経路による運賃計算の制度ではなく、現在の規則159条、160条に相当する、太線区間通過・発着の場合の迂回乗車の制度だけであった。一方大阪地区にも1961年4月の大阪環状線の開業によって、大阪環状線が70条太線区間に指定された。区間の変遷を下図に示す。
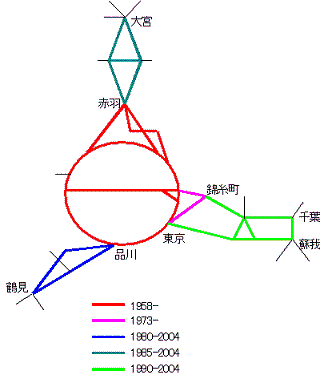 |
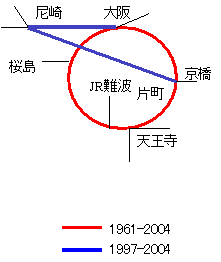 |
東京大環状線は、1972年7月の総武快速線開業、1980年10月の東海道貨物線(品鶴線)の旅客線化、1985年の東北本線支線(埼京線)の開業によって、順次拡大していった。しかし、1990年3月京葉線の東京駅延伸時に蘇我まで同区間を拡大したのは、JRとって大きなミスであった。これによって、たとえば、木更津から銚子(浜野・東千葉・松尾経由。蘇我・千葉間は経路指定なし)という乗車券(116.4キロ、1,890円)で、京葉線・品川・山手・赤羽・東北・総武という経路(232.3キロ、3,890円)を迂回し、その経路上で途中下車することが可能だったのである。鶴見や大宮までの拡大は、それぞれ、品川と赤羽でループが閉じていたので、このような事態は発生しなかった。
一般旅客の便宜を図るためには、東京・蘇我間(総武・外房経由、京葉経由)や西船橋・蘇我間(総武・外房経由、京葉経由)を69条の経路特定区間とするだけでよかったのである。JRは、2004年、この方向で制度を改訂した。東京大環状線は、2004年3月13日の規則改訂で、69条の特定区間に
が追加されたのと引き換えに、1980年以前の区間まで大幅に縮小された。ただし、70条2項として次の条項が規定され、70条特定区間から外れた駅と蘇我以遠の各駅との間で、最短距離による運賃・料金計算が継承された[8]。
一方大阪環状線区間は、1997年3月のJR東西線の開業により尼崎まで拡大したが、2004年の改訂で、69条の経路特定区間に
が指定され、廃止された。
なお、69条、70条の特定区間の特例には、例外の例外が規程109条(細則時代には83条)として存在する。
1973年4月の規則改訂で、東京近郊区間及び大阪近郊区間が設定された。大都市近郊区間に係わる規則の条項は、以下のとおりである。
上記3が「大都市近郊区間大回り乗車」の根拠規定である。 なお、大都市近郊区間の制定以前は「電車特定区間」が実質的に大都市近郊区間として機能していた。1969年5月の規則改訂で、157条2項に「東京附近の電車特定区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」と定められたが、それ以前にも、支社規程297条として同様の取扱がなされていた。なお、大都市近郊区間によって規則から姿を消した電車特定区間は、1987年4月に復活した。1984年4月の規則改訂で、低廉な賃率で運賃が計算される区間として定められた国電区間が分割民営化により電車特定区間に改称されたためである。
その後1974年4月に福岡近郊区間、2004年11月に新潟近郊区間、2014年4月に仙台近郊区間が設定された。福岡近郊区間は、路線の廃止や転換によって制定当初よりも縮小したが、東京・大阪・新潟近郊区間は、図3に示すように順次拡大していった。
| 東京近郊区間 | |
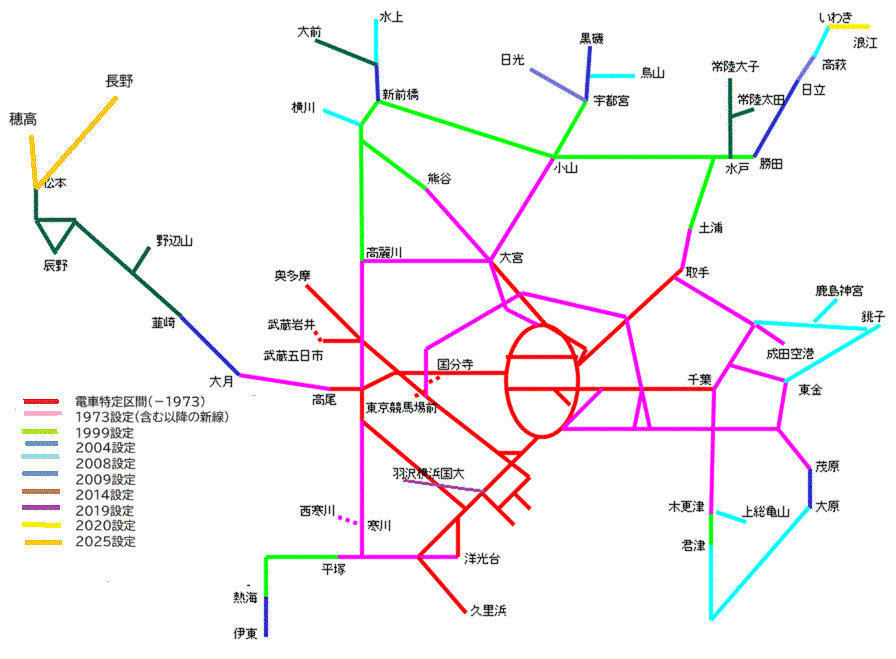 |
|
| 大阪近郊区間 | 福岡近郊区間 |
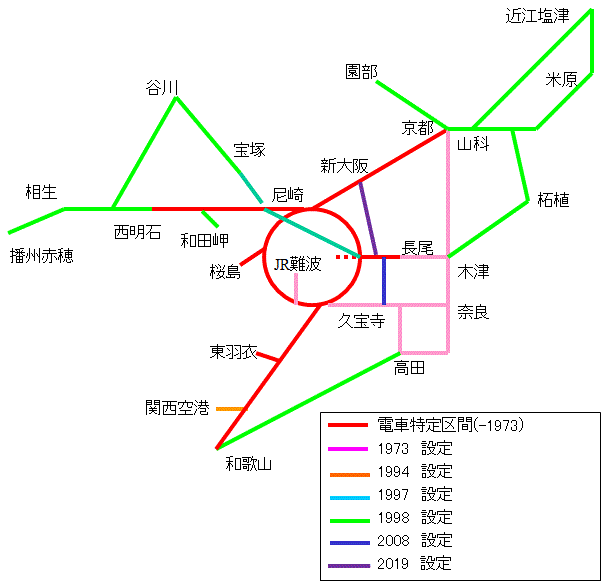 |
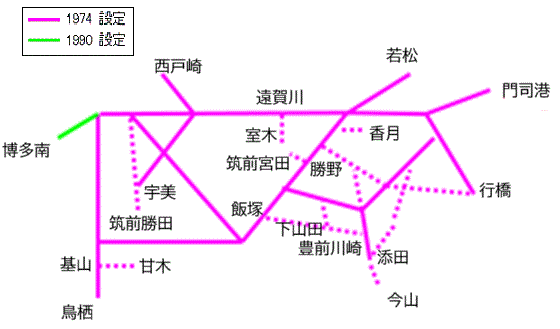 |
| 新潟近郊区間 | 仙台近郊区間 |
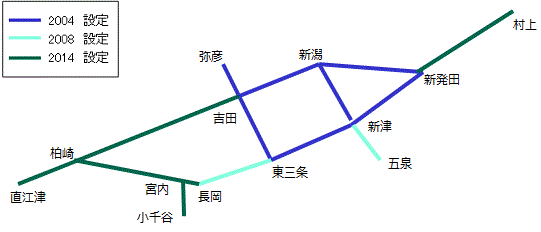 |
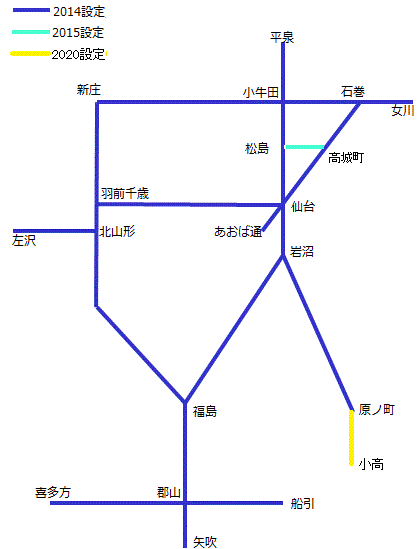 |
大都市近郊区間は、70条特定区間と異なって、選択乗車の制度であり、最短運賃計算キロで運賃を計算するものではない。したがって、乗車経路どおりの乗車券を購入することができるが、有効期間は1日で、途中下車ができないから、わざわざ高い運賃を支払う意味がない。制度自体も、ICカード乗車券の普及により実質的に最短経路による運賃計算の制度に変化している。自動改札機は、磁気式SFカードの時代から乗降駅間の最低運賃を引き落とすように設計されており、これがSuicaやICOCA等のICカード乗車券に引き継がれている。
近年東京・大阪近郊区間が拡大し、新潟近郊区間と仙台近郊区間が設定されたのも、自動改札機の設置及びICカード乗車券の取扱エリアの拡大によるものである。とくにJR東日本は、ICカード取扱区間と大都市近郊区間を一致させることにこだわり[9]、東京近郊区間は、2014年4月、400キロを超えるいわき・松本間にまで拡大し(10月吾妻線も)、さらに2025年3月には松本・長野間、松本・穂高間も含めた。
なお、規程に次の条項がある。 一読しただけでその意味をつかむことはきわめて難しいが、この制度によって短距離のほうが運賃が高くなる事態を是正する規定である。
また、特定都区市内を2度通過する場合に、特定都区市内制度を適用せず、個々の駅発着の運賃計算を行う、いわゆる「単駅指定」という例外の例外規定もある。従来、規程第115条に規定されていたが、2008年4月1日施行の旅規改訂で以下のただし書きが規則第86条及び第87条に挿入された。
2009年3月13日の制度改定で、規程115条に次の条項が規定された。
新大阪駅・大阪駅発着制度は、1972年3月の新幹線岡山延伸開業時に、北新地駅発着制度は、1997年3月のJR東西線開業時に制定された。なお、東海道新幹線開業時には、下記の横浜・新横浜駅発着制度ができたが、1969年に特定都区市内制度に横浜市内が指定されたのに伴い、廃止となった。
また、経路特定区間で条文を紹介したが、1932年8月当時、鹿児島・西鹿児島と八代間には、経路特定のほか、鹿児島駅発着のキロ程によって運賃計算を行う制度があった。
その変遷を表7に示す。フォーマットは、「A以遠(a1又はa2方面)の各駅とB以遠(b方面)の各駅との相互間(X・Y間)」であるが、これを「A以遠(a1・a2方面)=B以遠(b方面)(X・Y間)」と表す。
| 区間 | 24/04現 | 22/03現 | 19/11現 | 16/03現 | 06/01現 | 02/04現 | 99/02現 | 95/02現 | 93/02現 | 87/04現 | 82/05現 | 74/10現 | 67/04現 | 62/10現 | 58/11現 | 57/01現 | 53/03現 | 50/05現 | 47/08現 |
| 赤川以遠(金谷沢方面)=田名部以遠(樺山方面)(下北・大湊間) | ○1-1 | ○1-1 | ○1-1 | ○1-1 | ○1 | ||||||||||||||
| 松島・愛宕以遠(品井沼方面)=高城町以遠(松島海岸・手樽方面)(塩釜・松島間) | ○10 | ○1-1 7a | ○1-1 7a | ○1-1 7a | |||||||||||||||
| 大宮以遠(蓮田・宮原方面)=松戸以遠(藤代方面)(日暮里・上野間) | ○1 | ||||||||||||||||||
| 蓮田以遠(白岡方面)・宮原以遠(上尾方面)=三河島以遠(南千住方面)(日暮里・上野間) | ○1-2 | ○1-2 | ○2 | ||||||||||||||||
| 西日暮里以遠(田端方面)=三河島以遠(南千住方面)(日暮里・上野間) | ○1-1 | ○1-1 | ○1-1 | ○1-1 | ○1-2 | ○1-2 | |||||||||||||
| 西日暮里以遠(田端方面)=三河島以遠(南千住方面)(日暮里・東京間) | ○1 | ○1-2 | ○1-2 | ○1-2 | ○1-1 | ○1-1 | |||||||||||||
| 日暮里・鶯谷・田端以遠(駒込方面)・三河島以遠(南千住方面)=尾久(日暮里・上野、鶯谷・上野間) | ○2 | ○1-3 | ○1-3 | ○1-3 | ○1-2 | ○1-2 | ○1-2 | ○1-2 | ○1-2 | ○1-2 | ○1-3 | ○1-3 | ○1-3 | ○1-3 | ○3 | ||||
| 西大井以遠(武蔵小杉方面)=品川以遠( |
○3 | ○1-4 | ○1-4 | ○1-4 | ○1-3 | ||||||||||||||
| 横浜以遠(保土ケ谷・桜木町方面)=羽沢横浜国大(鶴見・武蔵小杉間) | ○4 | ○1-5 | ○1-5 | ||||||||||||||||
| 新川崎=羽沢横浜国大(新川崎・武蔵小杉間) | ○5 | ○1-6 | ○1-6 | ||||||||||||||||
| 鶴見・新子安・東神奈川・川崎以遠(蒲田・尻手方面)・国道以遠(鶴見小野方面)・大口以遠(菊名方面)=羽沢横浜国大(鶴見・横浜、新子安・横浜、東神奈川・横浜、鶴見・武蔵小杉間) | ○6 | ○1-7 | ○1-7 | ||||||||||||||||
| 鶴見・新子安・東神奈川・国道以遠(鶴見小野方面)・大口以遠(菊名方面)=新川崎(鶴見・横浜、新子安・横浜、東神奈川・横浜間) | ○1-3 | ||||||||||||||||||
| 鶴見・新子安・東神奈川・国道以遠(鶴見小野方面)・大口以遠(菊名方面)=新川崎・西大井(鶴見・横浜、新子安・横浜、東神奈川・横浜間) | ○1-3 | ||||||||||||||||||
| 鶴見・新子安・東神奈川・国道以遠(鶴見小野方面)・大口以遠(菊名方面)=新川崎以遠(西大井方面)(鶴見・横浜、新子安・横浜、東神奈川・横浜間) | ○1-3 | ○1-3 | ○1-3 | ||||||||||||||||
| 鶴見・新子安・東神奈川、川崎以遠(蒲田・尻手方面)・国道以遠(鶴見小野方面)・大口以遠(菊名方面)=新川崎以遠(西大井方面)(鶴見・横浜、新子安・横浜、東神奈川・横浜間) | ○1-4 | ○1-4 | ○1-3 | ||||||||||||||||
| 鶴見・新子安・東神奈川、川崎以遠(蒲田・尻手方面)・国道以遠(鶴見小野方面)・大口以遠(菊名方面)=新川崎・西大井・武蔵小杉以遠(武蔵中原・向河原方面)(鶴見・横浜、新子安・横浜、東神奈川・横浜間) | ○7 | ○1-8 | ○1-8 | ○1-5 | |||||||||||||||
| 武蔵白石・浜川崎以遠( |
○8 | ○1-9 | ○1-9 | ○1-6 | ○1-5 | ○1-4 | ○1-4 | ||||||||||||
| 今宮・芦原橋以遠(大正方面)=JR難波(新今宮・今宮間) | ○9 | ○1-10 | ○1-10 | ○1-7 | ○1-6 | ○1-5 | |||||||||||||
| 塚口以遠(伊丹方面)=神戸以遠(兵庫方面)(神崎・大阪間) | ○2 | ||||||||||||||||||
| 塚口以遠(伊丹方面)=立花以遠(甲子園口方面)(尼崎・大阪間) | ○2 | ○2 | ○2 | ||||||||||||||||
| 柱野以遠(玖珂方面)=御庄以遠(南河内方面)(川西・西岩国間) | ○1-4 | ○1-5 | ○1-4 | ○1-4 | ○1-4 | ||||||||||||||
| 綾羅木以遠(安岡方面)=長門一ノ宮以遠(長府方面)(幡生・下関間) | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | |||||||||||||||
| 宇多津以遠(丸亀方面)=児島以遠(上の町方面)(坂出・宇多津間) | ○11 | ○2 7b | ○2 7b | ○2 7b | ○2 7b | ○2 7b | ○2 7b | ○2 7b | |||||||||||
| 折尾以遠(水巻方面)=折尾以遠(東水巻方面)(黒崎・折尾間) | ○3 7c | ○3 7c | ○3 7c | ○3 7c | ○3 7c | ○3 7c | ○3 7c | ○2 7d | ○2 7d | ○2 7d | ○2 7d | ○2 7d |
1999年7月17日の改訂で上記第1項の各区間については、大都市近郊区間の選択乗車中であっても区間外乗車を認める規定(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)が追加された。
規則160条の4(旧規程151条)の分岐駅通過列車の区間外乗車制度は、分岐駅に停車しない急行列車を利用する際、当該列車に乗り継ぐために、その区間において途中下車しない条件で、最寄の停車駅までの区間外乗車を認めるものである。 その変遷を表8に示す。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:2009年4月以降の◎は、大都市近郊区間の選択乗車中であっても区間外乗車を認める区間。2006年3月18日改定で、規程第151条第3項(2024年4月1日改定で規則160条の4第2項)に明示。 |
なお、1962年以前の細則117条の時代には、次のとおり号数を付し、適用区間を明示していた。
1988年3月の山陽新幹線東広島駅開業によって三原・広島間が新在別線となり、新幹線三原方面から広島で呉線に乗り継ぐ経路に片道乗車券が発売できるようになった。従来の海田市・広島間の分岐駅通過区間外乗車を可能にするため、規程に次の条項が新設された。
2024年4月1日の旅規改定で規則160条の5に移行し、条文が変わった。
また1996年1月の三島会社の運賃改訂により新下関・博多間が新在別線となったため、従来は新幹線と在来線の乗り継ぎにも適用されていた西小倉・小倉間及び吉塚・博多間の区間外乗車の取扱いを継続するために、規程に次の条項が制定された。2024年4月1日の旅規改定では、160条の4第1項の(注)に「西小倉・小倉間又は吉塚・博多間について、新幹線に乗車する場合の取扱いは別に定める。」と記載され、規則に移行していない。
規則160条の6(旧規程152条)の特定折返し列車の制度は、一定区間を折り返す列車を利用する際、途中下車しない条件で、折り返し区間の区間外乗車を認める制度である。その変遷を表9に示す。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 2011年当時の規程には記載されていたが、「時刻表」のピンクのページから削除された。規程が改定されたかどうかは不明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 規程122条に「普通列車に準用する」旨の第2項が追加されたとの情報がある。 |
1962年の細則118条の時代には、分岐駅通過列車の規定と同様、次のとおり号数を付し、適用区間を明示していた。
さらに、1958年当時は、次のとおり列車名も明示していた。
1986年11月1日の東海道本線新垂井駅廃止まで、同駅には下り列車しか停車しなかったため、米原方面発新垂井着の乗車券で大垣経由関ヶ原・新垂井間の、新垂井発岐阜方面行き乗車券で関ヶ原経由新垂井・大垣間の乗車を認める制度があった(細則72条→116条、規程150条)。
また、2004年3月13日の石勝線楓駅廃止以前には、同駅には新夕張との間の普通列車しか運転されなかったため、規程152条2項として楓と占冠以遠(トマム方面)の相互発着の乗車券を有する旅客に、楓・新夕張間の区間外乗車を認める規定があった。
そのほか、94年3月1日改訂まで存在した経路特定区間「長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂、白石以遠(厚別方面)」に関して、規程の第155条の2によって(その後第155条)札幌・千歳空港(現南千歳)間の折返し乗車が可能だった。
上記各表は、各時点の旅客営業規則や時刻表で特例の有無をあたり、作成したものである。したがって、それぞれの特例がいつ制定されて、いつ廃止されたかが明確ではない。このうち1956年以降の改訂日が官報の公示等により確認できたもの及び新線開業、ダイヤ改正等から推定したものについて、その改訂履歴を表10に示す。
| 改訂日 | 項目 | 内容 | 備考 |
| 2025/03/15 | 選択乗車 | 変更:長岡以遠(宮内方面)=新潟以遠( |
上所駅開業 |
| 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(松本・長野間、松本・穂高間) | Suica取扱範囲の拡大 | |
| 2024/03/16 | 分岐駅通過 | 廃止:越前花堂・福井 | 北陸本線のハピラインふくいへの移管 |
| 2023/08/28 | 分岐駅通過 | 廃止:夜明・日田 | 日田彦山線添田・夜明間BRT化 |
| 大都市近郊 | 縮小:福岡近郊区間(添田・今山間) | ||
| 2023/03/18 | 選択乗車 | 変更:北上以遠(六原・柳原方面)=盛岡以遠(いわて沼宮内・ |
前潟駅開業 |
| 分岐駅通過 | 廃止:大阪・新大阪 | 大阪駅うめきた地下駅開業 | |
| 2022/09/23 | 分岐駅通過 | 設定:浦上・長崎 | 西九州新幹線開業 |
| 2022/03/12 | 経路特定 | 変更:大沼以遠(仁山方面)=森以遠( |
石谷駅廃止 |
| 特定分岐 | 廃止:折尾以遠(水巻方面)=折尾以遠(東水巻方面)(黒崎・折尾間) | 折尾駅短絡線を高架ホームに移設 | |
| 2021/05/27 | 列車特定 | 規程110条から規則70条の2に移行 | |
| 2020/03/14 | 経路特定 | 変更:品川以遠( |
高輪ゲートウェイ駅開業 |
| 選択乗車 | 変更:品川以遠( |
||
| 特定都区市内等 | 拡大(都区内・東京山手線内):高輪ゲートウェイ駅 | 特定分岐 | 変更:西大井以遠(武蔵小杉方面)=品川以遠( |
| 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(いわき・浪江間)、仙台近郊区間(原ノ町・小高間) | Suica取扱範囲の拡大 | |
| 2019/11/30 | 経路特定 | 変更:品川以遠(田町・大崎方面)=鶴見以遠(新子安・国道・羽沢横浜国大方面) | 相鉄・JR連絡線開業 |
| 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(鶴見・羽沢横浜国大間) | ||
| 特定都区市内等 | 拡大(横浜市内):羽沢横浜国大駅 | ||
| 特定分岐 | 設定:横浜以遠(保土ケ谷・桜木町方面)=羽沢横浜国大(鶴見・武蔵小杉間)、新川崎=羽沢横浜国大(新川崎・武蔵小杉間)、鶴見・新子安・東神奈川・川崎以遠(蒲田・尻手方面)・国道以遠(鶴見小野方面)・大口以遠(菊名方面)=羽沢横浜国大(鶴見・横浜、新子安・横浜、東神奈川・横浜、鶴見・武蔵小杉間) | ||
| 区間外乗車 | 設定:横浜市内発着の乗車券による「鶴見ー武蔵小杉間」の区間外乗車 | ||
| 2019/03/16 | 大都市近郊 | 拡大:大阪近郊区間(おおさか東線延伸区間) | おおさか東線延伸開業 |
| 選択乗車 | 変更:新大阪以遠(東淀川・南吹田方面)=西明石以遠(大久保方面)(新大阪・三ノ宮・神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸・三ノ宮間、西明石・新神戸間)、新大阪以遠(東淀川・南吹田方面)=新神戸・神戸以遠(兵庫方面)(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間) | ||
| 特定都区市内等 | 拡大(大阪市内):おおさか東線各駅(久宝寺を除く市外駅を含む) | ||
| 区間外乗車 | 設定:大阪市内発着の乗車券による「新加美−久宝寺−加美間」の区間外乗車(規程150条2項) | ||
| 2017/03/04 | 経路特定 | 変更:大沼以遠(仁山方面)=森以遠( |
桂川駅廃止 |
| 選択乗車 | 変更:三原以遠(糸崎・須波方面)=東広島、西条以遠( |
寺家駅開業 | |
| 2016/03/26 | 経路特定 | 変更:大沼以遠( |
隣接駅に変更 |
| 選択乗車 | 変更:筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=熊本以遠( |
西熊本駅開業 | |
| 特定分岐 | 変更:武蔵白石・浜川崎以遠( |
小田栄駅開業 | |
| 分岐駅通過 | 廃止:五稜郭・函館間、中小国・蟹田間 | 江差線の道南いさりび鉄道移管、海峡線の旅客営業休止 | |
| 折返し列車 | 廃止:五稜郭・函館間 | ||
| 2015/05/30 | 特定分岐 | 設定:松島・愛宕以遠(品井沼方面)=高城町以遠(松島海岸・手樽方面)(塩釜・松島間) | 仙石東北ライン運転開始 |
| 2015/03/14 | 大都市近郊 | 拡大:仙台近郊区間(東北本線松島・高城町間) | 仙石東北ライン開業(5月30日)の先行実施 |
| 選択乗車 | 変更:広島以遠( |
新白島駅開業 | |
| 分岐駅通過 | 廃止:津幡・金沢間 | 同区間のIRいしかわ鉄道移管 | |
| 折返し列車 | 廃止:津幡・金沢間、設定:幡生・下関間 | ||
| 2014/10/01 | 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(吾妻線) | Suica取扱範囲の拡大 |
| 2014/04/01 | 大都市近郊 | 設定:仙台近郊区間(東北本線矢吹・平泉間、岩切・利府間、常磐線原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線船引・郡山間、磐越西線郡山・喜多方間、奥羽本線福島・新庄間、左沢線、陸羽東線)
拡大:東京近郊区間(中央本線韮崎・塩尻間、岡谷・辰野・塩尻間、小海線小淵沢・野辺山間、篠ノ井線塩尻・松本間、水郡線水戸・常陸大子間、上菅谷・常陸太田間)、新潟近郊区間(上越線小千谷・宮内間、羽越本線新津・村上間、白新線、信越本線直江津・長岡間、越後線柏崎・吉田間) |
Suica取扱範囲の拡大 |
| 選択乗車 | 廃止:あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田以遠(田尻・上涌谷方面)(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)、小牛田以遠(松山町・上涌谷方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)、あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田・古川間(東北本線経由、新幹線経由)、一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)=小牛田・古川間(東北本線経由、新幹線経由) | ||
| 2011/03/12 | 新在別線 | 設定:九州新幹線博多・久留米間、筑後船小屋・熊本間 | 九州新幹線博多・新八代間開業 |
| 選択乗車 | 設定:博多南・博多以遠(吉塚・小倉方面)=新鳥栖・鳥栖以遠(肥前旭方面)(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)、久留米以遠(荒木・久留米高校前方面)=新鳥栖・鳥栖以遠(田代方面)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)、博多南・博多以遠(吉塚・小倉方面)=久留米以遠(荒木・久留米高校前方面)(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)、筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=熊本以遠(川尻・平成方面)(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)、筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=新大牟田・大牟田以遠(荒尾方面)(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)、筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)=新玉名・玉名以遠(肥後伊倉方面)(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)、熊本以遠(川尻・平成方面)=新大牟田・大牟田以遠(銀水方面)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)、熊本以遠(川尻・平成方面)=新玉名・玉名以遠(大野下方面)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間) | ||
| 2010/03/13 | 選択乗車 | 変更:品川以遠(田町・大崎・西大井方面) 廃止:小野、辰野以遠(宮木方面)=岡谷以遠(下諏訪方面)(川岸経由、塩尻経由) |
東海道本線(品鶴線)に武蔵小杉駅開業 |
| 特定分岐 | 変更:西大井以遠(武蔵小杉 |
||
| 2009/03/14 | 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(常磐線高萩・いわき間、上越線渋川・水上間、烏山線、信越本線高崎・横川間、総武本線成東・銚子間、外房線大原・安房鴨川間、内房線君津・安房鴨川間、成田線成田・松岸間、鹿島線、久留里線) | Suica取扱範囲の拡大 |
| 選択乗車 | 廃止:日暮里以遠(鶯谷・西日暮里・尾久方面)・両国以遠(浅草橋方面)=成田以遠(久住・空港第2ビル方面)(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)、佐倉以遠(物井方面)=松岸・銚子(総武本線経由、成田線経由)、蘇我以遠(本千葉方面・千葉みなと方面)=館山・安房鴨川間(外房線経由、内房線経由) | ||
| 2008/04/01 | 特定都区市内等 | 「単駅指定」を規則に規定 | |
| 2008/03/15 | 経路特定 | 岩国以遠( |
高島、和木駅開業 |
| 選択乗車 | 変更:相生以遠(竜野方面)= |
||
| 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(常磐線日立・高萩間、日光線)、大阪近郊区間(おおさか東線)、新潟近郊区間(信越本線長岡・東三条間、磐越西線新津・五泉間) | おおさか東線開業、Suica取扱範囲の拡大 | |
| 2006/03/18 | 分岐駅通過列車 | 廃止:香取・佐原間、木津・奈良間、東津山・津山間 | |
| 2005/12/10 | 選択乗車 | 変更:広島以遠( |
天神川駅開業 |
| 2004/11/27 | 選択乗車 | 廃止:新津以遠(古津・東新津方面)=新発田以遠(加治方面)(羽越本線経由、信越本線・白新線経由)、長岡以遠(宮内方面)=新発田以遠(加治方面)(新幹線及び白新線経由、信越本線及び羽越本線経由)、長岡以遠(宮内方面)=東三条・燕三条間(信越本線経由、新幹線経由) | 新潟地区にSuica導入 |
| 大都市近郊 | 設定:新潟近郊区間(信越本線東三条・新潟間、越後線吉田・新潟間、弥彦線、羽越本線新津・新発田間、白新線) | ||
| 2004/10/16 | 選択乗車 | 変更:熊谷以遠(行田方面)=高崎以遠( |
高崎問屋町駅開業 |
| 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(伊東線、中央本線大月・甲府・韮崎間、東北本線宇都宮・黒磯間、常磐線勝田・日立間、上越線新前橋・渋川間、外房線茂原・大原間) | ||
| 特定都区市内等 | 変更:(規則89条)北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、 |
||
| 2004/03/13 | 新在別線 | 設定:上越新幹線熊谷・高崎間 | 本庄早稲田駅開業 |
| 選択乗車 | 設定:熊谷以遠(行田方面)=高崎以遠(井野・北高崎・安中榛名方面)(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)、熊谷以遠(行田方面)=本庄早稲田、本庄以遠(神保原方面)(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)、高崎以遠(井野・北高崎・安中榛名方面)=本庄早稲田、本庄以遠(岡部方面)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)、変更:高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=越後湯沢以遠(石打・ガーラ湯沢方面)(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)、高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=上毛高原、後閑以遠(上牧方面)(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間) | ||
| 経路特定 | 設定:日暮里以遠(鶯谷・三河島方面)=赤羽以遠(川口・北赤羽方面)(尾久経由東北本線、○王子経由東北本線)、赤羽以遠(尾久・東十条・十条方面)=大宮以遠(土呂・宮原・日進方面)(戸田公園・与野本町経由東北本線、○川口・浦和経由東北本線)、品川以遠(田町・大崎方面)=鶴見以遠(新子安方面)(西大井経由東海道本線、○大井町経由東海道本線)、東京以遠(有楽町・神田方面)=蘇我以遠(鎌取・浜野方面)(京葉線、○総武本線・外房線)、大阪以遠(塚本・新大阪方面)=天王寺以遠(東部市場前・美章園方面)(福島経由大阪環状線、○天満経由大阪環状線) | 70条特定区間(列車特定区間)から移行 | |
| 70条特定 | 縮小:東京大環状線(赤羽以北、東京・錦糸町以東、品川以南)、廃止:大阪環状線全区間 | ||
| 列車特定 | 廃止:品川以遠(田町・大崎方面)=鶴見以遠(新子安方面)(東海道本線(新川崎経由)、○東海道本線(川崎経由)) | 経路特定区間に格上げ | |
| 大都市近郊 | 縮小:東京近郊区間(東北新幹線東京・宇都宮間、上越新幹線大宮・高崎間) | ||
| その他区間外 | 変更:(規程150条2項)規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間(注:塚本-尼崎-加島間)の全部又は一部について、 |
||
| 2003/10/01 | 新在別線 | 廃止:東京・新横浜間、設定:品川・新横浜間 | 東海道新幹線品川駅開業 |
| 選択乗車 | 廃止:東京以遠(神田・新日本橋・八丁堀方面)=小田原以遠(早川方面)(品川・横浜間、品川・新横浜間)
(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)、設定:品川以遠(田町・大崎方面)・西大井・新川崎=小田原以遠(早川方面)(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)、変更: |
||
| 2002/12/01 | 選択乗車 | 設定:北上以遠(六原・柳原方面)=盛岡以遠(いわて沼宮内・大釜・上盛岡方面)(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)
廃止:新花巻以遠(小山田方面)=盛岡以遠(厨川・大釜・上盛岡方面)(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)、北上以遠(六原・柳原方面)=新花巻以遠(小山田方面)(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)、北上以遠(六原・柳原方面)=花巻以遠(花巻空港方面)(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)、花巻以遠(村崎野方面)=盛岡以遠(厨川・大釜・上盛岡方面)(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)、岩沼以遠(槻木・亘理方面)・羽前千歳以遠(北山形・南出羽方面)=塩釜・本塩釜(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)、仙台以遠(東照宮・長町方面)=松島・松島海岸(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)、仙台以遠(東照宮・長町方面)=品井沼以遠(鹿島台方面)・高城町以遠(手樽方面)(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)、長岡以遠(宮内方面)=東三条以遠(保内方面)(信越本線経由、新幹線経由)、大宮以遠(日進・北与野・与野方面)=桐生(井野及び前橋経由、小山経由)、大船以遠(藤沢・北鎌倉方面)=桜木町・磯子間 (戸塚経由、本郷台経由)、横浜以遠(東神奈川方面)=磯子・本郷台間 (桜木町経由、戸塚経由)、柘植以遠(加太方面)=大阪以遠(塚本方面)、安治川口・桜島間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)、奈良以遠(木津方面)=大和新庄以遠(御所方面)(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)、東部市場以遠(平野方面)=大阪以遠(塚本・新大阪方面)(天王寺・大阪間、天王寺・JR難波間)、大阪以遠(天満・福島方面)・尼崎以遠(立花方面)=綾部以遠(梅迫方面)(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)、益田以遠(石見津田方面)=厚狭以遠(埴生方面)(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)、益田以遠(石見津田方面)=幡生以遠(下関方面)(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)、仙崎、長門市以遠(長門三隅方面)=幡生以遠(下関方面)(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由) |
|
| 列車特定 | 廃止:大宮以遠(与野・与野本町・日進方面)=青森以遠(油川方面)(高崎線、上越線及び信越本線(白新線を含む)、羽越本線及び奥羽本線、○東北本線) | 東北新幹線延伸に伴う盛岡・八戸間のいわて銀河鉄道・青い森鉄道への移管 | |
| 特定分岐 | 設定:西大井以遠(新川崎方面)=品川以遠(田町方面)(大崎・品川間) | 「新宿湘南ライン」大崎駅設置 | |
| 2002/04/01 | 選択乗車 | 廃止:肥前山口以遠(牛津方面)=岩松・竹松間 (早岐経由、諫早経由) | |
| 2001/12/01 | 経路特定 | 廃止:日暮里以遠(鶯谷・西日暮里・尾久方面)=岩沼以遠(○東北本線経由、常磐線経由)、岡谷以遠(下諏訪方面)=塩尻(洗馬・広丘方面)(辰野経由、○みどり湖経由) | |
| 列車特定 | 設定:岡谷以遠(下諏訪方面)=塩尻(洗馬・広丘方面)(辰野経由、○みどり湖経由) | 経路特定から急行「アルプス」の列車特定に格下げ | |
| 2001/03/01 | 選択乗車 | 変更:柘植以遠(加太方面)=大阪以遠(塚本方面) |
ユニバーサルシティ駅開業 |
| 2000/03/11 | 選択乗車 | 変更:あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田以遠(田尻・上涌谷方面)(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)、あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)、あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田・古川間(東北本線経由、新幹線経由)、あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)、あおば通、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=くりこま高原、新田以遠(石越方面)(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)、あおば通、仙台以遠(東照宮・長町方面)=松島・松島海岸(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)、あおば通、仙台以遠(東照宮・長町方面)=品井沼以遠(鹿島台方面)・高城町以遠(手樽方面)(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)、福島以遠(南福島・笹木野方面)=あおば通、仙台以遠(東照宮・東仙台・榴ケ岡方面)(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)、あおば通、仙台以遠(東照宮、東仙台・榴ケ岡方面)=白石蔵王、白石以遠(越河方面)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間) | あおば通駅開業 |
| 1999/07/17 | 特定分岐 | 「規則第157条第2項により当該区間を乗車する場合を含む。」を挿入 | |
| 1999/06/01 | 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(東海道本線平塚・熱海間、八高線高麗川・倉賀野間、東北本線小山・宇都宮間、常磐線土浦・勝田間、高崎線熊谷・高崎間、上越線高崎・新前橋間、両毛線、水戸線、内房線木更津・君津間) | |
| 1998/12/01 | 大都市近郊 | 拡大:大阪近郊区間(東海道本線米原・京都間、湖西線、福知山線宝塚・谷川間、北陸本線米原・近江塩津間、山陽本線西明石・相生間、兵庫・和田岬間、加古川線、赤穂線相生・播州赤穂間、山陰本線京都・園部間、関西本線木津・拓殖間、草津線、和歌山線高田・和歌山間) | |
| 1998/10/01 | 分岐駅通過 | 設定:池谷・勝瑞間(高徳線) | 池谷不停車、勝瑞停車の列車運行開始 |
| 1997/10/01 | 列車特定 | 廃止:高崎以遠(倉賀野方面)・新前橋以遠(前橋方面)・井野駅=直江津以遠(谷浜方面)(上越線群馬総社・宮内間及び信越本線長岡・黒井間、○信越本線) | 北陸新幹線開業に伴う横川・軽井沢間の廃止、軽井沢・篠ノ井間のしなの鉄道への移管 |
| 分岐駅通過 | 廃止:篠ノ井・長野間 | ||
| 1997/03/08 | 70条特定 | 設定:JR東西線 | JR東西線開業 |
| 大都市近郊 | 拡大:大阪近郊区間(JR東西線、福知山線尼崎・宝塚間) | ||
| 区間外乗車 | 設定:大阪市内発着の乗車券による「塚本−尼崎−加島間」の区間外乗車(150条2項) | ||
| 1996/07/18 | 分岐駅通過 | 設定:田吉・南宮崎間、廃止:南宮崎・宮崎間 | 宮崎空港線開業 |
| 1996/03/16 | 特定分岐 | 設定:武蔵白石・浜川崎以遠(川崎新町・昭和方面)=大川(武蔵白石・安善間) | 大川支線の電車が武蔵白石駅通過 |
| 分岐駅通過 | 設定:東神奈川・横浜間 | 「はまかいじ」運行開始 | |
| 1994/06/15 | 大都市近郊 | 拡大:大阪近郊区間(関西空港線) | 関西空港線開業 |
| 1995/05/29 | 選択乗車 | 変更:名古屋以遠( |
尾頭橋駅開業(95/03/16) |
| 1995/03/16 | 選択乗車 | 変更:名古屋以遠( |
尾頭橋駅開業 |
| 1994/09/04 | 選択乗車 | 変更:東部市場以遠(平野方面)=大阪以遠(塚本・新大阪方面)(天王寺・大阪間、天王寺・ |
JR難波駅改称 |
| 1994/03/01 | 経路特定 | 廃止:長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂、白石以遠(厚別方面)(○函館本線経由、室蘭本線及び千歳線経由)、肥前山口以遠(牛津方面)=諫早以遠(西諫早方面)(○長崎本線経由、佐世保線及び大村線経由) | |
| 1993/03/18 | 選択乗車 | 変更:日暮里以遠(鶯谷・西日暮里・尾久方面)・両国以遠(浅草橋方面)=成田以遠(久住・ |
空港第2ビル駅開業(92/12/03) |
| 1992/07/01 | 分岐駅通過 | 設定:南千歳・新千歳空港間 | 千歳線南千歳・新千歳空港間開業 |
| 折返し列車 | 設定:南千歳・新千歳空港間 | ||
| 1991/03/19 | 選択乗車 | 変更:日暮里以遠(鶯谷・西日暮里・尾久方面)・両国以遠(浅草橋方面)=成田以遠(久住・成田空港方面)(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由) | 成田空港駅開業 |
| 1990/12/22 | 選択乗車 | 変更:高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=越後湯沢以遠(石打・ガーラ湯沢方面)(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)、越後湯沢以遠(石打・ガーラ湯沢方面)=上毛高原、後閑以遠(沼田方面)(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間) | ガーラ湯沢駅開業 |
| 1990/12/12 | 大都市近郊 | 縮小:福岡近郊区間(宮田線) | 宮田線廃止 |
| 1990/03/10 | 70条特定 | 設定:総武本線錦糸町・千葉間、外房線千葉・蘇我間、京葉線 | 京葉線東京駅延伸開業 |
| 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(京葉線東京・新木場) | ||
| 選択乗車 | 廃止:西船橋以遠(下総中山方面・船橋法典方面)=蘇我以遠(鎌取方面・浜野方面)(総武本線・外房線経由、京葉線経由)、西船橋以遠(下総中山方面・船橋法典方面)=二俣新町(市川塩浜経由、南船橋経由) | ||
| 設定:一ノ関以遠(有壁・真滝方面)=水沢江刺、水沢以遠(金ケ崎方面)(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=くりこま高原、新田以遠(石越方面)(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)、一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)=くりこま高原、新田以遠(梅ケ沢方面)(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)、小牛田以遠(松山町・上涌谷方面)=くりこま高原、新田以遠(石越方面)(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間) | くりこま高原駅開業 | ||
| 1989/11/11 | 選択乗車 | 廃止:大府以遠(共和方面)=刈谷・緒川 (大府・刈谷間、大府・緒川間)、変更: |
東部市場駅開業 |
| 1989/10/01 | 選択乗車 | 廃止:金田以遠(赤池方面)=田川後藤寺以遠(池尻・船尾方面)(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由) | 田川線、伊田線、糸田線の平成筑豊鉄道転換 |
| 大都市近郊 | 縮小:福岡近郊区間(田川線、伊田線、糸田線) | ||
| 1989/07/09 | 選択乗車 | 変更:名古屋以遠( |
東海道本線に金山駅開業 |
| 分岐駅通過 | 設定:金山・名古屋間 | ||
| 1989/05/01 | 列車特定 | 廃止:音威子府以遠(咲来方面)=南稚内・稚内(天北線、○宗谷本線) | 天北線廃止 |
| 選択乗車 | 廃止:新旭川以遠(旭川方面)=紋別・渚滑間(名寄経由、遠軽経由) | 名寄本線廃止 | |
| 1989/03/29 | 選択乗車 | 変更:大宮以遠(日進・北与野・与野方面)=桐生 |
足尾線転換 |
| 1988/12/01 | 大都市近郊 | 拡大:東京近郊区間(京葉線新木場・南船橋間、千葉みなと・蘇我間、市川塩浜・西船橋間) | 京葉線延伸開業 |
| 選択乗車 | 設定:西船橋以遠(下総中山方面・船橋法典方面)=蘇我以遠(鎌取方面・浜野方面)(総武本線・外房線経由、京葉線経由)、西船橋以遠(下総中山方面・船橋法典方面)=二俣新町(市川塩浜経由、南船橋経由) | ||
| 1988/08/31 | 大都市近郊 | 縮小:福岡近郊区間(上山田線) | 上山田線廃止 |
| 1988/03/13 | 新在別線 | 設定:三島・静岡間(東海道新幹線)、福山・三原間、三原・広島間(山陽新幹線) | 新富士、新尾道、東広島駅開業 |
| 選択乗車 | 設定:三島以遠(函南方面)=新富士、富士以遠(富士川・柚木方面)(三島・富士間、三島・新富士間)、静岡以遠(安倍川方面)=新富士、富士以遠(吉原・柚木方面)(静岡・富士間、静岡・新富士間)、三島以遠(函南方面)=静岡以遠(安倍川方面)(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)、福山以遠(東福山・備後本庄方面)=新尾道、尾道以遠(糸崎方面)(福山・尾道間、福山・新尾道間)、三原以遠(本郷・須波方面)=新尾道、尾道以遠(松永方面)(三原・尾道間、三原・新尾道間)、福山以遠(東福山・備後本庄方面)=三原以遠(本郷・須波方面)(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)、三原以遠(糸崎・須波方面)=東広島、西条以遠(八本松方面)(三原・西条間、三原・東広島間)、広島以遠(横川・矢賀方面)=東広島、西条以遠(西高屋方面)(広島・西条間、広島・東広島間)、三原以遠(糸崎・須波方面)=広島以遠(横川・矢賀方面)(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)、変更:北上以遠(六原・柳原方面)=花巻以遠( |
||
| 分岐駅通過 | 設定:規程151条の2 | ||
| 1987/10/01 | 分岐駅通過 | 設定:西小倉・小倉間 | 鹿児島本線に西小倉駅開業 |
| 折返し列車 | 設定:西小倉・小倉間 | ||
| 1987/07/25 | 特定分岐 | 廃止:柱野以遠(玖珂方面)=御庄以遠(南河内方面)(川西・西岩国間) | 岩日線の錦川鉄道転換 |
| 1987/03/28 | 選択乗車 | 廃止:南宮崎以遠(宮崎方面)=志布志以遠(菱田方面)(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由) | 志布志線の廃止 |
| 1987/03/27 | 経路特定 | 廃止:河原田以遠(南四日市方面)=津以遠(阿漕以遠)(○伊勢線経由、関西本線・紀勢本線経由) | 伊勢線の伊勢鉄道転換 |
| 選択乗車 | 廃止:亀山以遠(関方面)=鈴鹿・東一新田(河原田経由、津経由) | ||
| 分岐駅通過 | 廃止:河原田・四日市間 | ||
| 1986/11/01 | 選択乗車 | 変更:名古屋以遠(尾頭橋・八田方面)=岐阜羽島、岐阜以遠( |
西岐阜駅開業 |
| 1986/03/03 | 選択乗車 | 設定:向井原以遠(伊予市方面)=伊予大洲以遠(西大洲方面)(伊予長浜経由、内子経由) | |
| 1985/09/30 | 70条特定 | 設定:武蔵野線武蔵浦和・南浦和間、東北本線赤羽・大宮間(川口経由、北赤羽経由) | 「埼京線」開業 |
| 1985/07/01 | 選択乗車 | 廃止:下北以遠(赤川方面)=大湊・田名部(下北・大湊間、下北・田名部間) | 大畑線の下北交通移管 |
| 特定分岐 | 廃止:赤川以遠(金谷沢方面)=田名部以遠(樺山方面)(下北・大湊間) | ||
| 1985/04/20 | 選択乗車 | 設定:相生以遠(竜野方面)=東岡山以遠(岡山方面)(山陽本線経由、赤穂線経由) | |
| 1985/04/01 | 大都市近郊区間 | 福岡近郊区間縮小 | 室木線、勝田線、添田線、香月線、渚滑線等廃止 |
| 選択乗車 | 変更:新旭川以遠(旭川方面)=紋別・渚滑間 |
||
| 1985/03/14 | 新在別線 | 設定:一関・北上間、北上・盛岡間 | 水沢江刺、新花巻駅開業 |
| 選択乗車 | 設定:新花巻以遠(小山田方面)=盛岡以遠(厨川・大釜・上盛岡方面)(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)、北上以遠(六原・柳原方面)=新花巻以遠(小山田方面)(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)、北上以遠(六原・柳原方面)=花巻以遠(二枚橋方面)(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)、花巻以遠(村崎野方面)=盛岡以遠(厨川・前潟・上盛岡方面)(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)、一ノ関以遠(有壁・真滝方面)=水沢江刺、水沢以遠(金ケ崎方面)(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)、北上以遠(村崎野・柳原方面)=水沢江刺、水沢以遠(陸中折居方面)(北上・水沢間、北上・水沢江刺間) | ||
| 廃止:中田以遠(地蔵橋方面)=小松島駅・南小松島駅(中田・小松島間、中田・南小松島間) | 小松島線廃止 | ||
| 1984/04/01 | 選択乗車 | 変更:新津以遠(古津・東新津方面)=新発田以遠(加治 |
赤谷線廃止 |
| 1983/07/05 | 経路特定 | 設定:岡谷以遠(下諏訪方面)=塩尻(洗馬・広丘方面)(辰野経由、○みどり湖経由) | みどり湖経由短絡線開業 |
| 選択乗車 | 設定:辰野以遠(宮木方面)=岡谷以遠(下諏訪方面)(川岸経由、塩尻経由)、川岸、辰野以遠(宮木方面)=塩尻以遠(洗馬・広丘方面)(信濃川島経由、岡谷経由) | ||
| 1983/03/22 | 選択乗車 | 廃止:博多以遠(越前簑島方面)・吉塚以遠(原町・御手洗方面)=直方以遠(中泉方面)(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)、山本以遠(相知・肥前久保方面)=唐津、西唐津、東唐津以遠(虹ノ松原方面)(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間) | 筑肥線博多・姪浜間廃止 |
| 1982/11/15 | 新在別線 | 設定:高崎・越後湯沢間、長岡・新潟間 | 上越新幹線開業 |
| 選択乗車 | 設定:長岡以遠(宮内方面)=新発田以遠(加治・五十公野方面)(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)、長岡以遠(宮内方面)=東三条以遠(保内・越後大崎方面)(信越本線経由、新幹線経由)、長岡以遠(宮内方面)=新潟以遠(白山・東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)、長岡以遠(宮内方面)=東三条・燕三条間(信越本線経由、新幹線経由)、高崎以遠(倉賀野・北高崎・安中榛名方面)=越後湯沢以遠(石打方面)(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)、越後湯沢以遠(石打方面)=上毛高原、後閑以遠(沼田方面)(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)、高崎以遠(倉賀野・北高崎方面)=上毛高原、後閑以遠(上牧方面)(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間) | ||
| 1982/11/03 | 選択乗車 | 金田以遠(赤池方面)=田川後藤寺以遠(池尻・船尾方面)(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由) | 後藤寺駅開業 |
| 1982/06/23 | 新在別線 | 設定:福島・仙台間、仙台・一ノ関間 | 東北新幹線開業 |
| 選択乗車 | 設定:仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田以遠(田尻・上涌谷方面)(東北本線経由、新幹線・陸羽東線経由)、小牛田以遠(松山町・上涌谷方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(東北本線経由、新幹線・陸羽東線経由)、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=一ノ関以遠(山ノ目・真滝方面)(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)、仙台以遠(東照宮・長町・榴ケ岡方面)=小牛田・古川間(東北本線経由、新幹線経由)、福島以遠(南福島・笹木野方面)=仙台以遠(東照宮・東仙台・榴ケ岡方面)(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)、仙台以遠(東照宮・東仙台・榴ケ岡方面)=白石蔵王、白石以遠(越河方面)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)、仙台以遠(東照宮・東仙台・榴ケ岡方面)=白石蔵王、白石以遠(越河方面)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間) | ||
| 1982/04/20 | 選択乗車 | 変更:名古屋以遠(熱田・金山・八田方面)=岐阜羽島、岐阜以遠(穂積・長森方面)(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)「ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互間発着を除く」追加 | |
| 1981/10/01 | 列車特定 | 設定:白石以遠(苗穂方面)=新得以遠(十勝清水方面)(函館本線及び根室本線、○千歳線及び石勝線) | 石勝線開業 |
| 1981/04/20 | 選択乗車 | 変更:徳山以遠( |
周防富田駅改称 |
| 1981/04/07 | 選択乗車 | 変更:大阪以遠(天満・福島方面)・尼崎以遠(立花 |
福知山線尼崎港支線廃止 |
| 1980/04/20 | 選択乗車 | 変更:東京以遠(神田・新日本橋方面)=小田原以遠(早川方面)(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)、 |
|
| 1976/11/06 | 選択乗車 | 設定:門司以遠(小倉方面)=下関・門司港 (門司・下関間、門司・門司港間) | |
| 1975/03/10 | 新在別線 | 設定:広島・徳山間 | 新幹線博多延伸開業 |
| 選択乗車 | 設定:新大阪以遠(東淀川方面)=新神戸・神戸以遠(兵庫方面)(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)、西明石以遠(大久保方面)=新神戸・神戸以遠(元町方面)(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)、広島以遠(向洋・矢賀方面)=新岩国、岩国以遠(南岩国・西岩国方面)(広島・岩国間、広島・新岩国間)、徳山以遠(新南陽方面)=新岩国、岩国以遠(大竹方面)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)、広島以遠(向洋・矢賀方面)=徳山以遠(新南陽方面)(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間) | ||
| 経路特定 | 設定:山科以遠(京都方面)=近江塩津以遠(新疋田方面)(東海道本線及び北陸本線経由、○湖西線経由) | ||
| 1974/07/20 | 分岐駅通過 | 設定:京都・山科間 | 湖西線開業 |
| 1974/04/01 | 大都市近郊 | 設定:福岡近郊区間(鹿児島本線門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線小倉・行橋間、日田彦山線城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線、上山田線) | |
| 1973/10/01 | 大都市近郊 | 拡大:大阪近郊区間(関西本線木津・湊町間、奈良線、桜井線、片町線木津・長尾間、和歌山線王寺・高田間) | |
| 1973/09/09 | 経路特定 | 変更:長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂、白石以遠( |
千歳線線路付替え |
| 1973/09/01 | 経路特定 | 設定:河原田以遠(南四日市方面)=津以遠(阿漕以遠)(○伊勢線経由、関西本線及び紀勢本線経由) | 伊勢線開業 |
| 選択乗車 | 設定:亀山以遠(関方面)=鈴鹿・東一新田間(河原田経由、津経由) | ||
| 分岐駅通過 | 設定:河原田・四日市間 | ||
| 1973/04/09 | 選択乗車 | 設定:大船以遠(藤沢・北鎌倉方面)=桜木町・磯子間 (戸塚経由、本郷台経由)、横浜以遠(東神奈川方面)=磯子・本郷台間(桜木町経由、戸塚経由) | 根岸線全通 |
| 1973/04/01 | 大都市近郊 | 設定:東京近郊区間(東海道本線東京・平塚間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線東京・大月間、青梅線、五日市線、八高線八王子・高麗川間、東北本線東京・小山間、山手線、赤羽線、日暮里・尾久・赤羽間、常磐線日暮里・土浦間、川越線、高崎線大宮・熊谷間、総武本線東京・成東間、錦糸町・御茶ノ水間、外房線千葉・茂原間、内房線蘇我・木更津間、東金線)、大阪近郊区間(東海道本線京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線神戸・西明石間、片町線長尾・片町間、阪和線)。旧電車特定区間の中央本線国分寺・東京競馬場間は削除 | |
| 選択乗車 | 廃止:八王子以遠(西八王子又は片倉方面)=拝島以遠(東福生、牛浜又は熊川方面)(八高線経由、中央本線及び青梅線経由) | ||
| 1972/10/02 | 選択乗車 | 設定:喜々津以遠(西諫早方面)=浦上・長崎(現川経由、本川内経由) | 長崎本線短絡線開業 |
| 1972/09/01 | 経路特定 | 廃止:赤羽以遠(川口方面)=日暮里以遠(上野・北千住方面)(尾久経由東北本線、○王子経由東北本線) | |
| 特定都区市内等 | 札幌、仙台、広島、北九州、福岡各市を追加。東京電車環状線内を「東京山手線内」に変更 | ||
| 1972/07/15 | 70条特定 | 設定:総武本線東京・錦糸町間、秋葉原・錦糸町間 | 総武快速線開業 |
| 選択乗車 | 変更:蘇我以遠(本千葉方面方面)=館山・安房鴨川間( |
||
| 1972/03/15 | 新在別線 | 設定:新大阪・西明石間 | 新幹線新大阪・岡山間開業 |
| 特定都区市内等 | 設定:新大阪駅・大阪駅発着制度 | ||
| 選択乗車 | 設定:大阪以遠(天満・福島方面)=西明石以遠(大久保方面)(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)
廃止:紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)=東和歌山以遠(紀三井寺方面)(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)、紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)=紀和・和歌山市(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間) |
||
| 分岐駅通過 | 設定:新大阪・大阪間 | ||
| 1971/04/20 | 選択乗車 | 変更:日暮里以遠(鶯谷・ |
|
| 1971/04/01 | 列車特定 | 廃止:多度津以遠(海岸寺方面)=佐古以遠(徳島方面)(予讃本線、土讃本線及び徳島本線、○予讃本線及び高徳本線) | |
| 1971/03/01 | 選択乗車 | 設定:蘇我以遠(本千葉方面)=館山・安房鴨川間(外房線経由、内房線経由) | |
| 1970/10/01 | 選択乗車 | 変更: 設定:八王子以遠(西八王子又は片倉方面)=拝島以遠(東福生、牛浜又は熊川方面)(八高線経由、中央本線及び青梅線経由) |
|
| 1970/03/25 | 選択乗車 | 変更:紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)=東和歌山以遠(紀三井寺方面)(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)、紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)=紀和・和歌山市紀和・和歌山市(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間) | |
| 1970/03/10 | 選択乗車 | 変更:「大宮以遠(日進・与野方面)=桐生以遠(相老方面)(井野及び前橋経由、小山経由)」及び「佐倉以遠(物井方面)=松岸・銚子(総武本線経由、成田線経由)」の「券面経路以外の途中下車禁止」削除 | |
| 1969/05/10 | 特定都区市内等 | 二大都市制度に横浜、名古屋、京都、神戸各市内を追加、特定都区市内制度に変更。横浜・新横浜間発着制度廃止 | |
| 選択乗車 | 変更:小田原以遠(早川方面)=横浜・新横浜間( |
||
| 大都市近郊 | 東京附近の電車特定区間相互発着の乗車券による選択乗車を規則に規定 | ||
| 1968/10/01 | 選択乗車 | 設定:小田原以遠(早川方面)=東神奈川以遠(新子安方面)(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)、廃止:戸塚以遠(保土ヶ谷方面)=藤沢以遠(辻堂方面)・鎌倉以遠(逗子方面)(大船・藤沢間、大船・鎌倉間) | |
| 1968/08/01 | 選択乗車 | 変更:岩沼以遠(槻木・亘理方面)・羽前千歳以遠(北山形・南出羽方面)=塩釜・本塩釜(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間) | |
| 1968/03/01 | 選択乗車 | 変更:紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)= |
東和歌山駅改称 |
| 1968/02/01 | 選択乗車 | 変更:紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬・六十谷方面)=東和歌山以遠(紀三井寺方面)(紀伊中ノ島・ |
和歌山駅改称 |
| 1967/05/10 | 選択乗車 | 変更:平野以遠(加美方面)=大阪以遠(塚本・新大阪方面)(天王寺・大阪間、天王寺 |
|
| 1967/03/01 | 選択乗車 | 設定:新旭川以遠(旭川方面)=紋別・渚滑間、渚滑線内(名寄経由、遠軽経由)、下北以遠(赤川方面)=大湊・田名部(下北・大湊間、下北・田名部間) | |
| 1966/10/01 | 選択乗車 | 変更: |
|
| 1966/04/01 | 選択乗車 | 変更:平野以遠(加美方面)=大阪以遠(塚本・新大阪方面)(天王寺・大阪間、天王寺・新今宮・湊町間) | |
| 1966/03/05 | 経路特定 | 設定:長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂以遠(白石方面) (○函館本線、室蘭本線・千歳線) | 経路特定区間に格上げ |
| 列車特定 | 廃止:長万部以遠(中の沢方面)=札幌、苗穂以遠(白石方面) (○函館本線、室蘭本線・千歳線) | ||
| 電車特定区間 | 拡大:東海道本線横浜・大船間、横須賀線、青梅線、五日市線 | ||
| 1965/10/01 | 選択乗車 | 廃止:下関以遠(幡生方面)=門司以遠(小倉方面)(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
設定:小郡以遠(四辻・*周防下郷方面)=宇部以遠(小野田方面)(山陽本線経由、宇部線経由)、石見益田以遠(石見津田方面)=厚狭以遠(埴生方面)(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)*周防下郷は65/11/01に追加 |
|
| 1965/06/15 | 選択乗車 | 設定:南宮崎以遠(宮崎方面)=志布志以遠(菱田方面)(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由) | |
| 1964/10/01 | 列車特定 | 設定:尼崎以遠(塚本方面)=和田山以遠(養父方面)(山陽本線、播但線及び山陰本線)、○東海道本線、福知山線及び山陰本線)、多度津以遠(海岸寺方面)=佐古以遠(徳島方面)(予讃本線、土讃本線及び徳島本線、○予讃本線、及び高徳本線) | |
| 新在別線 | 設定:東京・小田原間、名古屋・米原間 | 東海道新幹線開業 | |
| 選択乗車 | 設定:小田原以遠(早川方面)=横浜・新横浜(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)、東京以遠(神田方面)=小田原以遠(早川方面)(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)、名古屋以遠(熱田・金山・八田方面)=岐阜羽島、岐阜以遠(穂積・長森方面)(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)、米原以遠(彦根・坂田方面)=岐阜羽島、岐阜以遠(木曽川・長森方面)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)、名古屋以遠(熱田・金山・八田方面)=米原以遠(彦根・坂田方面)(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間) | ||
| 特定都区市内等 | 設定:横浜・新横浜間発着制度 | ||
| 1964/09/15 | 選択乗車 | 変更:居能以遠( |
|
| 1964/05/11 | 選択乗車 | 廃止:木ノ本以遠(高月方面)=敦賀以遠(南今庄・西敦賀方面)(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由) | 柳ケ瀬線廃止 |
| 1963/04/28 | 選択乗車 | 廃止:千葉以遠(西千葉方面)=成東以遠(松尾方面)(四街道経由、誉田経由) | |
| 1962/11/01 | 選択乗車 | 変更:仙崎、 |
|
| 1962/09/01 | 選択乗車 | 変更:木ノ本以遠(高月方面)=敦賀以遠( |
|
| 1962/05/15 | 選択乗車 | 廃止:小樽築港以遠(朝里方面)=小樽以遠(塩谷方面)、手宮(南小樽・小樽間、南小樽・手宮間) | 手宮線廃止 |
| 1962/04/20 | 経路特定 | 廃止:岩切以遠(東仙台方面)=品井沼以遠(鹿島台方面)(陸前山王駅経由東北本線、○利府駅経由東北本線) | 東北本線利府・品井沼間廃止 |
| 選択乗車 | 変更:仙台以遠(北仙台・長町方面)= 廃止:品井沼以遠(鹿島台方面)=松島・新松島(品井沼・松島間、品井沼・新松島間) |
||
| 1962/04/01 | 選択乗車 | 設定:石見益田以遠(石見津田方面)=幡生以遠(下関方面)(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由) | |
| 1962/01/15 | 選択乗車 | 変更:加治木以遠(帖佐方面)=霧島神宮以遠(北永野田方面)・ |
牧園駅改称 |
| 1961/10/01 | 列車特定 | 設定:音威子府以遠(咲来方面)=南稚内・稚内(天北線、○宗谷本線)、新津以遠(東新津・古津方面)=新発田以遠(加治方面)(白新線及び信越本線新潟・新津間、○羽越本線) | |
| 1961/04/25 | 70条特定 | 設定:大阪環状線 | 大阪環状線開業 |
| 選択乗車 | 変更:拓植以遠(加太方面)=大阪以遠(塚本 |
||
| 電車特定区間 | 拡大:大阪環状線(西九条・天王寺間) | ||
| 1961/04/06 | 特定都区市内等 | 二大都市制度を201キロ以上に変更 | |
| 選択乗車 | 変更:金田以遠(赤池方面)=後藤寺以遠(池尻・船尾方面)( |
||
| 1960/07/01 | 選択乗車 | 設定:仙崎、正明市以遠(長門三隅方面)=幡生以遠(下関方面)(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)、変更:仙台以遠(北仙台・長町方面)=品井沼以遠(鹿島台方面)・高城町以遠(手樽方面)(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)(松島・品井沼間、新松島・品井沼間)、香春以遠(採銅所方面)=添田以遠(豊前桝田方面)(日田彦山線経由、 |
|
| 1958/10/01 | 70条特定 | 設定:東海道本線東京・品川間、中央本線東京・新宿間、東北本線東京・赤羽間、日暮里・尾久・赤羽間、山手線品川・赤羽間、池袋・田端間、総武本線御茶ノ水・秋葉原間 | |
| 1957/04/01 | 経路特定 | 廃止:長万部以遠(中ノ沢方面)=岩見沢以遠(峰延・萱野方面)(函館本線、○室蘭本線)、福島以遠(南福 島方面)=青森以遠(油川・函館方面)(奥羽本線、○東北本線) | |
| 列車特定 | 設定:福島以遠(南福島方面)=青森以遠(油川・函館方面)(奥羽本線、○東北本線) | 列車特定区間に格下げ | |
| 特定都区市内等 | 二大都市制度を151キロ以上に変更 |
この表を充実したいと思うので、改定日をご存知の読者の方がおられたら、ぜひ情報提供をお願いしたい。
旅客営業規則等
| [1] | 「旅客及び荷物運送規則」は、1958年10月1日に全面改訂され、現行のJR旅客営業規則の体系となった(旅客及び荷物運送規則 1958年10月1日施行)。 改訂以前の1952年・1957年の規則と1958年規則の目次構成の対比を旅規対比(1952vs1958)に示す。旧規則では、乗車券類の種類ごとに運賃・料金、様式、効力、検査・回収(改札・引渡し)等の項目を記載していた。 その後規則の名称は、「旅客及び荷物営業規則」、「旅客営業規則」と変化し、国鉄からJRに引き継がれたが、別表及び旅規対比(1958vs1987)に示すとおり条文構成は58年当時から大きく変化していない。 一方、内規が「旅客営業取扱基準規程」として施行されたのは、1967年4月1日であり、それ以前の「旅客及び荷物運送取扱細則」、「旅客及び荷物営業細則」とは、条文構成及び表現に若干の差異がある。 たとえば、規程110条の列車特定区間は1967年以前の細則では81条に、149条の特定分岐区間の区間外乗車は同じく115条に規定されていた。 | ||||||||
| [2] | 1920年以前にも、運賃特定制度という形で、経路特定と同様の制度が存在していたようである(日本国有鉄道百年史、第5巻)。
鉄道国有化により明治40年11月1日から全国の旅客運賃賃率が統一されたが、同時に旅客運賃の特定がいくつかの線区で行われた。
中野・御茶ノ水間の運賃が東京市電の運賃に合わせて特定された(その後電車区間の拡大にあわせて運賃特定区間も拡大)ほか、次のような区間で運賃が特定され、複数の経路の運賃が均一となった。
現在の東京・名古屋・大阪周辺の運賃特定区間と経路特定区間をあわせたような制度である。
|
||||||||
| [3] | 中外商業新報(1919年2月25日付)の記事は次の通り(原文のまま)。
東京大阪市内経由旅客の取扱方改正
この大阪市内の選択乗車区間は、1997年の規則に存在していた「東部市場以遠(平野方面)=大阪以遠(塚本・新大阪方面)(天王寺・大阪間、天王寺・JR難波間)」の前身である。鉄道院では二十四日附を以て来三月一日から実施すべき東京又は大阪市内経由旅客取扱方を左の通り改正したる旨を全国に通達した 東京市内 (イ)東海道本線大井町以西(大森蒲田方面)各駅と東北本線川口町以北(蕨浦和方面)又は常磐線三河島以東(南千住北千住方面)各駅との相互間に発着の旅客は山手線経由乗車券を以て品川万世橋間と上野日暮里間各駅とに於て乗降を希望するときは山手線を乗車せざる場合に限り左の区間は別に運賃を徴収せず(東海道本線と東北本線との相互間品川万世橋間上野赤羽間東海道本線と常磐線との相互間品川万世橋間上野日暮里間) (ロ)東北本線川口町以北各駅常磐線三河島以東各駅と中央本線大久保以西(東中野中野方面)各駅相互間に発着の旅客は山手線経由の乗車券を以て日暮里上野各駅と万世橋新宿間各駅とに於て乗降を希望するときは前同断(東北本線と中央本線との相互間赤羽上野間万世橋新宿間常磐線中央本線との相互間日暮里上野間万世橋新宿間) (ハ)東海道本線と中央本線各駅総武本線各駅と平井以東(小岩井、市川方面)各駅との相互間とに於て乗降を希望する時は(同断)(東海道本線と総武線と相互間両国橋亀井戸間品川万世橋間中央本線と総武本線と相互間両国橋亀井戸間新宿万世橋間東北本線と総武線の相互間両国橋亀井戸間日暮里上野間) (ニ)(略) 大阪方面 大阪市内関西本線平野以東(八尾柏原方面)各駅と東海道本線神崎以西(西宮方面)同以北(伊丹方面)同以南(尼ケ崎)各駅又は吹田以東(茨木高槻方面)各駅相互間発着の旅客城東線経由乗車券を以て港町天王寺間各駅と大阪駅との乗降希望者は城東線を乗車せざる場合に限り港町天王寺間は別に運賃を徴収せず |
||||||||
| [4] | 第49条と第53条は、それぞれ
第49条 東北本線仙台以南(長町方面)各駅ト同鹿島台以北(松山町方面)各駅トノ相互間ニ発着ノ旅客カ岩切松島間経由ノ乗車券ヲ以テ松島ヲ遊覧スルトキハ岩切松島間ヲ乗車セサル場合ニ限リ岩切塩竃間ハ別ニ旅客運賃ヲ収受セスシテ乗車セシムルモノトス
第53条 東海道本線大井町以西各駅ト総武本線平井以東(小岩方面)各駅トノ相互間ニ発着ノ旅客カ山手線及田端、北千住、亀戸経由ノ乗車券ヲ以テ品川万世橋間各駅ト両国橋亀戸間各駅トニ於テ乗降ヲ希望スルトキハ山手線及田端、北千住、亀戸間ヲ乗車セサル場合ニ限リ左ノ間ハ別ニ旅客運賃ヲ収受セスシテ乗車セシムルモノトス
品川万世橋間 両国橋亀戸間 旅規には掲載されていないが、第49条の選択乗車区間を略図で示すと次のとおり。 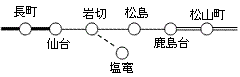 当時の東北本線は利府経由の旧線で現在の路線は塩竃までしか開通しておらず、仙山線と仙石線は未開業だった。また、第53、54、56及び57条の東海道本、中央本、東北本各線と総武本線との選択乗車の「田端、北千住、亀戸経由ノ乗車券」から、当時は新金貨物線で旅客営業が行われ、これを経由した乗車券が発売されていたことがわかる。 当時の東北本線は利府経由の旧線で現在の路線は塩竃までしか開通しておらず、仙山線と仙石線は未開業だった。また、第53、54、56及び57条の東海道本、中央本、東北本各線と総武本線との選択乗車の「田端、北千住、亀戸経由ノ乗車券」から、当時は新金貨物線で旅客営業が行われ、これを経由した乗車券が発売されていたことがわかる。 |
||||||||
| [5] | Cタイプの選択乗車が旅客にとってもっとも運賃上のメリットがあった。例えば、東海道本線で東北から関西方面に旅行する旅客が途中鎌倉に立ち寄るとき、選択乗車を利用すれば、大船・鎌倉間の別途乗車や大船・藤沢間の乗車放棄をせずに、1枚の乗車券の遠距離逓減運賃を享受できたのである。 | ||||||||
| [6] | 昭和22(1947)年6月23日付通報「上信越関係の急行列車設定に伴う特殊取扱いについて」で規定された。その後、1956年11月に大宮・秋田間が、57年4月福島・青森間が追加設定(福島・青森間は経路特定区間から降格)されたが、1958年10月の旅客制度全面改正時に、旅客及び荷物運送取扱細則第81条に規定された。 したがって、それ以前の「旅客及び荷物運送規則」及び「同取扱細則」には、列車特定区間制度の条項が存在しない。 | ||||||||
| [7] | 1965年3月1日のダイヤ改正で、名古屋・東和歌山(現和歌山)間に関西本線、同貨物支線(八尾・杉本町間。通称阪和貨物線)、阪和線経由の特急「あすか」が設定されたことによる。 この規定が存在することは、八尾・杉本町間には、営業キロが設定されており、阪和貨物線経由の乗車券が発売されていたことを意味している。 湘南新宿ラインの大崎・西大井間に営業キロが設定されず、品川経由の営業キロで運賃計算がされていることと好対照である。 なお、現在阪和貨物線を経由して運転される定期列車はないが、規程186条第1項第6号に、阪和貨物線経由の乗車券を発売する場合は「関西、(短絡)、阪和」の例により経路表示する」との規定が残されている(2009年4月1日廃止)。 | ||||||||
| [8] | 厳密にいえば、最短経路による運賃・料金計算の範囲は、従来70条太線区間通過とならなかった区間に拡大した。たとえば蘇我・浦和間は、70条「太線区間内にある駅発又は着」として、規則160条によるう回乗車のみが認められていたが、運賃・料金計算にも適用されるようになった。なお、70条2項に大井町、西大井以遠が規定されていないのは、総武線経由と京葉線経由の蘇我・東京間の営業キロが等しいため、いずれを経由しても最短経路の営業キロに差が出ないためだろう。 | ||||||||
| [9] | JR西日本は、2007年9月1日、岡山・広島地区にICカード乗車券ICOCAを導入した。このエリアには、岡山−総社−倉敷−岡山と三原−海田市−三原の二つの環状線区間が存在するが、山陽近郊区間は設定されなかった。ICOCAの約款に、最短経路の運賃引き落としとエリア内他経路の選択乗車の条項が規定され、ICカードと一般の乗車券によって取扱いが異なることになった。JR東海のTOICAエリアにも2010年3月13日から名古屋−岐阜−美濃太田−多治見−名古屋の環状線ができたが、名古屋近郊区間は設定されず、IC乗車券使用のときだけ最低廉運賃経路による運賃が減額されることとなった。JR九州は、2012年12月1日、SUGOCAの取扱いエリアを拡大したが、福岡近郊区間は変更しなかった。日田彦山線、久大本線、豊肥本線等はSUGOCAの「福岡・佐賀・大分・熊本エリア」に含まれていないが、これらの環状線を構成する路線は「運賃計算の特例に使用する路線」として、最低廉運賃の計算に使用される(JR九州:「SUGOCA」のカード内残額利用乗車の場合)。このように、JR東日本以外の各社は大都市近郊区間とICカード乗車券取扱区間を一致させていない。 | ||||||||
| [10] | みどりの窓口メーリングリスト(リンク切れ)に旧国鉄の首都圏本部、新幹線総局、静岡鉄道管理局、名古屋鉄道管理局、大阪鉄道管理局及び天王寺鉄道管理局制定の復乗特例規程が紹介されていた。 |
| 2005/05/04 | 誤記及び脱漏の訂正と注記の追加。 一部の誤記は読者の方からご指摘いただきました。 |
| 2005/05/10 | 表7の表記、表8の脱漏の訂正等 |
| 2005/05/17 | さらに表7の誤記(新川崎・西大井関連)及び表8の脱漏(大阪・新大阪)を訂正 |
| 2005/05/24 | 本文、表3、表4の誤記訂正。表5の内容追加(時刻表による推定)。 表7の新川崎関連の項目分割。表10を新設 |
| 2005/05/28 | 誤記の訂正(一部の誤記は読者の方からご指摘いただきました)。 「日本国有鉄道百年史」の記事から、「経路特定区間」及び「列車特定区間」の沿革・変遷を加筆(記事の存在については、読者の方からご教示を受けました)。 神戸大学附属図書館の新聞記事アーカイブから、脚注3の新聞記事を記載。 表3、表4、表5、表7の区間の表記法を規則・規程の条文表示から簡略化。 表10に追記 |
| 2005/05/30 | 誤記(総武快速線の開業時期)の訂正及びJR東西線関連規定の改正の反映(読者の方からご指摘いただきました)。 特定都区市内制度等に関連した乗り継ぎのための複乗規定の制定経緯、規程186条の八尾・杉本町間短絡線関連規定を追記(読者の方からご教示を受けました)。 表10の加筆(70条特定区間、新幹線関連) |
| 2005/06/30 | 「70条特定区間」に70条2項の規定を追記(本文及び脚注6(現脚注8))。 表10の加筆(東北・上越新幹線関連の新在別線、選択乗車区間) |
| 2005/09/05 | 別表1及び別表2を掲載し、脚注1に追記 |
| 2006/06/11 | 官報に記載された国鉄の旅規改訂の公示から、経路特定区間、選択乗車区間の推移を中心に表10を加筆。 これにより判明した、表3、表4の誤記を訂正。電車特定区間について加筆(官報のデータは読者の方から提供を受けました) |
| 2006/11/06 | 目次の設置。表4に選択乗車区間路線図(現行及び1958年)へのリンクを設定 |
| 2006/12/17 | 表10に選択乗車区間の改廃を追加 |
| 2007/09/22 | 表10の選択乗車区間の改廃を訂正・追加 |
| 2007/12/05 | 表3、表4、表7に、1947年8月、1950年5月、1953年3月時点の経路特定、選択乗車、特定分岐の各区間を追加。表10に追記(1958-87年の経路特定区間・選択乗車区間の変遷をすべて記載)。参考文献を追加。脚注1のデッドリンクを解消。脚注7(現脚注9)を挿入 |
| 2008/01/13 | 脚注1のリンクを変更 |
| 2008/04/12 | 2008年3月15日及び4月1日の旅規改訂を反映。表4に1989年10月1日時点の選択乗車区間を追加。図3に福岡・新潟近郊区間の地図を挿入。表10の選択乗車区間の改廃を追加。脚注1に「旅規ポータル」のリンクを追加 |
| 2008/06/03 | 国会図書館で閲覧した「旅客営業取扱基準規程」により、表5、表7、表8、表9を訂正追加。読者の情報により表5の注を追加。「分岐駅通過列車」に新在別線の西小倉・小倉間及び吉塚・博多間に関する条項を追記。複数の読者から得た「2002年12月1日改訂で選択乗車区間大幅削減」の情報をもとに表10に追記。列車特定区間の改廃がダイヤ改正時点と一致しないことから、日付が明確でないものを表10から削除。参考文献欄に国会図書館で閲覧した「旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程」を追加 |
| 2008/12/11 | 図3の大阪近郊区間変遷図の誤りを訂正(福知山線尼崎・宝塚間はJR東西線開業時に指定。兵庫・和田岬間は1998年12月指定)、表10に「福知山線尼崎・宝塚間」を追記 |
| 2008/12/31 | 表10に、2002/04/01付の選択乗車区間の廃止を追記。脚注8(現脚注10)を挿入 |
| 2009/03/14 | 2009年3月14日の旅規改訂(東京近郊区間の拡大、3選択乗車区間の廃止)を反映し、「選択乗車区間」を改稿、表4、図3を改訂、表10に追記 |
| 2009/06/01 | 表8を訂正(2006年3月18日廃止された分岐駅通過列車3区間を削除、規程第151条第3項適用区間を明示)、表10に追記(上記3区間の廃止を追記)。Cタイプの選択乗車区間の意義について、脚注4(現脚注5)を挿入。脚注6(現脚注7)に、阪和貨物線の廃止を追記 |
| 2010/04/19 | 大正11年の旅規に当たり初期の選択乗車について「157条選択乗車区間」の本文を再構成・加筆し、脚注4を挿入。2009年4月1日現行の規程に登場した特定都区市内発着の乗車券と併用する場合の他経路乗車の取扱いについて加筆。脚注9にJR東海のIC乗車券TOICAによる名古屋近郊の取扱について追記。表3、表4、表5、表7、表8のスタイルを変更(表中に年月行を挿入)。図3のスタイルを変更。参考文献に大正11年、平成21年の旅規を追加 |
| 2010/09/30 | 2010年3月13日の選択乗車区間の改定を反映し、表4を改訂、表10に追記。過去の選択乗車区間の変更を駅名改称等によるものも含めて表10に追加。表5の注記を改訂。表8の2006/04/01を2006/01/01に戻し、2009/04/01を追加(2006/04/01から変更なし)。表3、表4、表10の表記法を変更 |
| 2011/03/14 | 2011年3月12日の九州新幹線博多・新八代間開業に伴う選択乗車区間の新設により、表4を改訂、表10に追記。 |
| 2014/04/25 | 2014年4月1日の大都市近郊区間及び選択乗車区間の改定を反映し、「157条選択乗車区間」・「大都市近郊区間」を改稿、表4・図3を改訂、表10に追記。脚注9にJR九州SUGOCAの「運賃計算の特例に使用する路線」について追記。 |
| 2015/03/16 | 2014年10月1日の東京近郊区間拡大、2015年3月14日の仙台近郊区間拡大により、図3を変更し、「大都市近郊区間」に追記。3月14日の分岐駅通過列車及び折返し列車の変更を表8・表9に「15/03現行」として追加。これらの変更を表10に追記。 |
| 2015/06/05 | 2015年5月30日の仙石東北ライン運転開始に伴い設定された特定分岐区間、松島・高城町間を表7・表10に追加。図3の東京近郊区間の漏れ及び廃線区間を追加、福岡近郊区間の廃線駅名を追加、仙台近郊区間の駅名を訂正。 |
| 2016/05/10 | 2016年3月26日の小田栄駅開業に伴い、表7の表記を変更。北海道新幹線開業関連の分岐駅通過列車及び折返し列車の変更を表8・表9に「16/03現行」として追加。これらの変更を表10に追記。 |
| 2017/03/01 | 2017年3月4日の桂川駅廃止、寺家駅開業に伴う旅規改定にあわせて、表3、表4の表記を変更。このほか、漏れていたものを含めて、駅の開業等で表記が変更になった区間を表10に追記。 |
| 2018/04/11 | 「157条選択乗車区間」の中で記述していた、特定都区市内発着の乗車券との併用による他経路乗車について「その他の他経路乗車」として独立させ、規程第155条の条文を2011年現行版に変更。表10の2010年3月13日の項に東海道本線武蔵小杉駅開業に伴う表記の変更を追加 |
| 2019/03/15 | 2019年3月16日のおおさか東線延伸開業に伴う大阪市内駅の拡大及び区間外乗車を記載。「その他の他経路乗車」を改稿、デスクトップ鉄の雑記帳でコメントがあった規程第155条の仙石東北ラインを追加 |
| 2019/10/03 | 2019年3月16日のおおさか東線延伸開業に伴う大阪近郊区間の拡大を図3及び表10に記載(読者からメールで3月15日改訂の漏れの指摘を受けました) |
| 2019/11/30 | 本日の相鉄・JR連絡線開業に伴う経路特定区間の表記変更、東京近郊区間・横浜市内駅の拡大及び特定分岐区間の設定を表3、図3、表7及び表10に記載 |
| 2020/03/13 | 2020年3月14日の高輪ゲートウェイ駅開業に伴う経路特定区間、選択乗車区間、特定都区市内、特定分岐区間の表記変更及びSuica取扱範囲拡大に伴う東京近郊区間、仙台近郊区間の拡大を表3、表4、図3、表7及び表10に記載 |
| 2020/08/13 | 表1の規則86条条文を更新(2019年3月16日のおおさか東線開業に伴う本文の変更が未反映との指摘を受けました) |
| 2020/08/17 | 本文及び表1に引用した規則及び規程の条文を現行の条文に訂正。駅の開廃に伴う経路特定区間、選択乗車区間の表記の変更を表3、表4、表10に反映(読者から指摘を受けました) |
| 2021/06/22 | 列車特定区間が規程110条から規則70条の2に移行した、2021年5月27日の旅規改定を反映 |
| 2021/07/05 | 列車特定区間の規程110条から規則70条の2への移行に伴う改定漏れを訂正(読者から指摘を受けました) |
| 2022/03/12 | 駅の開廃に伴う経路特定区間の表記の変更を表3、表10に反映 |
| 2022/10/30 | 3月12日の特定分岐区間廃止(黒崎・折尾間)を表7に、9月23日の分岐駅通過列車設定(浦上・長崎間)を表8に反映。これらの変更を表10に追加(読者から指摘を受けました) |
| 2023/03/29 | 駅の開廃に伴う選択乗車区間の表記の変更を表4、表10に反映 |
| 2023/12/12 | 分岐駅通過列車の特例から大阪・新大阪間及び夜明・日田間が削除されていたことに気がついた。3月18日の大阪駅うめきた地下駅の開業と8月26日の日田彦山線添田・夜明間のBRT化によるものと思われる。これに伴い表8を改定、表10に追加した。また横浜市内発着の乗車券による鶴見・武蔵小杉間の市外乗車の記載が漏れていたことに気がつき、「その他の区間外・折り返し乗車制度」に加筆、表10に追加 |
| 2024/04/01 | 4月1日の旅規改定による区間外乗車の規程から規則への移行を記載し、規程から規則に移行したもの(2021年5月27日の移行を含む)について、新旧条文を対比。3月16日のハピラインふくいへの移管に伴い分岐駅通過列車から越前花堂・福井を削除 |
| 2025/04/23 | 3月16日の東京近郊区間拡大及び2023年8月28日の福岡近郊区間縮小に対応、図3を改定。3月15日の上所駅開業に伴う選択乗車区間の表記変更に対応。これらを表10に追加 |