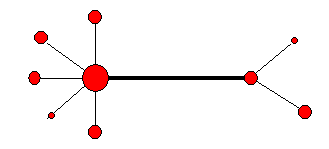 |
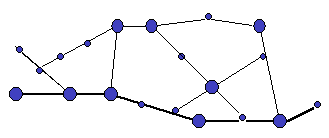 |
|
|
|
�l�b�g�ƃV���g���Ƃ����Ă��A�o�h�~���g���ł͂Ȃ��A�S���̘b�ł���B�ߔN�S�����q�A���ɂ����Ď��̂悤�Ȍ��ۂ��݂��邪�A�S���A���ɑ�����v�̕ω��ɑΉ����āA�������̏��i(���)���ω����Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�M�҂͂�����S�����q�A���̃l�b�g�^����V���g���^�ւ̕ω��Ƒ����Ă���B���̕ω����A�H���Ԃ𑖂��Ԑݒ�̕ω��ƃC���t���Ƃ��Ă̓S���l�b�g���[�N �̂ق���тƂ����A���݂ɊW���闼�ʂ��炽�ǂ�A�Ō�ɓS���̃l�b�g���[�N���������������l�������B
- ��������Ԃ��������B
- ���}���p�~����A�}�s�����}�Ɖ�����Ԃɕ������Ă������B
- �莞�Ԋu�^�s�̓��}�������Ԃ��������B
- ���G�ȕ�����������s����K���āA�O�K���ė�Ԃ��Ȃ��Ȃ����B
- ���}�̒�ԉw�̃p�^�[������Ԃɂ���ĕς��悤�ɂȂ����B
- ���}�̎��q����ԌQ���Ƃɐ�p���q�ɂȂ����B
- �H�ʓd�Ԃ��p�~����A�n���S��m���[���E�V��ʃV�X�e���ɂ�������B
| �l�b�g�^�ƃV���g���^ | |
|
|
�}�P�@�q��H���ƓS���H�� |
| ��Ԑݒ�̕ω� | |
|
|
�}�Q�@���q�A���V�F�A�̐���
�ʕ\�P�@�s��ʗ�Ԗ{������ �}�R�@���s�L���ʗ�Ԗ{������ϑ��s�L�� �}�S�@�}�s�u�݂��̂��v�̕����E���� |
| �S���l�b�g���[�N�̌`���Ƃق���� | |
|
|
�\�P�@�J�Ǝ����ʉc�ƃL��
�ʕ\�Q�@1972�N�ȍ~�̊J�ƘH�� �ʕ\�R�@1972�N�ȍ~�̔p�~�H�� |
| �S���l�b�g���[�N���������� | |
|
|
|
| �l�b�g���E�V���g�����N�\ | |
| �E�Q�l���� | |
| �E�� | �\�@�l�K���ė�� |
| �E�������� | |
�S���́A�n�\�ɐݒu���ꂽ�O������^�s����B�X�̘H���́A�ړ����v�����݂��镡���̒n�_����Ō���Ō��݂���A�����̘H�������ʏ�̓S���Ԃ��\������B��Ԃ́A�P���ȓ�n�_�Ԃ̉����ł͂Ȃ��A�|�C���g�łȂ����Ă���H����(���H���Ȃ��C����A���D�ɐݒu���ꂽ���[���ɂ��ړ���)�c���ɉ^�s���Ă���Ƃ����Ӗ��ŁA�l�b�g�^�A���Ƃ����邾�낤�B
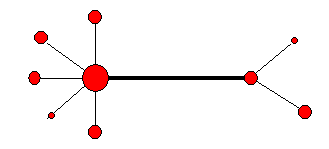 |
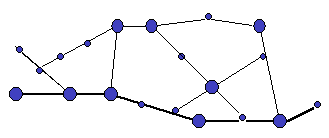 |
|
|
|
���ꂪ�S���ƍq��̗A���`�Ԃ̊�{�I�ȈႢ�ł���B�����[�I�Ɏ����̂́A�����\�̌`���ł���B�q���\��������`�̃A���t�@�x�b�g���ɏo���E����������\������uABC������ł���̂ɂ������A�u���b�h�V���E�S���ē������c�Ƃ���S�������\�́A�N�_����I�_�܂ł̗�Ԃ̐i�s�����ɂ����Ċe�w�̔����������ꗗ�\������[1]�B
�S���ɂ�����V���g���^�A���Ƃ́A�����ԌQ�͂قڈ��̘H��(���)�ɉ^�s����A����H��(���)���^�s�����Ԃ͂قڈ��̗�ԌQ�ł���A���`���ƒ�`����B���ɓI�ȃV���g���^�́A�|���S����V��ʃV�X�e���̂悤�ɁA��ԂƘH��(���)�Ƃ���Έ�ɑΉ����Ă���A���Ȃ킿�A��Ԃ͂˂ɂ��̘H��(���)�������^�s���A���̘H��(���)���^�s����͈̂��ނ̗�Ԃ� ���Ƃ����ł���B
����ɑ��ăl�b�g�^�Ƃ́A���Ă̍��S�����̓T�^��ł��邪�A����H��(���)�ɂ͈قȂ����^�C�v�̗�Ԃ��^�s���A�����Ԃ͕����̘H��(���)�ɂ܂������ĉ^�s�����A���`�Ԃł���B
�e�n���̓d�Ԃ́A�����_�Ń|�C���g��n��A�����̘H���ɂ܂������Đݒ肳�ꂽ���[�g�𑖂��Ă����B���̃��[�g�́A���ꂼ��̗��q�̈قȂ����ړ����v��S�̂Ƃ��Ė������悤�ɐݒ肳�ꂽ�B�S��Ԃ����Ƃ�����q�͑����Ȃ��������A1���Ԃ��Ƃ̋ψ�^�����������߁A�^�[�~�i���Ԃ��抷���Ȃ��Ɍ��ԃ��[�g����邱�Ƃ��K�v�������B�O�����~�݂��ꂽ���H�𑖂�o�X�̂悤�Ȃ��̂ł���������A�s�d�̌n���̑����́A�p�~��s�o�X�H���Ɍp�����ꂽ�B�܂��ɘH���Ԃ��c���ɑ���l�b�g�^�A���̓T�^�ł������B
����c�c�E�s�c�܂߂�12�H��(�n��)���铌���̒n���S�́A�������L��295.9�L��(�s��ʋǂ���2�펖�Ǝ҂Ƃ��ĉ^�s����ڍ��|�������֊Ԃ��� �܂�)�Ƃ����Ő����̓s�d�ȏ�̘H���Ԃ�L���Ă��邪�A�e�n������p�̐��H��L���A�ߍx�̒n����ɏ�����邱�Ƃ͂����Ă��A���̒n���S�H���ɏ������ ���Ƃ͂Ȃ��A�N�I�_�Ԃ�܂�Ԃ������̃V���g���^�A�����s���Ă���[2]�B
�ߔN���[���b�p�𒆐S�ɔ��B���Ă��邢����LRT���A�]���̘H�ʓd�ԂƈقȂ��{�I�ɃV���g���^�ł���B�H���Ɗe�n���̉^�s��ԂƂ́A�n���S�̂悤�ɂقڈ�Έ�̑Ή��ƂȂ��Ă���B�^���̌n�́A1���Ԍ^�ł��邪�A�]�[���^�������̗p���A�������ԓ��ł���Ώ抷�����R�ł���B�Ȃ��A�x���M�[�̃u�����b�Z���ɂ́A300���s�s�Ƃ��Ă͒������A�n���S�ƂƂ��ɏ]���^���H�ʓd�Ԗ����������Ă���B�s�S���ɂ͒n���̐�p�O��(�v�����g��)��݂��Ă��邪�A�e�n���͘H�����܂������ďc���ɉ^�s����A���Ă̓����s�d�Ɠ��l�̃l�b�g�^�A�����s���Ă���B
���S�́A�V�������J�Ƃ���1964�N�x�ɐԎ��ɓ]�������B���̌���Ԏ��z�͑��傷�����ŁA1987�N�̕������c���ɂ�����B���S���v�����c���ɂƂǂ܂炸�A���q��Ђ̕����ɂ܂Ŏ������w�i�ɂ́A�A�����v�̍\���ω��ɂ��A�S���ꗥ�ł̑Ή�������Ȃ������Ƃ�����B���q��Ђ̕����ɂ͂��܂��܂ȈĂ����������A���q�����̎��Ԃ��l�����A�ŏI�I��6�����ƂȂ����B���̊e���q��Ђ̃e���g���[�́A�{�B�O�Ђ�98���A�O����Ђ�95-99%�̗��q���������Г��Ŋ�������Ƃ����z��̂��Ƃɒ�߂�ꂽ[3]�B
�A���T�[�r�X�����҂Ƃ��Ă̓S�����Ǝ҂́A�A�����v�̕ω��ɑΉ������A���`�Ԃ�ݒ肹��������Ȃ��B���ꂪ�A�S���A���ɂ�����l�b�g�^����V���g���^�ւ̕ω��ƂȂ����B�e�H���E�e��Ԃ��ʓI�Ȏ��v�����A��n�_�Ԃ��������鎩�Ȋ����I�A���A���Ȃ킿�V���g���^�A���ɂȂ炴������Ȃ��̂ł���[4]�B���c�����ꂽJR�e�ЂƂ��A�������̓s�s�ԗA���ɓ��}�𓊓�����ƂƂ��ɁA��s�s�ߍx�H���𒆐S�ɉw�̐V�݂��Ԃ̃t���[�N�G���g���ɂ��A�����v�̌@��N�����ɂƂ߂�[5]�B
�����ł́A���B���Ԃ̒Z�k�ƂƂ��ɒ莞�Ԋu�ł̃t���[�N�G���g�^�s���d�v�ł���B���S�́A1972�N10���̃_�C�������ŁA���̃R���Z�v�g�m�ɂ����uL���}���ݒ肵���B
1964�N10���ɊJ�Ƃ������C���V�����́A�S���̃V���g�����Ɍ����āA�ЂƂ̃G�|�b�N�ƂȂ����B���{�ōő�̓s�s�ԗ��q�A�����v�����݂��铌�C���ɁA�ݗ����̓S���Ԃ���Ɨ������W���K�̍����S����V�݂��A�����|�V���Ԃ��������邾���̃V���g���^�A�����s�����B�u�Ђ��裂���s���Ƌ���_�Ԃ̈ړ����v�����ƂƂ��ɁA���Ȑ��ւ̗��q���A�V���w�����̏��p����Ԃ�ݒ肵�Ď�荞�B�܂��u�����ܣ�ɂ���đ����m�x���g�̐l���f���n�тɓ_�݂��钆�j�s�s�Ԃ̒������A����S�����̂ł���B
���͕��U�����̐V�����̃v���g�^�C�v�ƂȂ����̂́A1958�N10���^�s���J�n����151�n�d�ԓ��}�u�����ܣ�ł������B�����ɁA�@�֎Ԍ����̋q�ԗ�Ԃł��邪�A�Œ�Ґ��̐Q����}�u������������o�ꂵ���B������ėp�^����A�ʌ^�̗�Ԑݒ�̂͂���Ƃ����邾�낤�B�u���������v������I�������̂́A����[��ɒʉ߂���_�C���Ƃ��āA�֓��ƍL���Ȑ��̗A�����v�������Ƃɓ����������Ƃł���B����ȑO�ɉ@�d�A�Ȑ��d�ԁA���d�A�d�d�Ƒ�����s�s���̒ʋΓd�Ԃ��V���g�������Ă����B
�ʕ\1-1����A��Ԃ̉^�s�������N���o��ɂ�ĒZ���Ȃ��Ă������Ƃ��킩��B�ėp�^����ʌ^�ւ̗�Ԑݒ�̕ω��́A��������Ԃ����������A�t���[�N�G���g�ɓ�n�_�Ԃ��������钆�Z������Ԃ��������Ƃ�����B��������Ԃ̏I���͕��ʗ�Ԃɂ͂��܂�A��s�Q����}�ɋy�B�q��^���̑��ΓI�ቿ�i���ƍ������H�̖�s�o�X�ɂ���Ă��̌X���͂����������܂����B
1956�N�ɂ́A�����E��i�Ԃ𑖂镁�ʗ�Ԃ��������B1961�N�A���C�����̍Œ��������ʗ�Ԃ͕P�H�s143���ƂȂ�B65�N10�������ő��s �ƂȂ�A68�N10���A143M�Ɠd�ԉ�������Z�ԍ�s�ƂȂ����B��69�N�̉����ő�_�s�ƂȂ�(���̌��Ԕԍ����ς��A���݂́u���[�����C�g�Ȃ���v�ƂȂ�)�B1956�N�ɂ́A��B�ɒ��ʂ����Ԃ�9�{���������A���X�Ɍ���A2006�N3�������łP�{�����ɂȂ����B
����ł́A1956�N�ɂ͏�씭�X�s�̕��ʗ�Ԃ����������A68�N10�������Ő��s�ƂȂ����B���|����Ԃ�ʉ߂��镁�ʗ�ԂŁA�Œ������𑖍s����͍̂����s�ɂȂ��Ă��܂����i2005�N7���ɂ͂��킫�s��10�{���������A�N�����Ŕp�~�ƂȂ����j�B���}��}�s���܂߂��X�s�̗�Ԃ́A61�N��8�{���珙�X�Ɍ����Ă䂫�A93�N12���̉����Łu�䂤�Â�v���Վ���ԂƂȂ�A94�N12���Ɋ��S�ɔp�~����[���ƂȂ����B
�}3�ɁA���s�L���ʗ�Ԗ{���ƕ��ϑ��s�L���̐��ڂ��O���t�Ŏ����B
��Ԃ̕��ϑ��s�����́A1956�N����2007�N�̊ԂɁA���C�����ł�438�L������126�L���ɁA����ł�340�L������128�L���ɁA���ꂼ��啝�Ɍ�������[6]�B
���C�����͐V�����̊J��(1964�N)�ɂ���Ē������D����Ԃ��V�t�g��������A1961�N��68�N�̊Ԃɕ��ϑ��s�������傫���Z�k�����͓̂��R�� ����s���ł���B�������A1956�N����61�N�ւ̐��ڋy��1968�N�ȍ~�̐��ڂ����Ă��A�Z�k�X���͈�т��Ă���B����͕��s����V���������݂��Ȃ����A���Ȗk�ւ̒��ʗ�Ԃ̌����E�p�~�́A1982�N�̓��k�V�����J�Ƃ̉e�����Ă���B������̏ۂ��Ă��A��Ԃ̉^�s�����̒Z�k���X���́A�Ƃ��Ɉ�錧�암����s���̒ʋΌ��ɑg�ݍ��܂ꂽ���Ƃɂ���Č����ł���B
�ꕔ�̐Q����}�������A�S��Ԃ�ʂ��Ē�������Ԃɏ�闷�q�͏��Ȃ������B�Ƃ��ɒ��s�̒�������Ԃł́A��v�w�ł͂قƂ�ǂ̏�q���~��A���炽�ɏ�Ԃ���q�Ɠ���ւ���Ă��܂��B�P�Ɉ�̗�Ԃ������������^�s���Ă���Ƃ��������ł����āA��Ԃ̐��i�͋�Ԃ��ƂɈقȂ��Ă����B��������Ԃ̉^�s��Ԃ����q�̎��v�ɂ��킹�ĕ������ꂽ�킯�ŁA�ėp�^�̗�Ԑݒ肩��ʓI���v�������߂̕ω��Ƃ����邾�낤�B
���g���l���Ɛ��ˑ勴�̊����ɂ���āA�k�C���ƍ��쌧����������̒��ʗ�ԂŌ����悤�ɂȂ������A����A�O�d�A�ޗǁA�a�̎R�A����A�{��A�������e���ւ̒��ʗ�Ԃ͔p�~���ꂽ�B
���H�e�ʂ��s�����Ă��钆�ŁA�S���e�n�ɒ��ʂ����Ԃ�ݒ肷�邽�߂ɂ́A�����ƕ������K�{�������B���S����́A������������J��Ԃ���K���ĎO�K���ė�ԂƂ����̂��������Ȃ������B�ʕ\1�Ɍ���悤�ɁA1968�N�ɂ͓��C�����Ə���ɎO�K���ė�Ԃ��������B�������I�ɏ��Y�E�ޗǁE���H�s�̋}�s�u�I�Ɂv�Ə�씭�q�A�{�ÁA�O�O�s�̋}�s�u�݂��̂��v�ł���B
�u�݂��̂��v�́A1965�N10���̃_�C�������Őݒ肳�ꂽ��씭�q�A���A�{�ÁA��k�s�̎l�K����[7]�̋}�s�u��1�݂��̂�������v�̌�p��Ԃł��������A�l�K���Ď���́u��1�݂��̂�������v�ȏ�ɁA���G�ȕ����E�������s�����B�����}3�Ɏ����B
�}�S�@�}�s�u�݂��̂��v�̕����E����
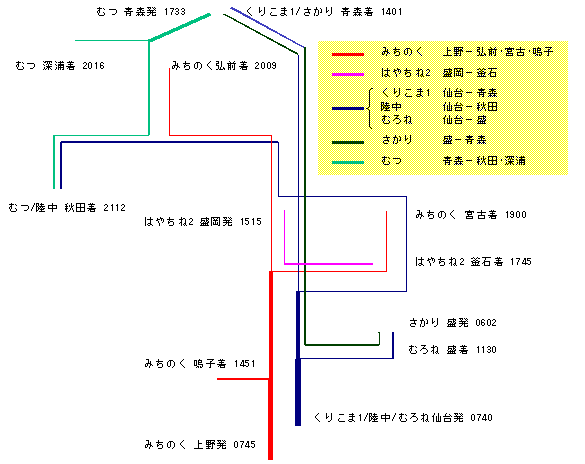
��݂��̂���́A�����c�Ŗq�s������K���ĂɂȂ�A�Ԋ��ŋ{�Ís������B�{�Ís�ɂ͐������̢�͂₿�˂Q������܂ŕ��������B������k����k�シ��O�O�s�́A�����ŏH�c�s�̋}�s�����������A�Ăѓ�K���ĂɂȂ�B�D������ԗ��ɓ���A��قŢ����������A�P�ƂōO�O�ɓ�������B�H�c�s�u�����v�ɂ͐X���́u�ނv�����������B��݂��̂���ɂ���ފe��Ԃ̕����E�������}�Ɍ���悤�ɕ��G�ł���B
�����E�����̗e�Ղȃf�B�[�[���J�[�̓�������g���āA����ȃ_�C����ݒ肵���̂ł���B�������A�l�͎����ŏ�芷������̂�����A���ʂ��邱�Ƃ͕K�{�Ƃ͂����Ȃ��̂��B��Ԃ����ʂ���H�����������ꂽ���ʁA�����E���������Ԃ͌������A���݂�2��ȏ�̕����E�����������Ԃ͂Ȃ�[8]�B
���S����̎��q�́A���}�^�A�}�s�^�A�ߍx�^�A�ʋΌ^��4�敪�ŁA�S���I�ɂقړ���K�i�̎��q���g���Ă����B�H���ɂ��Ⴂ�́A101�n��103�n�ʋΌ^�d�Ԃ̓h�F���炢�ł������B���}�^���q�́A�����E���d�Ԃƃf�B�[�[���J�[�̍��͂����Ă��A�R���f�[�V�����͓����ŁA�h�F�������鍑�S�F�����������BJR�ɂȂ��āA�e�Ђ͋����ēƎ��̐V�^���q��a���������BJR�ŏ��̓��}���q�́A1988�N3���̃_�C�������ŁAJR��B�̓��}��L����Ɏg�p���ꂽ783�n��n�C�p�[�T���[����ł���BJR�����{�́A1989�N3����651�n��X�[�p�[�Ђ�����A1989�N4����251�n��X�[�p�[�r���[�x��q��Ɗe���ɓ��}��V�݂��邲�Ƃɐ�p���q�𓊓������B
�J�Ɠ����A�V���|���l�Ԃ̘H���͓��C�������\������ꕔ�Ƃ͑z�肳��Ă��炸�A���R���Ɍ��݂����\��̓����|���s�ԘH���̎x���Ƃ��Ă̈ʒu�t���ł������B�����́A�펞�ɍU������₷���C�݉���������Đݒu����Ƃ����R���̎咣����ł���B���ꂪ���C���o�R�ɕύX���ꂽ�̂́A1886�N7���ł���B ����܂łɒ��R���������\�����镔��(�M�c�|�ؑ]��A��_�|���l�A�V���|�_�ˊ�)�͊J�Ƃ��Ă������A���̌���ɂ�艡�l�|�M�c�Ԃ����H����A�������珇�����L���i�݁A1889�N�V���|�_�ˊԂ��S�ʂ���B1934�N�O�߃g���l���̊J�ʂɂ��]���̌�a��o�R���猻�݂̘H���ƂȂ����B
����́A1889�N���˓S�����F���|���ˊԂ��A1896�N12�����{�S�����c�[�|�y�Y�Ԃ��J�Ƃ����B���̌�@1898�N8���܂łɊ���܂őS���� �J�Ƃ���B1905�N4���ɂ͓��闢�|�O�͓��Ԃ̘H�����J�ʂ��A��Ԃ͏�씭�ƂȂ�B
���炽�߂č��哱�ɂ��S�����݂��߂��̂��A1892�N�̑�1���S���~�ݖ@�ł������B���̖@���́A�k�C�������������𒆐S�Ƃ���33�H���̕~�݂���(�k�C���̓S�����݂ɂ��ẮA�ʓr�k�C���S���~�ݖ@�𐧒�)�A���̂����}��v�����1�����Ƃ��āA��Ƃ��ČR���I�ϓ_����9�H�����I�肳��A1893�N4���̖k�����A���H�����珇�����H���ꂽ�B
����ɓS���o�u���̕���Ŕ�����]���{�ƂƁA���{�ɂ�铝���̕K�v����F�������R���̎v�f����v���āA1906�N�S�����L�@�����z�����B���@�́A���ʉ^���m�p�j���X���S���n���e���m���L�g�X�A�A�V��n���m��ʃ��ړI�g�X���S���n�R�m�����j�A���Y��ƒ�߁A����ɂ��ƂÂ�1906�N10������1907�N9���ɂ����āA���{�S��(�����k��)��R�z�S��(���R�z��)�Ȃ�17�̓S����Ђ̖�4,800�L���̘H�����������ꂽ[9]�B
�������]�����𐄐i���鐭�F����t�́A1922�N�A�����S���~�ݖ@�𐧒肵���B���@�̂��Ƃłقڊ������������S���Ԃ�⊮����x��149�H���A10,218�L���̌��݂��߂����̂ł���A�����Ƃ̉�c���S�ɂ��H���Ԃ̊g�[���i��[10]�B
1959�N7���A�����n�Ƃ��Ă͍Ō�ɋI�������S�ʂ��A���{�̓S���l�b�g���[�N����������B�������A�S���J�Ƃ���2���I�ڂɓ�����1972�N����ߖڂƂ��āA���{�̓S���l�b�g���[�N�͂ق���юn�߂�B
| �@ | �T(1872-1905) | �U(1906-1938) | �V(1939-1971) | �W(1972-2007) | ���v | |||||
| �@��� | 7,586.2 | 99.6% | 12863.4 | 97.7% | 1,621.3 | 61.2% | 1,660.6 | 39.2% | 23,731.5 | 85.8% |
| �@�ݕ� | 16.4 | 0.2% | 126.7 | 1.0% | 190.0 | 7.2% | 76.8 | 1.8% | 409.9 | 1.5% |
| �@�H�� | 15.1 | 0.2% | 137.3 | 1.0% | 26.9 | 1.0% | 1.4 | 0.0% | 180.7 | 0.7% |
| �l�b�g�^�v | 7,618.1 | 100.0% | 13,127.4 | 99.7% | 1,838.2 | 69.4% | 1,838.8 | 41.1% | 24,322.1 | 87.9% |
| �@�V���� | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 552.6 | 20.9% | 1,834.5 | 43.3% | 2,387.1 | 8.6% |
| �@�n���S | 0.0 | 0.0% | 21.8 | 0.2% | 218.1 | 8.2% | 468.6 | 11.1% | 708.5 | 2.6% |
| �@�|�� | 0.0 | 0.0% | 13.8 | 0.1% | 7.9 | 0.3% | 0.8 | 0.0% | 22.5 | 0.1% |
| �@���m���[�� | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 19.9 | 0.8% | 93.2 | 2.2% | 113.1 | 0.4% |
| �@�V��� | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.6 | 0.2% | 95.4 | 2.3% | 102.0 | 0.4% |
| �@���O�� | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.1 | 0.2% | 3.7 | 0.1% | 9.8 | 0.0% |
| ��l�b�g�^�v | 0.0 | 0.0% | 35.6 | 0.3% | 811.2 | 30.6% | 2,496.2 | 58.9% | 3,343.0 | 12.1% |
| ���v | 7,617.7 | 100.0% | 13,163.0 | 100.0% | 2,649.4 | 100.0% | 4,235.0 | 100.0% | 27,665.1 | 100.0% |
| 27.5% | 47.6% | 9.6% | 15.3% | 100.0% | ||||||
| * | �c�ƃL���́A���H�̏��L��(��1��A��3�펖�Ǝ�)����Ɍv�サ�A�����̎��� �҂��^�s���Ă����Ԃ��e���Ǝ҂��Ƃɏd���v�シ�邱�Ƃ͂��Ȃ�(��}�A��_�A�R�z��������H���^�s���Ă���_�ˍ����S�����́A�_�ˍ����S����{�Ōv��)�B�A���A���c�����S������3�펖�Ǝ҂ł����Ԃ́A�O�Ԃ��قȂ�P���̐��H��JR�����{�Ƌ������ʂɎg�p���Ă���̂ŁA���ꂼ��Ɍv�サ�Ă���B | |||||||||
| ** | �J�ƌ���H�̕t���ւ�����������Ԃ́A���ׂē����̊J�Ɠ��ɂ�����B�w�S���v���x�L�ڂ̊J�Ɠ��́A���C�����E�V���|���s�ԁA�������E�����|�V���ԓ��͐V���̊J�Ɠ����L�ڂ��A�k�����E�։�|�����ԁA���k���E����|�X�ԓ��͋����̊J�Ɠ����L�ڂ��Ă��� | |||||||||
��T���Ɍ��݂��ꂽ�H���́A���݂�JR�̊�������̂ł���A���R�Ȃ��炷�ׂĂ��l�b�g�^�H���ł������B��U���ɂȂ�ƁAJR�̏������Ƒ�莄�S�̘H���ɉ����āA����(�����)�E���(�䓰�ؐ�)�̒n���S��P�[�u���J�[�Ȃǔ�l�b�g�^�H�����J�Ƃ������A���̔䗦�͂킸��0.3%�ł������B�V�����A���m���[����V��ʃV�X�e�����́A�����̓S���H���Ԃɏ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��V���g���^�̘H�����{�i�I�Ɍ��݂��ꂽ�̂́A��V���̏I�Ղ���ł���B
��W���ɊJ�Ƃ����H���́A��l�b�g�^���ߔ����߂�B�R�z�A���k�A��z�A�k���A��B�Ə����J�Ƃ����V������40%���ł���A�����Ēn���S��10%����B���m���[����V��ʃV�X�e���ȂǁA���V���g���^�̋O���n��ʋ@�ւ�4%������B
��W���ɊJ�Ƃ������q�H�����ʕ\�Q�Ɏ����B�l�b�g�^�ɕ��ނ������S�EJR�̈�ʘH���ł��A�S���S���l�b�g���[�N���ŏI�I�Ɋ������������g���l��(�Ìy�C����)�A���ˑ勴(�{�l���]��)��2�H���������A��������A���t���A�鋞�����̑�s�s���̒ʋΘH���̌��݂���̂ł������B
�ݗ��^�̐V���ɂ́A�ق��ɁA���c��`(JR���E�����A1991�N3��)�A�V���`(JR�k�A1992�N7��)�A����`(JR���E��C�A1994�N6��)�A�{���`(JR��A1996�N7��)�A�H�c��`(���}�A1998�N11��)�A�������ۋ�`(���S�A2005�N1��)�Ƃ������ŊJ�Ƃ�����`�A����������B���c��`�Ɗ���`�ł́A��3�펖�Ǝ҂����L����H����JR�Ǝ��S���Ƃ��ɑ�2�펖�Ǝ҂Ƃ��ĉ^�s�����B������A�S�����q��A���Ƃ̕⊮�W�����o���A�s�S�Ƌ�`�Ԃ̎��v����荞�ރV���g���^�A�����J�n�����Ƃ����_�Œ��ڂ��ׂ����낤�B�܂�������`�ɂ́A1993�N3�������s�c�n���S�������ꂽ�B�܂��A2004�N12���J�Ƃ̉H�c��`��2�^�[�~�i���ɂ͓������m���[�������L���A2002�N2���̊J�Ƃ̐_�ˋ�`�́A�_�ː_��ʂ������ꂽ�B
�p�~�H����9%��H�ʓd�Ԃ���߂�B�s�s���œT�^�I�ȃl�b�g�^�A�����s���Ă����Z��s�s�̘H�ʓd�Ԃ́A1977�N10���̋��s�s�d���Ō�ɁA�s�d�r������c���Ă��ׂĔp�~���ꂽ�B
1981�N3���̍��S�o�c�Č����i���ʑ[�u�@�̎{�s�ɂ��A����n����ʘH���Ɏw�肳�ꂽ�H�����������Ŕp�~���ꂽ[11]�B�p�~�H���́A�n���̖Ӓ��������łȂ��A�Ƃ��ɖk�C���𒆐S�Ƃ��āA����{���Ȃǃl�b�g���[�N(���)���\�����銲���n�ɂ��y�B�������S���O�Z�N�^�[�Ȃǂɓ]���n���ꂽ�H�����A1998�N�̍O��S���̋����ΐ�����ɁA���k��ʁA�̂ƓS���A�k�C�����ق������S���A�_���S���Ɣp�~���������B
�܂��V�����̊J�ƂɂƂ��Ȃ����s�ݗ����̔p�~�܂��͌o�c�ڊǂɂ���āA����|�m��ԁA�����|���ˊԋy�є���|����Ԃ�JR�̃l�b�g���[�N����O�ꂽ�B
���̂悤�ɁA�H���̔p�~�ƐV�݂Ƃ����݂Ɋ֘A���ēS���l�b�g���[�N���ق����ł䂭�̂����A���̉ߒ��œ����I�Ȏ��Ԃ�������B
�����Ȃ��Ƃ��A�ݗ�����p�~���邩�AJR����o�c�����������链�Ȃ��قǎ��v�������߂Ȃ������V�������t���K�i�ŐV�݂���K�v�͂Ȃ��B�O���������t���[�Q�[�W�g���C���ɂ��V�ݒ��ʕ����Ō��݂��A���ݔ��}������ƂƂ��ɁA�ݗ����̃l�b�g���[�N�����������ׂ��ł͂Ȃ����B�����V�����͊J�Ƃ������A�V�����̉w���ł��Ȃ����������∢�v���́A�ݗ����̑�R�Z�N�^�[�ڊǂŁA���E����┎����������ɒ��ʂ���ݗ����̓��}���Ȃ��Ȃ����B�s���́A�����V�����̊J�Ƃ��ǂ��v���Ă���̂��낤���B
LRT�̃��m���[����V��ʃV�X�e���ɑ��郁���b�g�́A���̓_����������B
���{�Ń��m���[���E�V��ʃV�X�e�������y�����̂́A���H�Ƃ̈�̐����Ƃ����ϓ_���瓹�H�����������Ƃ��鋌���ݏȂ̕⏕�������݂��邽�߂ł���B��s�s���m���[�����݂̂��߂̓��H�������Ƃɑ���⏕���x��Ɋ�A�n�������c�̂܂��͑�O�Z�N�^�[�����m���[���E�V��ʃV�X�e���H��ɕ~�݂���ɂ������āA�C���t������(�x�������)�̌��݂ɑ��S���ݔ��59.9%�����x�Ƃ���⏕�����o��B���������H��ɕ~�݂���O���ł���LRT�̐����ɂ͂��̂悤�ȕ⏕���͑��݂��Ȃ��B�����I��ʐ���Ɋ�A�s�s�̌�����ʐ����ɑ�����I�⏕�̎d�g�݂��K�v�ł���[13]�B
�܂��́A���ꎖ�Ǝ҂̘H���Ԃœ���z�[���ł̑Ζʏ�芷���̐��i���K�v���낤[14]�B����ɂ���āA�ɋ}�����^�]�ƂƂ��ɕ���w�ɂ�������ݒ��ʉ^�]���\�ƂȂ�A�S���̗��������シ�邱�Ƃ��ł���B
���S���C���E�R�z���̑��Á|�����ΊԂ́A1937�N�̍�_�Ԃ̕��X�������ȍ~�A��Ԑ��Ɠd�Ԑ��̕����ʕ��X���^�]���s���Ă���B�����̒�ԉw�Ŋe���Ԃ��������ԂɁA����z�[���ŏ�芷���邱�Ƃ��ł���B��Ԃɂ���Ă͗�Ԑ��E�d�Ԑ����A�N���o�`�b�N�ɏ��ڂ�_�C���ݒ�ɂ�蓞�B���Ԃ�Z�k���Ă���B��s���ł́A1956�N11���i��|�c�[�ԂŎR����E���l���k���d�ԂX���������Ƃ��A�����ʉ^�]�Ƃ����B�܂��A����ȑO����䒃�m����V�h�ł̓���z�[���Ζʏ抷���s���Ă����B
1960�N��㔼����70�N�㏉�߂ɍs���������颌ܕ��ʍ����̕��X����[15]�ł́A��������������Ɗɍs���̘H���ʕ��X���Ƃ��A�����ʂƂ��Ȃ������B����������ɍs���ւ̏抷���ʃz�[���Ȃ̂ŁA�K�i����~���א�����n������n��K�v������B����w�⏼�ˉw�̂悤�ɓ����s����Ɍ�������Ԃ̔����z�[������������� �́A�܂������s�ւł���B�����̉w�Ő��H�̗��̌�����݂���Ε����ʉ^�]���\�ƂȂ�B����X�����ݎ��ɍs���A�ŏ��̔�p�ł��̂ł���B�ԉH�w�̉������A�����ʂ��̗p����D�@�������̂����A�H���ʂ̂܂܂ł���B�ܕ��ʍ��ŕ��X�������ꂽ��ԂŁA����z�[���Ζʏ抷���\�ƂȂ����̂́A�˒ˉw�ł̓��C�����d�ԂƉ��{����d�Ԃ̏�芷�������ł���B
����w�ł́AJR�������̊J�Ƃɂ������ē��w�ōs�������ݒ��ʉ^�]�y���ׂ����낤�B���w�̊ɍs�����z�[���ɂ́A���C�����_�˕��ʂ���̓d�Ԃƕ��m�R����˕��ʂ���̓d�Ԃ��������A���ꂼ�ꂪ�قڌ��݂ɓ��C�������s���ʂ�JR�������o�R�В������ʂɌ����ĉ^�]�����B���m�{����l����Ɍ��������q�́A�ق�50%�̊m���Œ��ʓd�Ԃ����p�ł��A���ʂ��Ȃ��d�Ԃɏ�Ԃ����Ƃ������w�̃z�[���őΖʏ�芷�����ł���̂�[16]�B��s���ł́A�c�c�L�y �����̏��|�����Řa���s�Ɛ���������̓d�Ԃ�V�؏�s�ƐV���r�܍s�ɐU�蕪���Ă���B����́A�V����13�����Ƃ��ďa�J�܂ʼn�������A���}�������Ə������悤�ɂȂ�A����ɗ����������B
���ݒ��ʕ����́A���t���̊J�Ǝ��ɑh��w�Ŏ������ׂ��ł������B�h��|��t�݂ȂƁE�{��t�ԂƑh��|����E�l��Ԃ̗�Ԗ{���͂قڈ�v����B���t���̗�Ԃ�h��܂�Ԃ��ɂ����A��t���ʂ���̗�Ԃƌ��݂ɊO�[���E���[���ɐU�蕪�����ʂ�����̂ł���B�������A���t���̃z�[���͕ʂɐݒu���Ă��܂����B�O�[�E���[�����狞�t���ւ̏�芷���͌א�����n��Ȃ���Ȃ炸�A�ڑ��_�C���̐ݒ�������A����߂ĕs�ւł���B�Ȃ��A2007�N3���̃_�C�������ŁA�[���̃��b�V���������������t������O�[����[���ւ̒��ʗ�Ԃ������ݒ肳�ꂽ�B
���ݒ��ʕ���������P�[�X�ł��A���Ȃ��Ƃ�����z�[���̑Ζʏ抷�͎��{���ׂ��ł���B�c�c�́A��k���̊J�Ǝ��ɔѓc���w���s���J�w�̃z�[����ԍ〈���̂悤�ɓ�K���Ăɂ��āA����z�[���ŗL�y�����Ƃ̑Ζʏ抷���ł���悤�ɂ��ׂ��ł������B
���S�́A���J���牡�l�H���2.7km�̒Z������V�݂��AJR���C���ݕ������o�R���ďÓ�V�h���C���̐V�h�w�ɏ������v��ł���B����ɁA���l�H��V���l�o�R���g�܂Ő��H���������A���}�������o�R�����n���S���s�S���ɁA�ڍ����o�R�����n���S��k���E��ʍ����S������ѓs�c�n���S�O�c���ɁA���ꂼ�꒼�ʂ���v�������BJR�������2015�N�A���}�������2019�N�̊J�Ƃ�ڎw���Ă���A���ꂼ��A�s�s�S�������֑��i�@�Ɋ�Â��u���B�����㎖�ƔF��v�̔F�����[17]�B
2006�N4���A�x�R���C�g���[�����J�Ƃ����B�k���V�����J�Ǝ��Ɍo�c��������Ƃ��Ă���k�����̎x���̂����A�x�R�`�����O�Z�N�^�[�Ɉڊǂ��A�s�X�n�ɘH�ʂ̐V�������݂���LRT���������̂ł���B�����́A�d���̈Ⴂ�Ȃlj������ׂ��_�͂��邪�A�x�R�n���S���s�����Ƃ̏�����ɂ��s�S���ʂ��s���ׂ����낤�B�g�����ɂ��Ă����l�̌v�悪���邪�A��������R�d�O�Ƃ̒��ʂɂ��A�����̌��オ�}���B
2007�N3���APASMO���f�r���[���AJR�O���[�v��Suica�Ƃ̑��ݎg�p���J�n���ꂽ�B��s����JR�E���S�E���c��ʂ�1���̃J�[�h�ŃV�[�����X�ɏ��p����悤�ɂȂ����B���̂悤�ȁA�n�[�h�ʥ�\�t�g�ʂł̐ڑ��̃V�[�����X���ɂ���āA�S���l�b�g���[�N�̗��������シ��̂ł���B
| ���t | N/S | ���� |
| 1869(M 2)/11/10 | N | �S�����݂̕_�c����(�����|���s�Ԃ̊����y�ѓ����|���l�ԁA���s�|�_�ˊԁA���i�Δȁ|�։�Ԃ̂R�x���̌��� �v��) |
| 1872(M 5)/06/12 | S | �i��|���l�ԉ��c�ƊJ�n(���̓S��) |
| 1872(M 5)/10/14 | S | �V���|���l�Ԑ����J�� |
| 1883(M16)/07/28 | S | ���{�S���E���|�F�J�ԉ��c�ƊJ�n(���̎��S) |
| 1885(M18)/03/01 | N | ���{�S���E�ԉH�|�i��ԊJ�ƁA�V���ɏ����ꊯ�S�Ƃ̒��ʉ^�]�J�n |
| 1889(M22)/07/01 | N | ���C�����E�[�J(�ւ���-���l��)�|�Č��|�n��(���V��)�J�ƁA�V���|�_�ˊԑS�� |
| 1891(M24)/09/01 | N | ���{�S���E����-�X�ԊJ�ƁA���|�X�ԑS�� |
| 1892(M25)/06/21 | N | �S���~�ݖ@���z |
| 1895(M28)/02/01 | S | ���s�d�C�S���J��(���̓d�C�O��) |
| 1903(M36)/08/22 | N | �����d�ԓS���E�i��|�V���ԊJ�ƁA�ȍ~���Ћy�ѓ����s�X�S���A�����d�C�S���̎O�Ђ������s���ɘH�ʓd�ԖԊg�[(�O�Ђ�1906/09/11�����������S���ƂȂ�A1911/07/31�����s�ɔ��������) |
| 1904(M37)/08/21 | S | �b���S���E�ѓc���|����Ԃɓd�ԉ^�]�J�n(�S���ɂ�鏉�̓d�ԉ^�]) |
| 1905(M38)/04/12 | S | ��_�d�S�E���~�c�|�_�˕���(�O�{)�ԊJ��(���̓s�s�ԓd�ԉ^�]) |
| 1906(M39)/04/19 | N | �S�����L�@���z(4/20�{�s)�A�S��17�̎��S�̘H����4,800�L���� |
| 1912(M45)/06/15 | N | ���̢���}�1�A2��Ԃ�V���|���֊Ԃɐݒ�A�֊��A���D���o�R���ăA�W�A�嗤�̓S���ƘA�� |
| 1919(T 8)/03/01 | N | �������E�����|�������ԊJ�ƁA����|�����|�i��|�V�h�|���Ԃ̢�̣�̎��^�]�J�n |
| 1922(T11)/04/10 | N | �����S���~�ݖ@���z(4/11�{�s) |
| 1925(T14)/11/01 | N | �_�c�|���ԊJ�ƁA�R����̊�^�]�J�n |
| 1927(S 2)/12/30 | S | �����n���S�E���|�ԊJ��(���̒n���S) |
| 1930(S 5)/03/15 | S | �����|���{��Ԃɓd�ԉ^�]�J�n(���̍����d��) |
| 1930(S 5)/10/01 | N | ���}�����A�����|�_�ˊԂʼnc�Ɖ^�]�J�n |
| 1934(S 7)/12/01 | N | �O�߃g���l���A�⓿���A�L�����̊J�ʂɂƂ��Ȃ��A���C�����A�R�z���A������̉^�]�n����ύX |
| 1942(S17)/06/11 | N | �֖�g���l�������B�ݕ��c�Ƃ�7/1�A���q�c�Ƃ�11/15�J�n |
| 1943(S18)/04/01 | N | ����c�S��(����c���E����c�|����c�`��)���B�ȍ~43�A44�N��22���S1,067�L����펞����� |
| 1949(S24)/06/01 | N | ���{���L�S���@�̎{�s�ɂ����{���L�S��(�i�m�q)�ݗ� |
| 1956(S31)/11/19 | N | �i��|�c�[�ԂŎR����E���l���k���d�Ԃ̕����ʕ��X���^�]�J�n |
| 1958(S33)/10/01 | S | ���S�_�C�������A�Œ�Ґ��̓��}������ܣ�E�����������o�� |
| 1959(S34)/07/15 | N | �I���{���S�ʁA���{�̊����S���l�b�g���[�N���� |
| 1960(S35)/12/04 | N | �s�c�n���S�Ƌ����d�S�A����ő��ݏ�����J�n |
| 1961(S36)/11/01 | N | ���S�_�C�������A�F��E�k���E�R�A�E���H�E�H�z�E�M�z�E���يe���ɓ��}�V�� |
| 1964(S39)/10/01 | S | ���C���V����(�����|�V����)�J�� |
| 1968(S43)/10/01 | N | �����颂��Ƃ���_�C�������A���}�Ԃ�S���Ɋg�� |
| 1970(S45)/05/18 | S | �V���������@���z(6/18�{�s) |
| 1971(S46)/04/20 | S | ����X�����A�����^�]�J�n�B�k��Z�E�����Ԃ́A�����������S�A�ɍs�����c�c�ƕ������L����� |
| 1972(S47)/10/02 | S | ���S�_�C�������A��Ђ裁A��Ƃ���Ȃǂ�L���}��Ɏw�� |
| 1972(S47)/11/12 | S | �����s�d�́A�r������c���S���p�~ |
| 1975(S50)/03/10 | S | �R�z�V����(�V���|������)�S�� |
| 1980(S55)/10/01 | S | ���S���̌��ʃ_�C�������B�Q����}�̍팸�E��ԒZ�k�����{�A�}�s��啝�ɐ��� |
| 1980(S55)/12/27 | S | ���S�o�c�Č����i���ʑ[�u�@���z(81/3/11�{�s)�A����n����ʐ��̔p�~������ |
| 1981(S56)/10/01 | N | �Ώ����J�� |
| 1982(S57)/06/23 | S | ���k�V����(��{�|������)�J�ƁB���̂���7/1�̖x�]�q�H�̔p�~�܂Ţ�Œ��Г������գ���ł��������������ł��� |
| 1982(S57)/11/15 | S | ��z�V����(��{�|�V����)�J�� |
| 1983(S58)/03/22 | S | �}��������E�Õl�Ԕp�~�B�����s�c�n���S�J�ƁA�}����������� |
| 1985(S60)/07/26 | S | ���S�Č��ė��ψ���S���v�Ɋւ���ӌ����ɒ�o(10/11�t�c����) |
| 1987(S62)/04/ 1 | S | ���S�������c���ɂ��i�q�O���[�v�a��(���q�U�ЁA�ݕ��P��)�B�S�����Ɩ@�{�s |
| 1988(S63)/03/13 | N | ���g���l��(�Ìy�C����)�J�� |
| 1988(S63)/04/10 | N | ���ˑ勴(�{�l���]��)�J�� |
| 1991(H 3)/03/19 | S | ���c��`���J�ƁA����c�G�N�X�v���X��^�s�J�n |
| 1992(H 4)/07/01 | S | �R�`�V����(�����|�R�`��)�J�ƁA�V�ݒ��ʉ^�]�J�n |
| 1993(H 5)/10/26 | S | �i�q�����{������� |
| 1994(H 6)/06/15 | S | ����`���J�ƁA��͂邩��A����s�[�g��^�]�J�n |
| 1996(H 8)/01/10 | S | JR�k�C���AJR�l���AJR��B���^�������BJR�e�Ђ̈ꗥ�^���̌n������� |
| 1997(H 9)/03/08 | N | �i�q�������J�ƁA���w�œ��C�����_�˕��ʁE���m�R���Ƃ̌��ݒ��ʕ��������{ |
| 1997(H 9)/10/01 | S | �k���V�����E����|����ԊJ�ƁA����E�y���Ԕp�~�A�y���E�m��ԑ�3�Z�N�^�[�� |
| 2001(H13)/12/01 | N | �Ó�V�h���C���J�ʁA���C�����E���{����Ɠ��k���E������Ƃ̊ԂŁA���n�_�Ԃ̒��ʉ^�]�J�n |
| 2001(H13)/06/22 | S | �i�q�����{�A�i�q���C�A�i�q�����{�����ԉ�Љ� |
| 2002(H13)/12/01 | S | ���k�V�������ˉ��L�J�ƁB�����|���ˊԑ�3�Z�N�^�[�Ɉڊ� |
| 2004(H15)/03/13 | S | ��B�V�����J�ƁB����|����ԑ�3�Z�N�^�[�Ɉڊ� |
| 2006(H18)/04/29 | N | �x�R���C�g���[���J�� |
| 2007(H19)/03/18 | N | PASMO�f�r���[�ASuica�Ƃ̑��ݏ�����J�n |
| �E | �S���S�N���j�҂���ψ���u�S���S�N���j�1972/10�A�S���}�����s�� |
| �E | �r�c����Ғ��u�S�������N�\�@1972-93�v1993/08�A�������@ |
| �E | ��v�ۖM�F�E�O��F�E�]�c�p�v�ҁu�S���^�A�N�\�v1999/01�AJTB |
| [1] | JAL�̍��ې������\�́A�u���b�h�V���E���ł���B�r����`����ʓI����������̖��c���낤�B�t�ɁA�S�������\�ɂ��A�C�M���X��ABC RailwaysGuide�̂悤�ɔ����w�ŕ\������`��������(�����������h���Ɗe�s�s�Ƃ̑��݊Ԃ݂̂��L��)�B��ʗ��s�҂́A�ʉ߂���H���ɋ������Ȃ��A�ړI�n�܂ł̎����ׂ����̂�����A������̂ق������₷���̂�������Ȃ��B���B�ł͓��{�̂悤�ɓS�������\�����y���Ă��炸�A��ʗ��s�҂͉w�̏o�D�����ŌW���ɐq�˂Ă���B���������@�����y���Ă��Ȃ����ƂƂ����܂��āA�o�D���ɒ��ւ̗ł��A�������炢�炳������B | ||||||||||||
| [2] | �n���S���V���g���^�ł���̂́A���{�����łȂ��C�O�̑�s�s�ɂ����Ă����ʂ��Ă���B���̒��Ńj���[���[�N�̒n���S����������ŁA�s�S���̃}���n�b�^�����ł́A�����̌n���i�����E�ɍs�j�������H���i���X���j���^�s����l�b�g�^�A�����s���Ă���B�j���[���[�N�͘H�ʓd�Ԃ̎�����o���A�����Ȃ�n���S�����݂��ꂽ���ƂɊW������̂�������Ȃ��B�Ȃ������n���S�ł��A�ՊC���ōs����ԉΑ���N���N�n�̃C�x���g���ɁA�L�y�����E��k���̗��s���J�w����c�������ցE�L�y�������c������ԒZ�������o�R���ėՎ���Ԃ��^�s����A��O�I�Ƀl�b�g�^�A�����s���Ă���B | ||||||||||||
| [3] | �o�c������܂ꂽ�O����Ђ̌o�c��Ղ��m�ۂ����U�[�u�Ƃ��ĎO��������݂���ꂽ�B1996�N�̎O����Ђ̉^�������ɂ��A�S������^���̌n�͕����B | ||||||||||||
| [4] | �{�e�ł́A���q�A���ɂ��ďq�ׂĂ��邪�A�ݕ��A�����R���e�i���A���[�h�̔p�~�ɂ���ċ��_�Ԃ̃V���g���^ �A���ɕω����Ă���B�S���ݕ��A���́A�������H�Ԃ̃g���b�N�Ɠ��q�C�^�̊g��ɂ��A���A����(�g���E�L��)�A�V�F�A�Ƃ��Ɍp���I�Ɍ������Ă���B�ݕ��w���p�~����A�����̊e�w�ɂ������ݕ���ԗp�ޔ��������ݐ����g���Ȃ��Ȃ����B���S�̉ݕ��A���͒����S���A�O��S���y��JR�ݕ����o������e�n�̗ՊC�S�����̉ݕ���ƓS���������قڐ�ł����B��莄�S�ʼnݕ��A�����p�����Ă���̂́A�����A���S�A���S��3�Ђ����ł���(2002�N10��������)�B | ||||||||||||
| [5] | JR������ɊJ�݂��ꂽ�w(�V���̉w������)�́A141�ɏ��(JR�����{28�AJR���C14�AJR�����{39�AJR�l��3�AJR��B47�AJR�k�C��13)�BJR��B���w�̐V�݂ɐϋɓI�ŁA�Ƃ���5�̑�w�O�w��ݒu��(�ق��ɐV�c������B�H��O�ɉ���)�A�ʊw�A�����v�̎�荞�݂ɂƂ߂����Ƃ͒��ڂɒl����B | ||||||||||||
| [6] | 2004�N10���̃_�C�������ŁA���C������Ԃ̕��ω^�s�������������������BJR�����{��JR���C�Ԃ̒��ʗ��(�É��E���Ís�j��������������A�Ó�V�h���C���ɑO�������̒�������Ԃ��呝�����ꂽ���߂ł������B�Ƃ��낪�A2005�N3�������ŋ�B�s���̃u���[�ƃ��C����1�{�����ɂȂ�A�Ăѕ��ϑ��s�����͌��������B�������ł́A��V���J�ƂɑR����2005�N7�������ŁA�ߋ����̓y�Y�s���A���c�s���̕��ʗ�Ԃ����ꂼ��1�{���팸�i���}�������j�A���킫�s�����ʗ�Ԃ�1�{��������A���ϑ��s������0.7�L�����������B�������A2007�N3���̃_�C�������ł��킫�s�̕��ʗ�Ԃ��S�p����A���ϑ��s���������������B | ||||||||||||
| [7] | ���đ��݂����l�K���ė���́A���̂R��Ԃł���B
|
||||||||||||
| [8] | ��Ԃ̕����E�����̓��[���b�p�ɂ����č��ۋK�͂ōs���Ă����B1979�N���_�̃x���M�[�E�I�X�e���f���́u�����}�s�v�̓x�������A�����V�����o�R���X�N���s�A�n���u���O�o�R�R�y���n�[�Q���s�A�~�����w���o�R�U���c�u���O�A���B���n�s�̗�ԂŁA�e���̎ԗ������Ă����BTGV�������V���̌��݂ɂ�胈�[���b�p�ɂ����Ă��l�b�g�^����V���g���^�ւ̕ω��������邪�A����ňقȂ������̋q�Ԃ�����l�b�g�^�A�������݂ł���B | ||||||||||||
| [9] | ���S�̔����́A�����m�푈���ɂ����{����A1943�N4���̏���c�S��(����c��)�����߂Ƃ��āA�L��E�P�����E�O�M�E�ɓߓd�C�S��(�ѓc��)�A�앐�S��(�앐���A�ܓ��s��)�A�~�d�C�S��(�~��)�A�{��d�C�S��(��ΐ�)�Ȃ�22�S���A1,067�L�����������ꂽ�B | ||||||||||||
| [10] | ���ǂ낭�ׂ����ƂɁA�S���~�ݖ@��1987�N�̍��S���c���܂ő������A���S���Ԏ��ɂȂ��Ă�����ꕔ�̐Ԏ��H����p�~�������ŁA�̎Z�̌����݂̗����Ȃ��ʂ̃��[�J���H�������݂��������@�I�����ɂȂ��Ă����B��~�݃X�w�L�H������߂��S���~�ݖ@�ʕ\��147��2�ɢ���H�����f�����\��������j�����S���������B���̔��f���́A�S���{�ݖ@�ɏ]���Č��݂��i�݁A1964�N10��7�����f�|�㒃�H�Ԃ��A1972�N9��8���㒃�H�|�k�i�Ԃ��J�Ƃ����B����������܂Ő��H���L�т邱�Ƃ͂Ȃ��A���S�o�c�Č����i���ʑ[�u�@�œ���n����ʐ��Ɏw�肳��A1983�N10��23���S�����p�~���ꂽ�B�㒃�H�|�k�i�Ԃ�11�N�̎��������Ȃ������B | ||||||||||||
| [11] | ���S�o�c�Č����i���ʑ[�u�@�́A��8���ŁA�����S���Ԃ��\������H���������A�K�ȑ[�u���u���Ă����x�̋ύt������ȘH��(�n����ʐ�)�y�ђn����ʐ��̂����p�~���ăo�X�ɓ]������H��(����n����ʐ�)�I�肵�A��9���ŁA�H�����Ƃɓ���n����ʐ��c��̋��c���o�āA�p�~����\������Ƃ����葱�����߂��B���S�o�c�Č����i���ʑ[�u�@�{�s��(81/3/11)�ɂ��A�n����ʐ��y�ѓ���n����ʐ��̊�́A���̂Ƃ����߂�ꂽ�B���S�̐��H���̂���Ɉꗥ�ɓK�p���Ă���̂ŁA�K���������ԂƂ���Ȃ������B
�����F�i1)�l��10���l�ȏ�̓s�s(��v�s�s)�𑊌݂ɘA�����A���q�c�ƃL����30�L�����A���ׂĂ̗אډw�Ԃ̗��q�A�����x(�L���������1�����ϗA���l��)��4000�l�ȏ�̘H���A(2)1�̘H���Ǝ�v�s�s��A�����A���q�c�ƃL����30�L�����A���ׂĂ̗אډw�Ԃ̗��q�A�����x(�L���������1�����ϗA���l��)��4000�l�ȏ�̘H���A(3)�ݕ��A�����x��4000�g���ȏ�̘H�� �n����ʐ��F���q�A�����x���A8000�l�����̘H��; ����n����ʐ��F���q�A�����x���A4000�l�����A������1.�אډw�Ԃ�1���Ԃ�����̍ő嗷�q�A���l����1000�l�ȏ�̘H ���A2.���H�̐����ɂ��o�X�]�����s�\�ȘH���A3.�ϐ�ɂ��o�X���s�s�\���Ԃ�1�N������10������H���A4.���q��l������̕��Ϗ�ԋ�����30�L�����A�����ϗA�����x��1000�l����H�������� |
||||||||||||
| [12] | �����s�]���悪�������Ă���T�ˁ|�V�؏�Ԃ�LRT���v��ł́A�S��5.8�L���̂����������ݕ��x��(�z�����ݕ���)�̐��H3.8�L���𗘗p���A���ݔ�̍팸��}�낤�Ƃ��Ă���B | ||||||||||||
| [13] | �ŋ߂ɂȂ��āA������ʈړ��~�����ݔ�������⏕���x�ɂ��Ᏸ�����q(LRV)�̍w���ɕ⏕�����o��悤�ɂȂ����B�Ȃ��A�s�s���̓S�O���n��ʋ@�ւ̐����ɑ���ł�������⏕���x�́A�^�A�{�ݐ������ƒc�ɂ���n�������S���������Ɣ�⏕���x�ł���B���̂��߁A���v���傫���Ȃ��n���s�s�ɂ����Ă��A�̎Z��x�O�������t���K�i�̒n���S�����݂��ꂽ�B���S�s�X�n�̂ݒn���̐�p�O���𑖍s����LRT�ŏ\���ł������B | ||||||||||||
| [14] | �S�����Ɩ@�{�s�K����37���1���Œ�߂���p���~�����̋�̓I�[�u�͈ȉ��̂Ƃ���B
|
||||||||||||
| [15] | ���X�����ɂ��������Ɗɍs���̕����́A�������E����|���E��(61/4)�A���E�|�O���(69/4)�A����E�k��Z�|�䑷�q��(71/4)�A�������E�ю����|�Óc����(72/7)�A�Óc���|��t��(81/7)�B
���l���k���d�Ԃ��ɍs���̖������ʂ����Ă������C�����Ɠ��k���́A�ݕ�����V�݂��A����������Ԑ����番�������B����ɂ�蓌�C�����ł́A1980�N10���A���{����d�Ԃ����ݕ����ɕ����A�i��-�����Ԃ̒n���V�����o�R���đ����������ƒ��s����B�܂��A1988�N7���V�݂����H��ݕ������g�p����������q��Ԣ�V�h�Ó색�C�i�[��̉^�]���J�n����B���k���ł��A���������ݕ������g�p���āA1988�N3���A���k���E������̒r�܍s�������d�Ԃ̉^�]���J�n�A2001�N12���A�V�h�Ó색�C���Ƃ��āA���C���E���{����ɒ��ʂ���B |
||||||||||||
| [16] | JR�����{�̕��m�R���̒E�����̂Ɋւ��āA���S�Ƃ̋����ɏ����߂́u�A�[�o���l�b�g���[�N�v�헪���������E�����D��̌o�c���j�Ƃ��Ĕᔻ����Ă���B ���m�R���Ɠ������̏�����ɔ������H�t���ւ��ɂ���Ĕ�������̃J�[�u�i�Ȑ����a300���[�g���Ŋɘa�Ȑ����قƂ�ǂȂ��j���������Ƃ̂��Ƃł���A���ݏ����ꂪ���̂̉����Ƃ��邳��Ă���悤���B�������A���w�̓���z�[����芷���E���ݒ��ʉ^�]�ɂ��ڑ��̃V�[�����X���ɂ���ė��q�̕X��}�邱�Ƃɖ�肪����̂ł͂Ȃ��A���̂��߂̈��S���m�ۂ�ӂ������Ƃ����ł��邱�Ƃ��������Ă��������B | ||||||||||||
| [17] | �S�����Ɩ@�̏�p�~�����[�u�ɉ����āA2005�N�ɂ́A�s�s�S�������֑��i�@�����肳�ꂽ�B�u�����̓s�s�S���{�݂�L�����p���s���s�s�S�����֑��i���Ƃ��~���� ���{���A�����Č�ʌ��ߋ@�\�̍��x����}��v���Ƃ�ړI�Ƃ��āA�����̓S����A������V���̌��ݓ��́u���B�����㎖�Ɓv�Ə�芷���̗�������̂��߂́u�w�{�ݗ��p�~�������Ɓv���߂Ă���B |
| 2004/11/15�F | 2004�N10���_�C�������A2003�N�ȍ~�̐V���J�Ɠ��f���A�}�\��lj����đ啝�ɉ����B |
| 2005/07/09�F | �}�Q��2004�N10�������_�C����2005�N3��(���C����)�A7��(���)�����_�C���ɕύX�B�ʕ\�P�̑��s��Ԃ��ڍׂɋL�ځB��16��lj��B |
| 2006/11/19�F | �ڎ���ݒu�B�\�P��2006�N�����݂̃f�[�^�ɕύX�B�ʕ\�Q�A�R�ɂ��̌�2006�N���܂ł̊J�ƁE�p�~��Ԃ�lj��B�l�b�g���E�V���g�����N�\�ɒNjL�B |
| 2007/06/09�F | �}�P��V�݁i�}�P-�R��}�Q-�S�ɕύX�j�B�}�Q�̗��q�A���V�F�A�̐��ڃO���t�ɁA2004�N�̃f�[�^��lj��B�}�R��2005�N3��(���C����)�A7��(���)�����_�C����2007�N3�������_�C���ɕύX�B�\�P��2007�N3�������݂̃f�[�^�ɕύX�B�ʕ\�Q�A�R���ŐV�f�[�^�ɕύX�B�u�S���l�b�g���[�N�����������v�̏͂��č\�����A�u�l�b�g���[�N�����̒����v��lj��B���S�̂i�q�A���}������v��ɂ��ĒNjL�B�l�b�g���E�V���g�����N�\�ɒNjL�B |